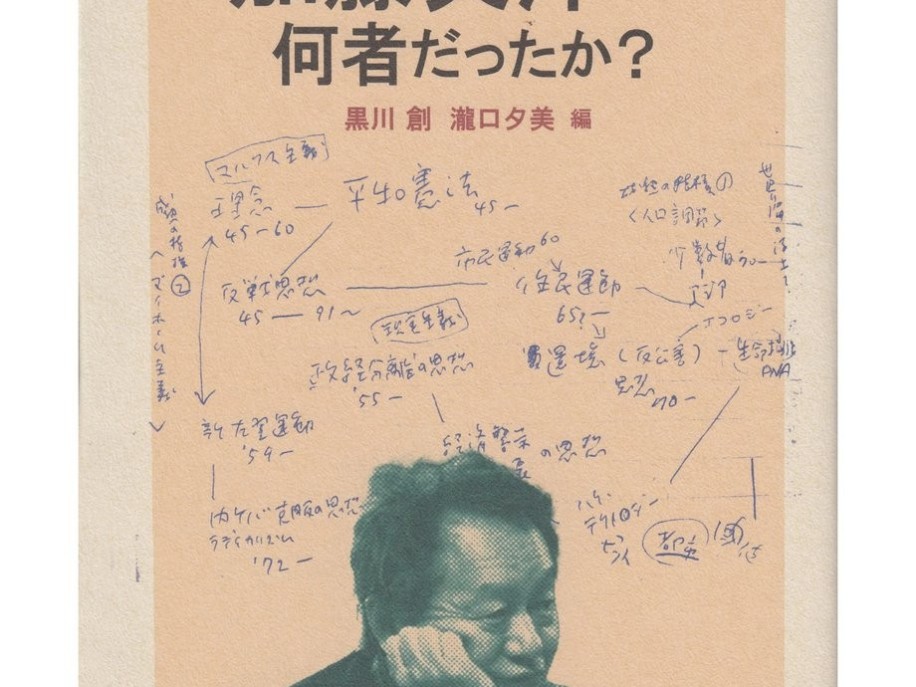自著解説
『職業としての大学人』(文学通信)
「二〇二一年一一月二日、この日、私は東京地方検察庁特捜部に呼び出されていた」。4月末に刊行した『職業としての大学人』(文学通信)は、この一文から始まり、いわゆる日大事件の渦中にいた著者が、メモと記憶にしたがって書き下ろした圧巻の93,000字を収録する。元理事や前理事長の逮捕・起訴といったこの事件は、しかし、日本の大学行政の問題点をも明るみに照らし出した。「大学改革」のかけ声ばかりが先行し、学問や教育が痩せ細るなか、大学への信頼はどのように取り戻せばいいか。近現代日本文学の研究者が、「大学人」として、大学をおおう「言葉」を思索する。
最近、言葉を使うときに、思わず立ち止まったり、ためらいを覚えたりする場面が多くなった。よく使われている言葉だけれども、果たしてその意味は自分のなかでよく消化できているのか。そんなとまどいや躊躇を感じることがある。
テレビを見ていたり、新聞を流し読みしたりしているときにそんなことを感じるのなら分からないでもない。そうではなく、大学の、しかも学問のあり方や根本についてのかなり真剣な話題のなかで、そうしたためらいを覚えることがある。大学をふくめた高等教育の行政、その中枢の議論で、言葉の使い方に疑問を覚えたとしたら、事はたんなる個人の感想というだけにとどまらなくなる。
Society5.0などはその最たるものだが、まだ英語で知ったかぶりをするのはむかしから洋学かぶれの典型とからかわれたものである。しかし、多様性とか、主体性という言葉になると、簡単に笑えなくなる。戦後、七〇年以上にわたって、これらの言葉を意味あるものにするために、多くの人たちが悪戦苦闘してきた。歯が浮くような、日本の伝統的な語彙にない言葉であるだけに、その言葉を定着させるために、多くの人たちが定義、再定義をくりかえし、その意味のために批評や論争を避けずにやってきた。しかし、その言葉がこの間、ふたたび中味のない宙に浮いた言葉になってきていないか。
私がたまたま気づいたのは、高校の教育カリキュラムを変更しようとして、学習指導要領が改訂され、高大接続の改革の名のもとに、大学入試制度の改変が議論されていたときである。少し前から、教育において「生きる力」が獲得の目標にされていた。「生きる力」?それが教育のなかで重要なテーマなのか。その「生きる力」のために、「思考力・判断力・想像力」を身につけることが錦の御旗になった。「判断力」を手に入れるにはどうしたらいいのか?
ふつうの言語センス、地に足のついた思考パターンでいけば、題目にかかげただけでとまどいを覚える。もちろん、私たちはときに曖昧な言葉を旗印にかかげたり、スローガンにしたりする。分かってやっているならばいいが、教育のカリキュラム設定の文脈で、それは空疎な言葉にならないか。言葉に敏感になり、その言葉に応じた立ち居振る舞いを問うことで、大人の常識に疑問を投げかける成長期の若者たちに、そんな言葉で果たして立ち向かえるのだろうか。
しかし、高校の場面だけでなかった。実はすでに大学も、大学院もこうした空疎な言葉に取り巻かれ、あたかも意味ある言葉であるかのように「多様性」や「主体性」、「対話」や「アクティブ」という言葉を交わしていないと、そのなかで生きていけないようになってしまっていた。
「対話型授業」や「アクティブ・ラーニング」という言葉を多用しながら、自分はどこまで対話的か、ふりかえってみる。対話しているつもりで対話になっていない。同じように分かっているもの同士の対話になっていて、ほんとうの「対話」になっていない。「アクティブ」と言いながら、やらされている感覚が強いのはどうなのだろう。これは「主体性」の現れと言っていいのか。
もちろん、丸山真男が言っていた「主体性」は東京大学法学部というエリートの頂点に守られていたものではないか。そうした反問が半世紀前にくりだされたことをよく覚えている。同じことを目指すべきではない。しかし、言葉について絶えず問い直し、その意味がどこまで生きたものになっているか、そうしたふりかえりがなくて、果たして学問は成り立つのだろうか。
いまや大学という場所も、がんじがらめに空疎な言葉に縛られている。授業はあらかじめ詳細なシラバスで細目を確定しておかなければならない。この授業を通して、何の力を身につけることができるのか。それは求められている能力のどれとどれに該当するのか。授業の前と後に何を予習し、何を復習するのか。細かくナビゲーションして、いまどこに立っているかが分かるようにしなさい。
ほとんど虚構の王国である。自分がどこに立っているか分からないから、思索が始まる。私が『職業としての大学人』で書きたかったことのもそのことだと、いまになって思う。虚構から目覚めよ。いま私たちは壮大な虚構におおいつくされている。
[書き手]紅野謙介(こうの・けんすけ)
1956年東京都生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程中退。日本大学文理学部特任教授。専攻は日本近代文学。著書に『書物の近代』(ちくま学芸文庫、1999)、『投機としての文学』(新曜社、2003)、『検閲と文学』(河出ブックス、2009)、『物語岩波書店百年史1 「教養」の誕生』(岩波書店、2013)、『国語教育の危機 大学入学共通テストと新学習指導要領』(ちくま新書、2018)、『国語教育 混迷する改革』(ちくま新書、2020)など。
中味のない、宙に浮いた言葉
最近、言葉を使うときに、思わず立ち止まったり、ためらいを覚えたりする場面が多くなった。よく使われている言葉だけれども、果たしてその意味は自分のなかでよく消化できているのか。そんなとまどいや躊躇を感じることがある。
テレビを見ていたり、新聞を流し読みしたりしているときにそんなことを感じるのなら分からないでもない。そうではなく、大学の、しかも学問のあり方や根本についてのかなり真剣な話題のなかで、そうしたためらいを覚えることがある。大学をふくめた高等教育の行政、その中枢の議論で、言葉の使い方に疑問を覚えたとしたら、事はたんなる個人の感想というだけにとどまらなくなる。
Society5.0などはその最たるものだが、まだ英語で知ったかぶりをするのはむかしから洋学かぶれの典型とからかわれたものである。しかし、多様性とか、主体性という言葉になると、簡単に笑えなくなる。戦後、七〇年以上にわたって、これらの言葉を意味あるものにするために、多くの人たちが悪戦苦闘してきた。歯が浮くような、日本の伝統的な語彙にない言葉であるだけに、その言葉を定着させるために、多くの人たちが定義、再定義をくりかえし、その意味のために批評や論争を避けずにやってきた。しかし、その言葉がこの間、ふたたび中味のない宙に浮いた言葉になってきていないか。
「生きる力」?「判断力」?
私がたまたま気づいたのは、高校の教育カリキュラムを変更しようとして、学習指導要領が改訂され、高大接続の改革の名のもとに、大学入試制度の改変が議論されていたときである。少し前から、教育において「生きる力」が獲得の目標にされていた。「生きる力」?それが教育のなかで重要なテーマなのか。その「生きる力」のために、「思考力・判断力・想像力」を身につけることが錦の御旗になった。「判断力」を手に入れるにはどうしたらいいのか?
ふつうの言語センス、地に足のついた思考パターンでいけば、題目にかかげただけでとまどいを覚える。もちろん、私たちはときに曖昧な言葉を旗印にかかげたり、スローガンにしたりする。分かってやっているならばいいが、教育のカリキュラム設定の文脈で、それは空疎な言葉にならないか。言葉に敏感になり、その言葉に応じた立ち居振る舞いを問うことで、大人の常識に疑問を投げかける成長期の若者たちに、そんな言葉で果たして立ち向かえるのだろうか。
学問の場をおおう空疎な言葉
しかし、高校の場面だけでなかった。実はすでに大学も、大学院もこうした空疎な言葉に取り巻かれ、あたかも意味ある言葉であるかのように「多様性」や「主体性」、「対話」や「アクティブ」という言葉を交わしていないと、そのなかで生きていけないようになってしまっていた。
「対話型授業」や「アクティブ・ラーニング」という言葉を多用しながら、自分はどこまで対話的か、ふりかえってみる。対話しているつもりで対話になっていない。同じように分かっているもの同士の対話になっていて、ほんとうの「対話」になっていない。「アクティブ」と言いながら、やらされている感覚が強いのはどうなのだろう。これは「主体性」の現れと言っていいのか。
もちろん、丸山真男が言っていた「主体性」は東京大学法学部というエリートの頂点に守られていたものではないか。そうした反問が半世紀前にくりだされたことをよく覚えている。同じことを目指すべきではない。しかし、言葉について絶えず問い直し、その意味がどこまで生きたものになっているか、そうしたふりかえりがなくて、果たして学問は成り立つのだろうか。
虚構から目覚めよ
いまや大学という場所も、がんじがらめに空疎な言葉に縛られている。授業はあらかじめ詳細なシラバスで細目を確定しておかなければならない。この授業を通して、何の力を身につけることができるのか。それは求められている能力のどれとどれに該当するのか。授業の前と後に何を予習し、何を復習するのか。細かくナビゲーションして、いまどこに立っているかが分かるようにしなさい。
ほとんど虚構の王国である。自分がどこに立っているか分からないから、思索が始まる。私が『職業としての大学人』で書きたかったことのもそのことだと、いまになって思う。虚構から目覚めよ。いま私たちは壮大な虚構におおいつくされている。
[書き手]紅野謙介(こうの・けんすけ)
1956年東京都生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程中退。日本大学文理学部特任教授。専攻は日本近代文学。著書に『書物の近代』(ちくま学芸文庫、1999)、『投機としての文学』(新曜社、2003)、『検閲と文学』(河出ブックス、2009)、『物語岩波書店百年史1 「教養」の誕生』(岩波書店、2013)、『国語教育の危機 大学入学共通テストと新学習指導要領』(ちくま新書、2018)、『国語教育 混迷する改革』(ちくま新書、2020)など。
ALL REVIEWSをフォローする