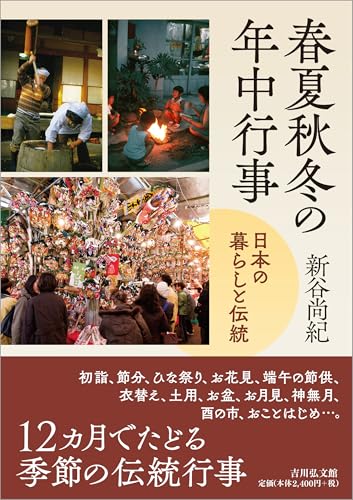書評
『むしろ幻想が明快なのである ――虫明亜呂無レトロスペクティブ』(筑摩書房)
一瞬のプレーに美の意味を問う
虫明亜呂無は本名である。一九二三年、東京生まれ。父は萬鉄五郎に師事した画家の虫明柏太で、亜呂無は芳香を意味するフランス語アロムからとられたという。スポーツ、演劇、映画、音楽、文芸、競馬等、さまざまなジャンルをその名のとおり香り高く色彩感覚にあふれた文体で軽々と越境する散文作品を残して、彼は九一年に世を去った。没年以後、その仕事は幾度か再編されてあらたな読者を獲得してきたが、仕事の幅の広さゆえに、便宜上、どうしても分野別にせざるをえない側面があった。その意味で、本書は虫明亜呂無にはじめて触れる読者だけでなく、彼の世界をあくまでひとつの言語圏として味わいたいと願う愛読者にもありがたいアンソロジーになっている。
全篇に貫かれているのは、身体への、生命へのまなざしである。その核をなすのは、著者が十代の少年だったころに観た「職業野球」の記録映画から書き起こされる「名選手の系譜」と、ベルリン・オリンピックの年の私的な記憶を交えながらサッカーについて綴られた「芝生の上のレモン」である。どちらも長尺だが、これがスポーツの精髄だと彼が見定めた領域に身を浸しきってその感覚を言葉で伝えようとする文学的な試みで、あえて言えば前者は交響詩に、後者は小説の感触に近い。
野球やサッカーの本質は、勝ち負けにはない。特定の選手を祭り上げて騒ぐことでもない。賛嘆の対象はあくまでプレーのうつくしさにあるべきだと著者は熱く繰り返す。観客のいない戦前の球場の、「頽廃にちかい孤絶の状態」でとらえられたプレーの数々。「人間のからだが、あのように伸び、曲がり、蹴り、投げ、走ることから、いわば、舞踊のエッセンスともいえる美の造型にむかって、もてる力のすべてを集中する」ことに彼は心を打たれる。
一瞬の動きをとらえ、選手の心理や生理までをも追い、奇跡的な美のすばらしさを理解するには、時間が必要である。観る側も「待たねばならない」。それだけでなく、「ひとは待ちながら、スポーツをとおして、自分を知ってゆかねばならない」。
しかも凝視の対象は単体だけではない。サッカー選手たちの波状の動きや、競馬レース中の馬群のダイナミスムへの傾倒は、内田叶夢監督の「宮本武蔵 一乗寺の決斗」の撮影現場ルポにあるとおり、そこにはない身体の動きを官能的な情景描写のなかに幻出させる筆力と不可分のものだ。
忘れてならないのは、著者の戦争体験だろう。昭和二十年八月十五日、彼は九州・都城の飛行場で、飛行戦隊の兵士として、特攻隊出撃の準備をしていた。死は間近に迫っていた。しかし戦争は「季節の自然の推移のように」終結した。
敗戦のあっけなさは、緊迫した一瞬のプレーの美の意味を問い直すだけでなく、戦場で失われた身体にもありえたであろう舞踏を幻視し、自分を知るための契機となったのではないか。博覧強記もただの知識の集積ではなく、身体と密接に結びついた言葉に等しいものだったろう。
虫明亜呂無の香りに含まれている原料は想像以上に複雑である。読者は楽しみつつも、その真のあらわれを「待たねばならない」。
ALL REVIEWSをフォローする