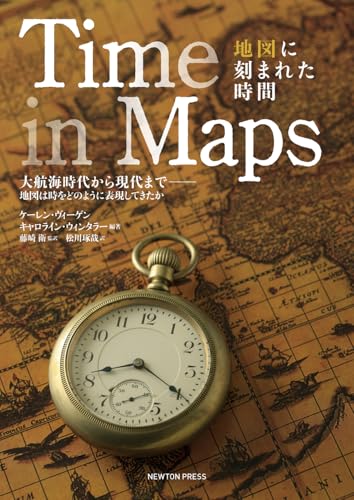書評
『プリニウス12』(新潮社)
観察で究めようとする知性と心性
プリニウスは1世紀に実在した人物だから、まずは『世界史辞典』(角川学芸出版)の素描「ローマの軍人、政治家、学者。北イタリアのコモの騎士身分の家に生まれる。23歳頃から12年間ライン地方で軍務に服し、イタリア帰国後10年ほど文筆活動に専念。ウェスパシアヌス帝により属州財務に登用され、見聞を広めつつ著作活動を続けた。晩年ナポリ湾ミセヌムの艦隊司令官に任じられ、79年ヴェスヴィオ火山の噴火の際にポンペイ近くのスタビアエで殉職。多作であったが、百科全書的な情報の宝庫たる『博物誌』全37巻のみ現存する」で輪郭がわかってもらえる。こんな男だから、幼少期から昆虫や樹木に好奇心あふれ、長じて自然界の森羅万象に目が向かったとしても不思議ではない。とにかく何事も自分の目で確かめないと気がすまない。万巻の書に通じていながら、多少の危険があっても現物を観察したい男だった。さかのぼれば、自然現象や動植物の生態への関心も半端ではなかった。かくして古代の膨大な知識が『博物誌』として集大成されたのだ。
イタリア通として知られるヤマザキマリであるが、博物学者プリニウスについてはそもそも「どうしてもこの男が描きたかった」という。さすがに奇人のような偉人の生と死をとりあげるのは目のつけどころがいい。しかも、その執念を実らせるために、相棒に情景描写に巧みなとり・みきを迎えているところが心にくい。鬼に金棒、待ち望まれた合作が完結したのだ。
なぜ地震はおきるのか、なぜ雷鳴が轟くのか。近代科学の洗礼にあずからぬ古代人なら、神々のせいにしたい。だが、頭脳明晰な男には、観察にもとづく合理的な説明がいる。ほかにも、『博物誌』のなかには、書物からの引用や自分の体験を交えて、種々雑多な話題がとりあげられているが、それらを嘘八百やでたらめと断じるべきではない。プリニウスにとっては、自然の謎に迫るために真剣に検討すべき話題であったはずだ。
ところで、この最終巻では、属州ヒスパニア・タラコネンシスからローマに帰還したプリニウスが、親しいウェスパシアヌス帝に出会う場面がある。『博物誌』は同帝に捧げられているから、お互いの友愛が感じられて感動的である。それが史実であったか問うのは、いささか野暮ったいようでもある。
79年夏、ウェスウィウス山が噴火した。プリニウスはそれを目撃する。艦隊司令官としてナポリ湾の港にいたのだから、「燃える山」の実態を知りたくて船を出す。好奇心あふれる男だから、火山の大爆発という自然の大異変に直面すれば、出来事を調査せずにはおれなかった。もともと喘息もちにもかかわらず、降りしきる火山灰・火山礫のなかで息絶えるという壮絶な死に様。観察によって究めようとする古代人の知性と心性が、劇画でこそよく浮かび上がる。
今日の基準からすれば、『博物誌』には虚実こもごもの説明も少なくない。だが、それらは嘘でも大ボラでもない。そこにこそ古代人の心がありありと透けて見える。専門研究者なら避けて通りたい心と知識の系譜学だが、その地平を切り開くには劇画という手法がある。しかも、表情豊かな人物画と緻密をきわめる情景画がほどよく調和していているのだから、心から拍手をおくりたい。
ALL REVIEWSをフォローする