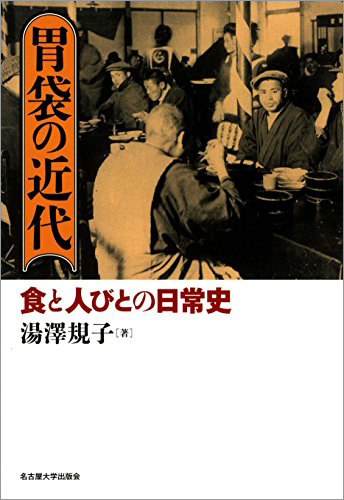書評
『焼き芋とドーナツ 日米シスターフッド交流秘史』(KADOKAWA)
胃袋に注目し描く日米女性工場労働者
甘いものは疲れを癒やし、場の雰囲気を和ませてくれる。いや、甘くなくても、塩辛い煎餅でも。おやつの時間は大切だ。書名にある焼き芋は、近代日本の紡織工場で働いていた女性たちが好んだもの。ドーナツはアメリカの紡織工場の女性たちがおやつに、ときには朝食がわりにしたもの。本書は日米の女性工場労働者がどのように生きたかを描く。著者が注目するのは「日常茶飯」のこと、とりわけ「胃袋」。
象徴的なエピソードが初めのほうに出てくる。「高井としを」という女性がいた。『女工哀史』で知られる細井和喜蔵の内妻、というか『女工哀史』のネタ元。1902年に生まれ、10歳のときから工場で働いた。大和郡山や名古屋の工場を経て1920年、東京・深川の紡績工場にたどり着く。
としをは無一文で、着替えも石鹼もない。シラミがわいて、寄宿舎の同僚にうつってしまう。なにしろ同じ布団を昼夜交替の2人で使うのだから、同僚が怒るのも当然だ。初給料日の翌日、としをは日本橋で着物と襦袢を買い、同室の女工たちには煎餅や饅頭をたくさん買って帰ったという。お菓子が怒りをしずめ、人をつなぐ。
当初、寄宿舎の女工たちは外出を制限されていた。つまり24時間、工場に管理されていた。待遇改善を要求し、自由に外出する権利を獲得する。自分で稼いだお金で買い食いする喜びは大きなものだったろう。女工たちが好んで食べたもののひとつが焼き芋だった。
この本の後半はアメリカの話。高井としをたちの時代よりも1世紀ほど前、19世紀前半の紡織工場。ここでも女性たちの労働は過酷だ。ただし、紹介されているメニューを読むと、寄宿舎の食事は100年後の日本よりもはるかにいいけれども(ローストチキンやベイクドサーモンなどが出て、デザートはパンプディングとコーヒーか紅茶!)。
やがて寄宿舎制度が廃止され、工場労働者たちは自分で食事を用意する。そこで重宝されるのがドーナツやサンドイッチだった。自分で焼く余裕はなかったから、出来合いのものを買って食べた。
『小公女』のバーネットや『若草物語』のオールコット、そして津田梅子や森有礼の名前が登場する。4人ともドーナツが好き? いやいや、そんな話ではなく、アメリカの女工たちは共同組織を作り、雑誌を発行していたというのだ。それがアメリカにおける女性教育の源となり、日本にも影響を与えたというのである。副題「日米シスターフッド交流秘史」とはそういう意味。
これは食べ物ではないが、パッチワークキルトの話が出てくる。小さな布を縫い合わせる手芸。素材になるのは自分が着古した服の一部だった。つまり、過去の時間が縫い合わされている。
しかもパッチワークキルトは数人が集まって共同で作るものだったという。おしゃべりしながら作った布は、結婚や出産祝いに贈られることもあれば、亡骸を包む棺がわりになった。禁酒運動や奴隷解放運動、女性参政権運動では、キャンペーンの旗印としてキルトが作られた。針と糸が彼女たちをつなぎ、思いを伝えた。
おやつの時間、そして仲間とのおしゃべりは大切だ。
ALL REVIEWSをフォローする