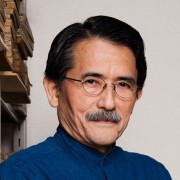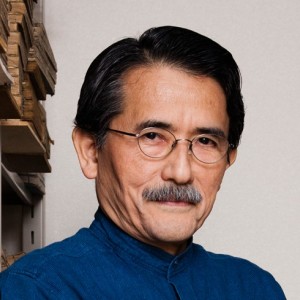書評
『旧制高等学校生の青春彷徨: 旧制府立高校の昭和時代』(彩流社)
亡び去りしものへの挽歌
北杜夫の『どくとるマンボウ青春記』は我が愛読の書であるが、その興味津々たる所以は、著者が松本高校の学生になって、様々な出来事に面食らいながら、それでも大人の世界を垣間見つつ成長していく、そのあたりにあるような気がする。しかし、もう旧制高校出身の世代は寥々たる数になり(もともとごく一握りのエリートたちに過ぎなかったのだが)、新制世代の私どもには、その実態はなんだか雲をつかむように覚束ないことになった。
こういう状況のなかで、旧制東京府立高等学校という、旧制高校群のなかでもまた独特の文化を持った新しい高校の、その創立から廃校までを世潮との対比のなかで綿密に跡付けて見せたのが本書である。
私はこの本に拠って初めて、あの「寮歌」と呼ばれるものが毎年夥しく自作されて歌い継がれていたということを知った。またストームだとか、寮雨(寮の窓からの立ち小便)だとか、稚気溢るる狼藉沙汰のことも本書で具に知ることができた。
しかしながら、最も大切な読みどころは、「大日本帝国の贅沢品」とまで言われた旧制高校という天地には独特の自由があり、アカデミズムがあり、学問というものを真摯に教育しようとした優れた先生たちがいて、その彼らが、どのようにして昭和の軍国主義的潮流からの抑圧に抵抗し、戦中戦後の苦難のなかで学問の片端でも護り教えようと努力したか、そこらのところは、まことに涙ぐましい思いで読まれる。
果ては戦後の学制改革でその全てがあえなく潰えて行く、亡び行くものの悲哀にも筆を及ぼして、まさに余蘊がない。読後、そぞろ「もののあはれ」を憶えたことであった。
初出メディア
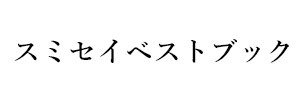
スミセイベストブック 2013年8月号
ALL REVIEWSをフォローする