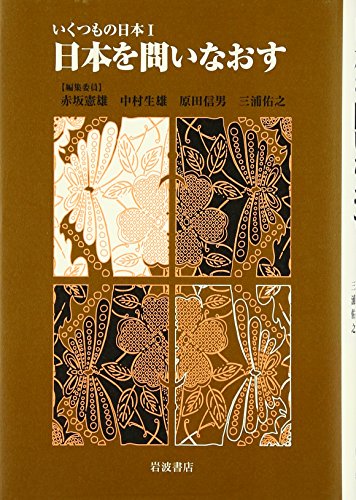書評
『「日本」とは何か』(講談社)
書物の博捜が裏付けた成立と意味
何気なくわれわれは日本という国号を使っているが、そもそもこの「日本」がどのように生まれ、展開してきたのか、ということをよくわかっていないのだ、と著者は指摘する。これまでの理解はどうだろうか。
日本は倭国と称され、称してきたのであったが、中国から律令を継受し、大宝令を制定し国家を整えるなかで、日本という国号を使うようになり、中国に認められた、と考えてきた。
このこと自体には間違いはないが、しかし倭という国号がどう生まれ、日本という国号がどのようにして名付けられたのかということになると、確かに曖昧なままにあった。
古代史学者からは、この点について様々な理解が提出されてきているが、著者は、日本は王朝の名であったという理解に賛意を示しつつも、「日神」の観念に基づいて律令国家の国号として定まったというような神話的な理解には疑問を呈する。
そこで著者がとった方法は、文学研究の方法に基づいてテキストの読みを徹底することにあった。
たとえば『日本書紀』と『古事記』との記述の相違に注目し、前者には日本という国号が頻出するのに、後者には全く出てこないことを問題とする。つまり後者から日本の国号を考えることはできないと見る。
また『日本書紀』が日本の国号を使う時は朝鮮半島の世界に対してであり、中国においては倭国を用いていることを明らかにして、そこに帝国的国家観を認めるとともに、倭から日本への国号の転換が中国に受け入れられたことで、国号日本は確立したと見る。
では何故、中国に認められたのか。
それはもともと中国の世界像に東の果ての地を「日域」「日下」と並んで「日本」とも考えていたからである、と中国の書物を博捜しつつ指摘する。
こうして倭も、日本も、中国の世界像のなかから生まれた呼称であったという。実に興味深い。
これは広く書物を探って「日本」についての言説を探ったことによる大きな成果である。そしてその後の国号日本についての解釈についても、同様な方法が用いられる。
九世紀から十世紀にかけて行われた『日本書紀』の講読について読み解きを綿密に行ない、その時の博士たちは外部から位置づける「日本」には興味を示さずに、「やまと」の和語に関心を示していったとして、自説を裏付けている。
さらに、この国号日本に新たな解釈が付されて登場してきたのが、日の神の国日本という考え方であったという。
これは十一世紀の成尋(じょうじん)の著作から見え始めており、自分たちに内在したものとして神話的に根拠づける解釈として広く中世に広がったもので、この考え方がその後の日本の国号の理解に大きな影響をあたえたと見る。
しかし中世には、さらに仏教的な世界観が入り込んだ「大日/本国」という考え方が入ってくるなどして、紆余曲折を経ながら近世・近代の日本観が形成・展開していったために、ついに「日本」についての国民的な合意を今にいたるまで得てこなかったという。
明解に日本の国号の成立から、その解釈と意味づけの歴史について、多様な書物をとりあげて縦横に駆使しつつ指摘しており、極めて説得的である。
今後の国号論の展開に大きな一石を投じたものとして高く評価されよう。
ALL REVIEWSをフォローする