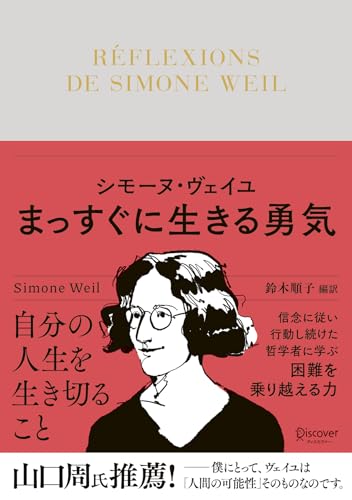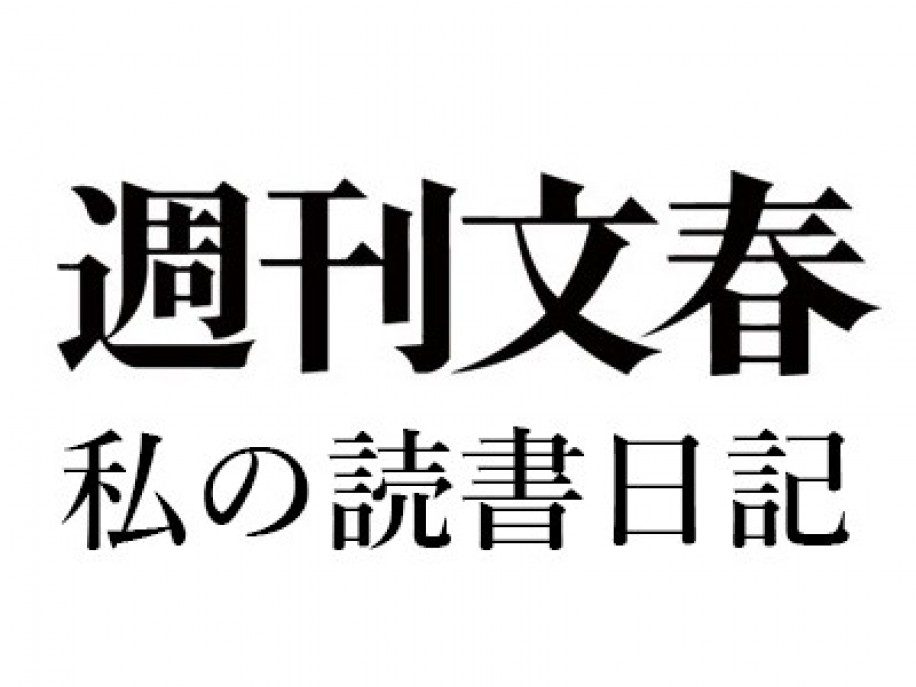書評
『工場日記』(筑摩書房)
言葉だけで成り立つ思考を焼きなました
フライプレス機、絶縁材(カルトン)、固定磁気回路、座金、発条(バネ)、歪(ゆが)み取り、溶鉱炉、焼きなまし、鉄鋲(リヴェット)打ち、帯板の型抜き、可動指片の転向装置(デフレクタ)、圧着端子(ターミナルラグ)、フライス刃。工場で働く者のために用意された作業マニュアルに記されているかのような単語ばかりだが、どれもシモーヌ・ヴェイユの『工場日記』から拾いあげたものである。シモーヌ・ヴェイユといえば、『重力と恩寵(おんちょう)』『根をもつこと』『神を待ちのぞむ』などがいまも読み継がれているユダヤ系フランス人の哲学者だが、一九四三年、三十四歳の若さで亡くなった彼女が二十代半ばに残した言葉は、その思想の根幹にあった労働と人生の問題を、また晩年の宗教との関係を考えるうえで欠かすことができない。
ヴェイユは二十二歳で哲学の大学教授資格を取得し、フランス中部の地方都市ル・ピュイの、女子高等中学で教鞭をとりながら、一九三三年、ロシア革命の幻想を暴く論考「展望 われわれはプロレタリア革命に向かっているのか」を世に問うて、注目を集めた。
デカルトの言によれば、調子の狂った時計は時計の諸法則の例外ではなく、固有の諸法則にしたがう異質の仕組(メカニスム)にすぎない。おなじく、スターリン体制は調子の狂った労働者国家ではなく、この仕組を構成する歯車装置によって規定され、これらの歯車装置の本性にしたがって機能する、まったく異質の社会的仕組とみなすべきだ。
アランの教え子として、ヴェイユは日々、思索と執筆の時間を確保する静の人であると同時に、節を曲げない動の人でもあった。一九三二年、ヒトラーが政権を握った直後の夏、自身の血を恐れることなく、ベルリンとハンブルクを訪れて労働者の実態を見極め、革命がなお可能かどうかを確かめようとしたのもその一例だ。
知識と言葉を持つ者が、そうでない者の上に立つ。生産者と、彼らを搾取する支配者の関係に相似するこの構造を壊すには、働く者が「理論的知識と労働とをつなぐ内的な関係性」を理解するしかない。大量生産が求められる工場の、分業と流れ作業のなかで、自分に与えられている仕事がどこに位置し、どんな意味を持っているのか。知に裏打ちされた労働の積み重ねによって、冒頭に掲げた単語は、もう謎めいた呪文ではなくなり、故障した機械の前で右往左往することも苛立つこともなくなっていくだろう。
頭ではそう言える。しかし現場でこの「内的な関係性」は本当に構築できるのか。ヴェイユは一途である。それを確かめるためには、自身が名もない労働者となって工場で働いてみるしかない。幼い頃から病弱で、体力があるわけでもなく、偏頭痛にも始終悩まされている。過酷な労働など勤まりそうもないのに、身分を隠し、あえて未熟練工として働くことを決意するのだ。かくてヴェイユは、一九三四年、現代技術と労働の関係を探る研究のためという名目で長期休暇を得て、同年十二月から翌年八月までのあいだに、三つの工場で働き、その体験を書き留めた。
最初がパリ十五区にあった鉄道車輛製造のアルストン社、ついでパリ郊外ブーローニュ・ビヤンクールにあった鉄鋼製造のカルノー社、最後は同じ区域の、ルノーの工場。プレスによる金属加工とフライス刃による部品加工に従事し、漫然と流れ作業の一部になるのではなく、与えられた部材の性質や使用する機械の働きを理解しようと彼女は努力を重ねる。
しかしお世辞にも手先が器用とは言いがたく、一時間あたりの最低賃金が保障される作業到達量さえ、なかなかクリアできなかった。失敗するたびに機械の組立工や調整工にののしられ、あまりの仕事量に疲れ果てて、ものを考える時間が奪われていくことに「深い屈辱をおぼえる」ようになる。自身の置かれている立場を早くから「奴隷」になぞらえているのも当然と言えるだろう。現実は過酷で、理想は遠い。
一九四二年五月、ヴェイユは、マルセイユから船でニューヨークに渡る直前、或る神父への手紙のなかで、ポルトガルの小さな村の海辺での神秘的な体験を語っている。守護聖人の祝日、満月の夜に漁師の妻たちの歌う古い聖歌を聴いているとき、工場で受けた「生涯消えることのない奴隷の烙印」を意識しながら、キリスト教が「すぐれて奴隷の宗教」であることを悟ったというのだ。奴隷たちは神を信じずにはいられない。自分もまたそのひとりであると。
ヴェイユはみずから飛び込んだ溶鉱炉で、言葉だけで成り立つ思考を「焼きなまし」た。『工場日記』は決して即物的な記録ではない。働く女性たちや工員たちの言動が、哲学者ではなく作家の眼差しで素描された作品でもある。それはまた、忌まわしい数字と数字のあいだに、自分だけでなく他者の不幸を飲み込んだ生身のヴェイユの、震えるような存在のカルテと言ってもいいのではないだろうか。
ALL REVIEWSをフォローする