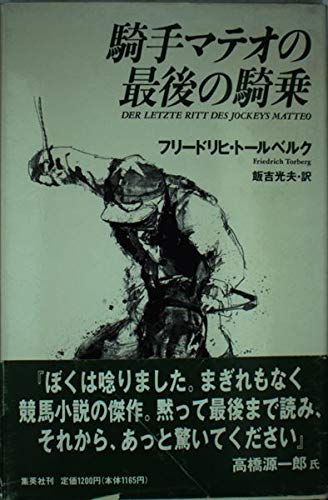書評
『死者たち』(河出書房新社)
ガイストたちが描く時代精神
スイス生まれの現代作家クリスティアン・クラハトが書いたこの小説の、幕開けに設定されているのは一九三〇年代初頭。映画がサイレントからトーキーへと移り変わろうとしていた時代である。政府官僚の甘粕正彦は、映画界の市場開放を要求するアメリカの文化帝国主義に対抗するため、「東京とベルリンを結ぶセルロイドの枢軸」を夢想して、日独合作映画を製作しようと目論(もくろ)む。そのためにドイツから派遣されてきたのが、ホラー映画を撮るというアイデアに惹(ひ)かれていた、スイス人映画監督のエミール・ネーゲリだった。物語は、この二人の生い立ちから出会い、そしてその顚末(てんまつ)を縦糸にして語られる。しかし、物語を追うことだけがこのケレン味たっぷりの小説のおもしろさではない。甘粕はネーゲリの過去の作品を見て、「この映画監督のカメラは漂う霊(ガイスト)のようであった」という感想を持つ。二人の出会いは、孤独で繋(つな)がりを持たない死者たちの出会いで、「人は一人で生まれ、一人で死に、そして一人で転生する」と書かれる。スイスに戻ったネーゲリが日本で撮ったフィルムをもとにした映画には、本書と同じ『死者たち』というタイトルが付けられる。
独特なホラー映画に似たこの小説の登場人物たちは、なんらかの意味でみな「霊(ガイスト)」であり、「死者たち」である。その世界は黄泉(よみ)の国であり、「夢と映画と記憶とが互いに交錯する狭間(はざま)の世界」であって、ネーゲリのような架空の人物と、本書にカメオとして登場するチャップリンやフリッツ・ラングといった歴史上の人物たちとの差はない。日本側の主人公である甘粕も、アナキスト大杉栄を殺害した歴史上の人物としては、一九三〇年にはすでに満州に渡っていて、翌々年の満州国建設に一役買ったが、ここでは歴史的事実から自由になり、キャラクターとして転生を遂げている。
歴史と虚構というミキシングの他にも見逃せないのは、ドイツ映画に対応する日本の能楽である。犬養毅暗殺事件が起こっている最中、甘粕は来日していたチャップリンと能楽堂で、顔を朱に塗った鬼女が出てくる「鉄輪(かなわ)」という能を鑑賞する。この顔を赤く塗った女は、甘粕がかつて東尋坊の洞窟で出会い、それからいわば「霊」としてしばしば視界に現れるようになった、「現実のイマーゴ」なのだ。さらに、能の構成原理として説明される「序」「破」「急」は、三部から成る本書『死者たち』の各部のタイトルにもなっていて、ドイツ語の原書でも、漢字が使われている。つまり言語のレベルでも、ベースになるドイツ語に日本語のミキシングが企てられているわけだ。
最後の「急」の第三部は、一九三二年。ここでわたしたちは、ガイストという言葉には「霊」だけではなく「精神」という意味もあることを思い起こさずにはいられない。死者たちが表象するのは、まさしく「時代精神」(ツァイトガイスト)でもある。カメオの一人、映画批評家のジークフリート・クラカウアーが、当時の社会的心理の反映として映画を分析した名著『カリガリからヒトラーへ』の第四章は、ちょうどこのヒトラー前夜の時期を扱っていた。
「一気に頂点へと向かう」急のすぐ先に待ち受けていたのはナチス政権の成立で、それこそは真のホラーだったのだ。
ALL REVIEWSをフォローする