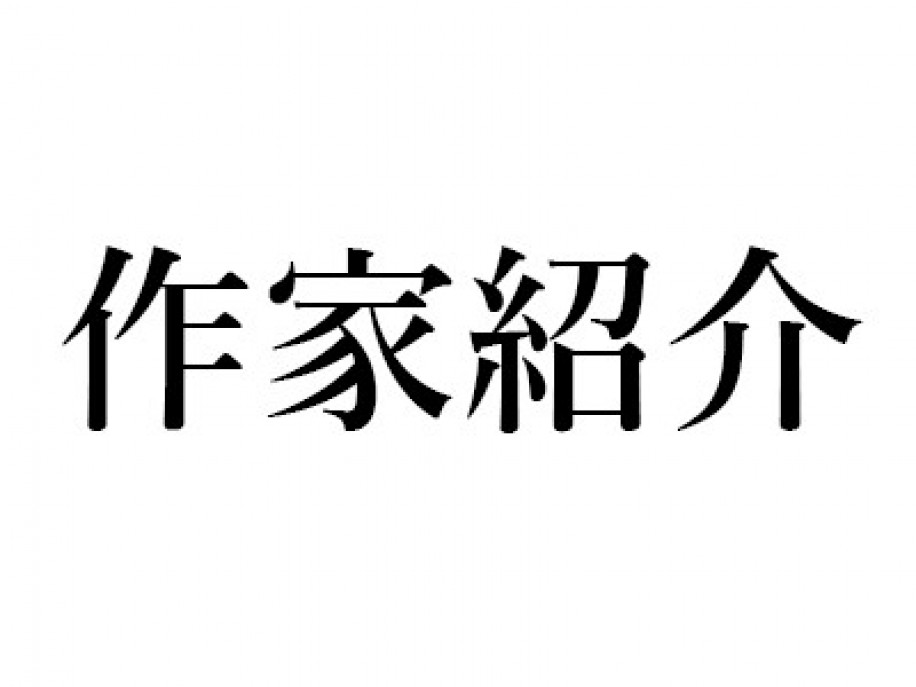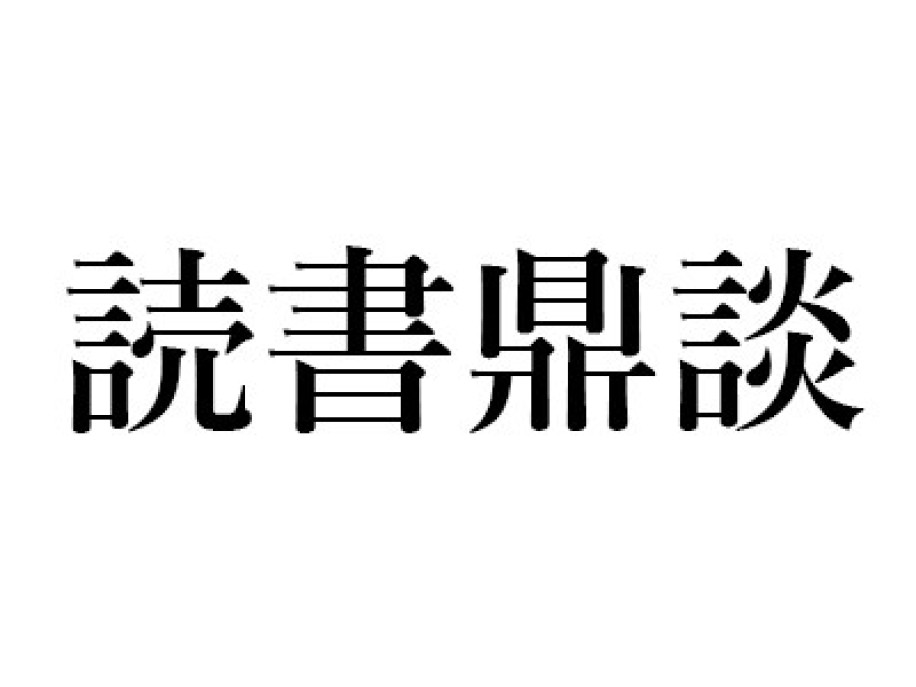書評
『東京のクリームソーダ』(光琳社出版)
探偵はクリームソーダを愛したか?
アイスクリーム・ソーダをはじめて日本にもたらしたのは、不二家の創業者藤井林右衛門だと言われている。洋菓子の視察のために彼が渡米したのは大正元年。帰国後、横浜元町の菓子店に隣接する喫茶室をオープンさせたのが大正三年、すなわち一九一四年のことで、その喫茶室の名は、驚くなかれ「ソーダ・ファウンテン」だったという。クリーム・ソーダはパフェやフルーツポンチとならんで、ハイカラな外国文化そのものだったのである。横浜や銀座の不二家を日本におけるクリームソーダ伝搬の地として、当初は一流の洋菓子店でしか口にできなかったこの飲みものの子孫が、二十世紀も押し詰まった東京の喫茶店や大衆食堂の見本棚で、カレーライスや醤油ラーメンの俗にまみれながらもどこか別次元の神々しさを漂わせているのはそのためなのだが、だからといってこの華々しい過去が、「東京の」クリームソーダに特有の、ちょうど町なかの洋品店に吊されている婦人用「高級ブラウス」に匹敵するいかがわしさを打ち消すまでにはいたらない。片岡義男の写真集『東京のクリームソーダ』は、そんないかがわしさに対するまことに意表を突いた注視の成果だ。現実と非現実を橋渡しする緑色の燈火のような存在。「非現実」だと見切ってはじめて意識の隅にのぼってくる、虚構の最前線にある飲料。クリームソーダがお茶の水の文化アパートに暮らす高等遊民だった明智小五郎の好物だとする著者の想像は、その意味でけっして的外れなものではない。一眼レフという「生首」を手にした者が、「現実を少しだけ非現実のほうに寄せてから受けとめる作業を、さらに二、三歩だけ先へ進め」たときに到達する境地、「いっそのことすべては架空なのだ」と思いなす覚悟をもってとらえられた緻密な映画セットとしての日常。そういう偽りの街にふさわしい人物を挙げるとしたら、昭和初期の名探偵をおいてほかにないからである。
果物屋の店先、すだれ、雨樋、歩道橋、歩行者用信号機、踏切、マネキン、子供用長靴、吊革広告、路地裏、提灯、トタン板の塀、交錯する電線、ビニール傘、ガードレール、飲食店のディスプレイ、クーラーの室外機、ジョッキを掲げる水着姿の女性、そして抜けるような青空とソフトクリームを思わせる雲。晴れた夏の日に、レンズのもとで徹底的に現実の皮膜を剥ぎ取られたこれら虚構世界のなかでも、傑出した存在感を放っているのが、ほかのどこでもない、「東京の」クリームソーダなのである。
三百枚の写真が収められた本書の舞台は、やや東京南西部に偏りすぎているようにも感じられるのだが、問題の飲料の証拠写真は十一枚を占めており、そのうち九枚はプレートが写っているから値段の特定も可能だ。ソーダフロートと名前を変えたものが七百円と高くなっている以外あとは横ばいで、どの店もだいたい五百円前後をめどにしている。気泡のうごめく緑の液体に真っ白なアイスクリームが浮かんでいる奇妙な映像が、平均すると三十頁に一枚の割で挿入されたこの写真集を、一秒間に二十四コマ進む三百コマの短篇映画に見立てれば、わずか十二・五秒で終わる。そのうちの十一コマはほんの一瞬にすぎないけれども、サブリミナル効果をあげるには不足のない数だろう(なにを隠そう、私はこの本を閉じてから、炎暑をものともせず近所の喫茶店ヘクリームソーダを飲みに出かけたのだ)。
しかし片岡義男の読者なら、クリームソーダをあしらった写真集のみならず、小説をも期待するだろう。オリンパスOM-1を手にした「僕」と美しい「彼女」が、首都圏の私鉄沿線にひろがる駅前商店街に繰り出し、写真における現実と非現実について哲学的な会話をかわしながら喫茶店のディスプレイに飾られたクリームソーダの謎を解く。もちろん「僕」は現代の明智小五郎だ。そんな探偵小説をぜひ書いてもらいたい。
【この書評が収録されている書籍】
図書新聞 1998年9月26日
週刊書評紙・図書新聞の創刊は1949年(昭和24年)。一貫して知のトレンドを練り続け、アヴァンギャルド・シーンを完全パック。「硬派書評紙(ゴリゴリ・レビュー)である。」をモットーに、人文社会科学系をはじめ、アート、エンターテインメントやサブカルチャーの情報も満載にお届けしております。2017年6月1日から発行元が武久出版株式会社となりました。
ALL REVIEWSをフォローする