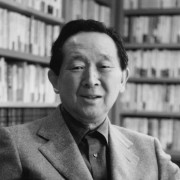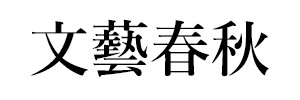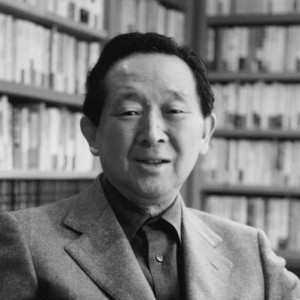書評
『魔の山』(新潮社)
僕は精神の働きが鈍いのではないかと思う。例えば「どんな一言があなたを立直らせたか」とか、「あなたの座右銘は」などと聞かれた時、その都度僕は答えに困るのである。
そんな際、黙って傍らの硯を手元に引き寄せ、色紙にさらさらと「天地有情」とか「色即是空」というような意味深い言葉を書いて見せることができない。
「さあ、それはどうも」
などと言って、あたふたと醜態を晒してしまう。
たしかに僕はいく度か苦況にぶつかっている。その最初は戦争に敗けた時だが、戦況がどんどん悪くなってきた時、毎晩空襲があるようなさなかでいずれは自分も死ぬのだ、それならば潔よくと考えたが、まさか天皇陛下が無条件降伏を命じて戦争が終ると思っていなかったから、急に何もかも馬鹿らしくなってぼんやりしてしまった。
その時は、はじめて自由に読めるようになったマルクス、エンゲルスの『共産党宣言』や『空想より科学への社会主義の発展』などを読んで、この本には本当のことが書いてあると思った。
次は数年間の学生運動に失敗し、革命思想に疑問を持つようになった時だった。結核を患い「幸運に恵まれて生命をとりとめても一人前の仕事は無理」と医師に宣告されたから僕にはどんな未来の展望もないように思われた。森羅万象を解明できると主張するビッグセオリーに深い疑問を持っていたから僕はこれから、自分の感性にとって納得できるものだけを判断の基準にして生きようと考えていた。
その頃、僕が読んだのは日本や英仏の近代詩、現代詩だった。短歌は戦争中自分でも戦争を詠む歌を作っていたから、その反動で伝統短詩型には手が伸びなかった。小説はドストエフスキー、トーマス・マン、カフカという具合だった。なかでも「魔の山」(岩波文庫等)は山の上の療養所にいる主人公ハンス・カストルプの境遇に親近感があって深く影響された。
宗教的なものに心が傾かなかったのは、僕の方の知識が不足していたからでもあるが日本にあった総ての宗教が戦争に協力していたような印象があったからだ。
新しい薬のお蔭で結核が治ってからはマックス・ウェーバーに捕った。『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読んだのがはじまりだったが思弁的な方へ引張られることが多くて、ハイデガーの『存在と時間』やフッサールは読んでも、実用的なものには必要性は感じても心は動かなかった。こうした経過のなかで天邪鬼(あまのじやく)な性格が胸中に拡っていったのだろう。自分にとっての頂門の一針的な著作から僕は離れていった。そうして十四、五年ほど前から自分流に生きることが可能になってみると、まだ一人の人間として、しっかりした中心になる思想が作られていないことに気付く結果になった。そのせいだろうか、今僕はギボンの『ローマ帝国衰亡史』そしてブローデルの『地中海』のような歴史についての長篇を読んでみたいと思っている。
【この書評が収録されている書籍】
そんな際、黙って傍らの硯を手元に引き寄せ、色紙にさらさらと「天地有情」とか「色即是空」というような意味深い言葉を書いて見せることができない。
「さあ、それはどうも」
などと言って、あたふたと醜態を晒してしまう。
たしかに僕はいく度か苦況にぶつかっている。その最初は戦争に敗けた時だが、戦況がどんどん悪くなってきた時、毎晩空襲があるようなさなかでいずれは自分も死ぬのだ、それならば潔よくと考えたが、まさか天皇陛下が無条件降伏を命じて戦争が終ると思っていなかったから、急に何もかも馬鹿らしくなってぼんやりしてしまった。
その時は、はじめて自由に読めるようになったマルクス、エンゲルスの『共産党宣言』や『空想より科学への社会主義の発展』などを読んで、この本には本当のことが書いてあると思った。
次は数年間の学生運動に失敗し、革命思想に疑問を持つようになった時だった。結核を患い「幸運に恵まれて生命をとりとめても一人前の仕事は無理」と医師に宣告されたから僕にはどんな未来の展望もないように思われた。森羅万象を解明できると主張するビッグセオリーに深い疑問を持っていたから僕はこれから、自分の感性にとって納得できるものだけを判断の基準にして生きようと考えていた。
その頃、僕が読んだのは日本や英仏の近代詩、現代詩だった。短歌は戦争中自分でも戦争を詠む歌を作っていたから、その反動で伝統短詩型には手が伸びなかった。小説はドストエフスキー、トーマス・マン、カフカという具合だった。なかでも「魔の山」(岩波文庫等)は山の上の療養所にいる主人公ハンス・カストルプの境遇に親近感があって深く影響された。
宗教的なものに心が傾かなかったのは、僕の方の知識が不足していたからでもあるが日本にあった総ての宗教が戦争に協力していたような印象があったからだ。
新しい薬のお蔭で結核が治ってからはマックス・ウェーバーに捕った。『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読んだのがはじまりだったが思弁的な方へ引張られることが多くて、ハイデガーの『存在と時間』やフッサールは読んでも、実用的なものには必要性は感じても心は動かなかった。こうした経過のなかで天邪鬼(あまのじやく)な性格が胸中に拡っていったのだろう。自分にとっての頂門の一針的な著作から僕は離れていった。そうして十四、五年ほど前から自分流に生きることが可能になってみると、まだ一人の人間として、しっかりした中心になる思想が作られていないことに気付く結果になった。そのせいだろうか、今僕はギボンの『ローマ帝国衰亡史』そしてブローデルの『地中海』のような歴史についての長篇を読んでみたいと思っている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする