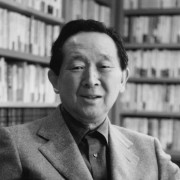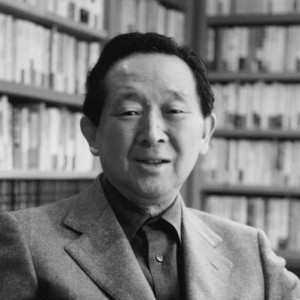書評
『魔の山』(新潮社)
トーマス・マンの『魔の山』を読んだのはいつの頃だったか正確には覚えていない。ただ、この小説の主人公カストルプと同じ胸の病気を患っていた後の恢復(かいふく)期だったから一九五〇年代の後半だろう。私は一九五二年のメーデー事件の報道を思わず病床に起き直って読んだのを覚えている。その頃、まだ絶対安静を強いられていて、ひとりで起き上がることは許されていなかった。この事件は私に自分が世の中の流れから完全に離されているという印象を与えた。「流刑の身」「流竄(るざん)の地」というような言葉が自然に浮かんできた。それから数年後、少し病気が良くなってからマンを読みはじめたのだ。
『トニオ・クレーゲル』『ヴェニスに死す』と辿(たど)ってマン自身が、
と言った作品を手にしたのである。
この小説は人間がどれほど時代に影響され、悩み、迷い、そしてかりそめの愛や無意味な情熱に捉(とら)えられるかを私に教えてくれているように思われた。
作品には善良で世界の進歩を信じているセッテンブリーニや、独裁によって神の国をもたらすことが出来ると主張するナフタ、そして本能に自らを委せて生きようとして自殺してしまうベーベルフルンなどが登場する。人種的にもイタリア人、ユダヤ人、オランダ人そして美しいロシア婦人ショーシャといった具合に、設定されたスイスの山頂に近い療養所という舞台の性格にふさわしい国際的性格を現して、世界大戦直前から戦争までのヨーロッパ人の問題意識と、それぞれの人物の形象化に成功しているのだ。
私がこの作品から受けた印象は、それまで読んだ小説の感銘の質、心理描写の巧みさや自然描写の美しさからの感動とは異質なものであった。ここには、ヨーロッパ社会の動きを全体としてひとりひとりの人間の生き方の問題として捉えている眼があり、同時代に対する作家精神の責任の意識が感じられた。その背景には、ヨーロッパ的知と東方の知恵、民主主義と独裁、宗教と科学、ロマン主義的感性と合理主義、現実主義の対立があり、それらが論じられ、かつ行動によって表現されていた。
もし、人間に対する感性的な認識がおろそかにされないのなら、小説という芸術の形式が世界を相手にしてこのような虚構を描き得るのだという発見は私の心を震撼(しんかん)しつづけた。
体力が恢復してくるにつれて、私はこれからどう生きていったらいいのかという問題にぶつかっていた。マンも、「自作について」で語っているように、私が入りこんでいた療養の世界は、
だったのである。
『魔の山』は現実の社会に戻ることを恐れていた私を励まし、前へと押し出すようであった。読み終わった私の胸中には、
という作品の中の最後の言葉がいつまでも鳴り響いていた。
【この書評が収録されている書籍】
『トニオ・クレーゲル』『ヴェニスに死す』と辿(たど)ってマン自身が、
後世の人々は、いつかおそらく『魔の山』の中に、二十世紀も三十年頃までのヨーロッパ人の魂の状態の、そして精神的問題点の記録を見るだろう。
と言った作品を手にしたのである。
この小説は人間がどれほど時代に影響され、悩み、迷い、そしてかりそめの愛や無意味な情熱に捉(とら)えられるかを私に教えてくれているように思われた。
作品には善良で世界の進歩を信じているセッテンブリーニや、独裁によって神の国をもたらすことが出来ると主張するナフタ、そして本能に自らを委せて生きようとして自殺してしまうベーベルフルンなどが登場する。人種的にもイタリア人、ユダヤ人、オランダ人そして美しいロシア婦人ショーシャといった具合に、設定されたスイスの山頂に近い療養所という舞台の性格にふさわしい国際的性格を現して、世界大戦直前から戦争までのヨーロッパ人の問題意識と、それぞれの人物の形象化に成功しているのだ。
私がこの作品から受けた印象は、それまで読んだ小説の感銘の質、心理描写の巧みさや自然描写の美しさからの感動とは異質なものであった。ここには、ヨーロッパ社会の動きを全体としてひとりひとりの人間の生き方の問題として捉えている眼があり、同時代に対する作家精神の責任の意識が感じられた。その背景には、ヨーロッパ的知と東方の知恵、民主主義と独裁、宗教と科学、ロマン主義的感性と合理主義、現実主義の対立があり、それらが論じられ、かつ行動によって表現されていた。
もし、人間に対する感性的な認識がおろそかにされないのなら、小説という芸術の形式が世界を相手にしてこのような虚構を描き得るのだという発見は私の心を震撼(しんかん)しつづけた。
体力が恢復してくるにつれて、私はこれからどう生きていったらいいのかという問題にぶつかっていた。マンも、「自作について」で語っているように、私が入りこんでいた療養の世界は、
閉鎖と、人を包み込んでしまう力の世界
だったのである。
『魔の山』は現実の社会に戻ることを恐れていた私を励まし、前へと押し出すようであった。読み終わった私の胸中には、
この世界を覆う死の饗宴の中から、雨の夜空を焦がしているあの恐ろしい熱病のような業火の中から、そういうものの中からも、いつかは愛が生れ出てくるであろうか。
という作品の中の最後の言葉がいつまでも鳴り響いていた。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする