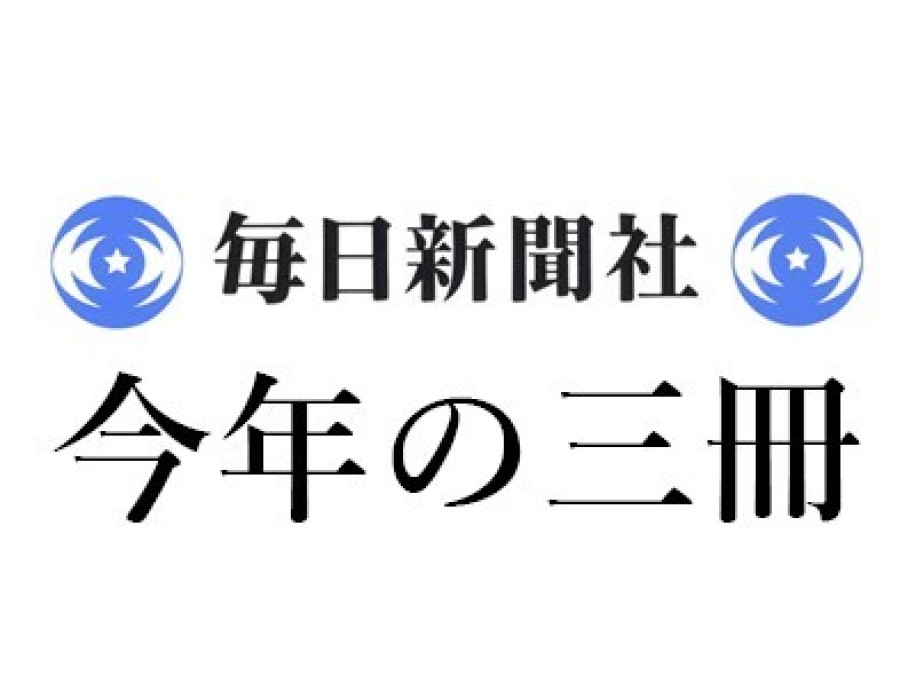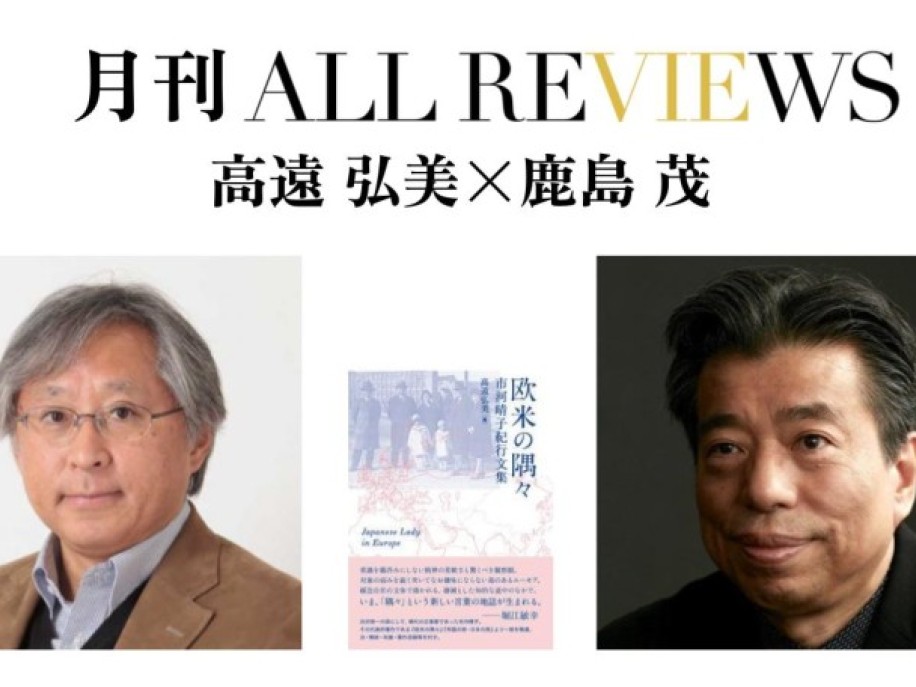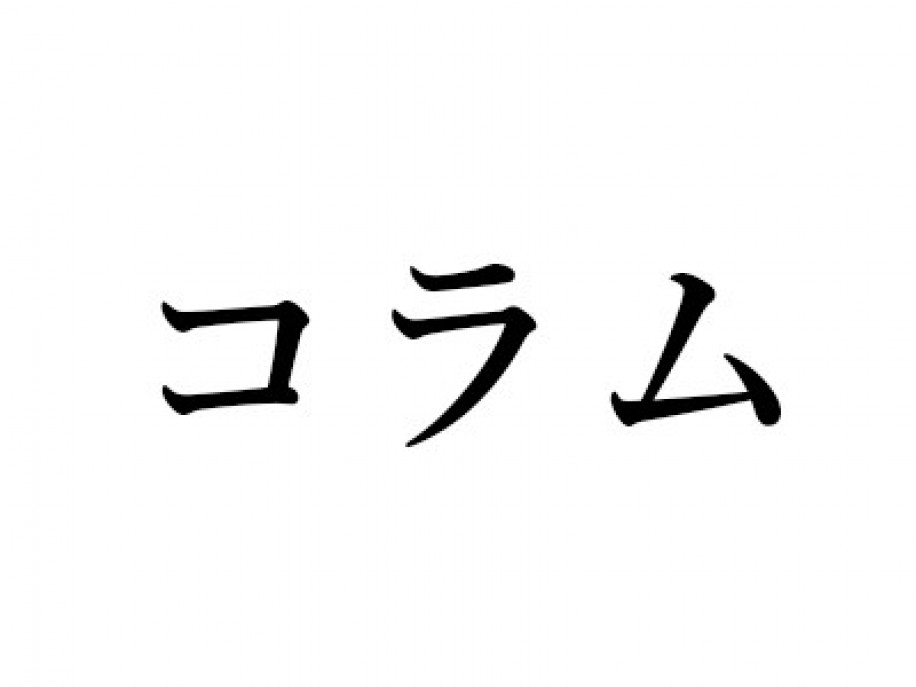解説
『ビデの文化史』(作品社)
文学博士A先生はお若いころ、留学生として渡仏した際、ホテルで初めてビデをみて、何だか判らぬままに小便器と勘違いして用を足された。
「てっきり小便用だと思ったんだ。でも、用を足したあと、すぐに流れて行かなくてね。往生したよ」
フランスのホテルではトイレ・バスが共同の場合でも各室にビデがあるのがふつうだから、A先生の勘違いは決して笑うことはできない。私がA先生だったら同じようにしたかもしれない。
またB先生は一日パリを歩いて疲れ切った足を毎夜そこで洗った。
「あれは足を洗うものじゃないのか。大きさだってちょうどいいし、姿勢も楽だしね」
その他、靴下や小物を洗ったとか、風呂上がりにそこで口をすすいだとか、スーパーで買ってきた西瓜やビールを冷やした(フランスのホテルの部屋に冷蔵庫が置いてあるのはきわめて稀だ)とか驚くべき話はいくらでもある。
その逆に、本書の訳者、加藤雅郁さんと私の共通の友人Cのように、新婚旅行でフランスにゆき、トイレも風呂もないのにビデだけ置いてあるのを不審に思った若妻に、ことこまかに使用法を説明して、ついには純情可憐なる妻を泣かせてしまったという例もある。ただし、この場合、Cが正確な知識を披露したというより、針小棒大にあることないことをまくしたてた結果、新妻を泣かせるに至ったのではないかと私は踏んでいるのだが。
ところで、これは私だけの経験ではないと思うけれど、フランス人は概して食事中の猥談を好む。無粋な私にしても何遍彼ら(男女を問わず、また年齢もさほど関係ない)から食事の最中、卑猥な話を聞いて、料理をこぼしそうになったかわからない。それなのにビデについて聞いた記憶がとんとない。
いや、単に会話だけではない。必要があればエロティックな記述も辞さない浩瀚な百科事典『十九世紀ラルース』で「bidet」を引いても、「洗い桶が入った便器。跨がって使用」くらいしか書かれていないし、たとえばポルノグラフィの傑作『O嬢の物語』のような作品ですら、あれだけセックスが描かれているのに、性交に欠かせないビデは蔑ろにされているようにみえるのだ。あるいは語彙が豊富で、しばしばエロティックなイメージに事欠かないプルースト『失われた時を求めて』のごとき小説でも、十九世紀末から二十世紀初頭を舞台にしているにもかかわらず、ビデに関する言及は一切見られない。
フランスにおいて、エロティックなイメージ(寝室)と尾籠なる排泄行為(トイレ)、それに衛生思想(風呂)というトライアングルの中心にあるがごときビデは、まさにその中間性において人びとの意識からすとんと抜け落ちている。人びとは無意識のうちにそれに跨がり、無意識のうちに忘れてしまうのではないか。朝になると自然に手にしているのに、ふだんはその存在を忘れている歯ブラシか櫛のように。
さらに言えば、ビデがフランス人にとって、あまりに日常的で、ごくふつうのものとして家庭の一室に置かれていることからして、否が応でも両親の性行為ないし母親の局部の洗浄を暗示してしまうがゆえに、どこか瀆聖的であり、あからさまな言及を避けるべきものとして意識下に閉じこめられているからということもあるだろう。
本書に出会うまで私は漠然とそう考えていた。
しかし、本書を読んでこうした考えだけでは片づかないことがよくわかった。スタッフ男爵夫人や小説家コレットはたしかに遠慮がちにしか書いていないが、十八世紀の『百科全書』、アントワーヌ・ブレの「ビデ」小説、サド侯爵『美徳の不幸』、「マリー・アントワネットのコンシエルジュリーにおける使用品目録」、ゴンクール兄弟『日記』をはじめとするあまたの文献ではビデが堂々と名指しされているのだ。
本書の美点はただそうした文献を紹介していることにとどまらない。社会構造、生活環境、個人の価値観まできちんと押さえたうえでの記述は文化史として必要不可欠である。水事情、建築、衛生学、トイレ、風呂、疾病予防、生理学、医学思想、教育、道徳意識、健康法、結婚生活、官能性、ポルノグラフィ、娼館、階級意識、産業構造、百貨店、職人技、デザイン、美術品と、ビデをとりまくさまざまな要素を細大漏らさず述べているのはまこと推賞に値する。
読者はビデという、今まで知っていたつもりで実はおぼろげにしか理解していなかった器具の歴史とその背景を知って、人間の歴史、否、人間存在の不思議さに心打たれることだろう。日本の文化は余白を大切にするのに対して西洋では、といった類いの、紋切り型の比較文化論ではなく、あくまで具体的な事物を通じて、人間の文化のありようを考えることこそ、いまの時代には必要であろう。
ひとことで言うなら、本書はビデを通じての文化論から出発した人間論の試みにほかならない。と言って、読者諸兄におかれては、何も肩肘張って頁を繰る必要はさらさらない。ロミやジャン・フェクサスの本がそうであったように、まずは愉しみつつ、ビデをめぐる、愚かしくもいとおしい人間の歴史におつき合い頂ければ幸いである。
道案内を務める加藤雅郁さんは、すでに語学書を何冊も公にしているかたわら、翻訳でも美術論その他で刮目すべき仕事をしている気鋭の仏文学者である。本書を契機にした加藤さんの今後の一層の活躍を大いに期待したいと思う。
二〇〇七年七月
「てっきり小便用だと思ったんだ。でも、用を足したあと、すぐに流れて行かなくてね。往生したよ」
フランスのホテルではトイレ・バスが共同の場合でも各室にビデがあるのがふつうだから、A先生の勘違いは決して笑うことはできない。私がA先生だったら同じようにしたかもしれない。
またB先生は一日パリを歩いて疲れ切った足を毎夜そこで洗った。
「あれは足を洗うものじゃないのか。大きさだってちょうどいいし、姿勢も楽だしね」
その他、靴下や小物を洗ったとか、風呂上がりにそこで口をすすいだとか、スーパーで買ってきた西瓜やビールを冷やした(フランスのホテルの部屋に冷蔵庫が置いてあるのはきわめて稀だ)とか驚くべき話はいくらでもある。
その逆に、本書の訳者、加藤雅郁さんと私の共通の友人Cのように、新婚旅行でフランスにゆき、トイレも風呂もないのにビデだけ置いてあるのを不審に思った若妻に、ことこまかに使用法を説明して、ついには純情可憐なる妻を泣かせてしまったという例もある。ただし、この場合、Cが正確な知識を披露したというより、針小棒大にあることないことをまくしたてた結果、新妻を泣かせるに至ったのではないかと私は踏んでいるのだが。
ところで、これは私だけの経験ではないと思うけれど、フランス人は概して食事中の猥談を好む。無粋な私にしても何遍彼ら(男女を問わず、また年齢もさほど関係ない)から食事の最中、卑猥な話を聞いて、料理をこぼしそうになったかわからない。それなのにビデについて聞いた記憶がとんとない。
いや、単に会話だけではない。必要があればエロティックな記述も辞さない浩瀚な百科事典『十九世紀ラルース』で「bidet」を引いても、「洗い桶が入った便器。跨がって使用」くらいしか書かれていないし、たとえばポルノグラフィの傑作『O嬢の物語』のような作品ですら、あれだけセックスが描かれているのに、性交に欠かせないビデは蔑ろにされているようにみえるのだ。あるいは語彙が豊富で、しばしばエロティックなイメージに事欠かないプルースト『失われた時を求めて』のごとき小説でも、十九世紀末から二十世紀初頭を舞台にしているにもかかわらず、ビデに関する言及は一切見られない。
フランスにおいて、エロティックなイメージ(寝室)と尾籠なる排泄行為(トイレ)、それに衛生思想(風呂)というトライアングルの中心にあるがごときビデは、まさにその中間性において人びとの意識からすとんと抜け落ちている。人びとは無意識のうちにそれに跨がり、無意識のうちに忘れてしまうのではないか。朝になると自然に手にしているのに、ふだんはその存在を忘れている歯ブラシか櫛のように。
さらに言えば、ビデがフランス人にとって、あまりに日常的で、ごくふつうのものとして家庭の一室に置かれていることからして、否が応でも両親の性行為ないし母親の局部の洗浄を暗示してしまうがゆえに、どこか瀆聖的であり、あからさまな言及を避けるべきものとして意識下に閉じこめられているからということもあるだろう。
本書に出会うまで私は漠然とそう考えていた。
しかし、本書を読んでこうした考えだけでは片づかないことがよくわかった。スタッフ男爵夫人や小説家コレットはたしかに遠慮がちにしか書いていないが、十八世紀の『百科全書』、アントワーヌ・ブレの「ビデ」小説、サド侯爵『美徳の不幸』、「マリー・アントワネットのコンシエルジュリーにおける使用品目録」、ゴンクール兄弟『日記』をはじめとするあまたの文献ではビデが堂々と名指しされているのだ。
本書の美点はただそうした文献を紹介していることにとどまらない。社会構造、生活環境、個人の価値観まできちんと押さえたうえでの記述は文化史として必要不可欠である。水事情、建築、衛生学、トイレ、風呂、疾病予防、生理学、医学思想、教育、道徳意識、健康法、結婚生活、官能性、ポルノグラフィ、娼館、階級意識、産業構造、百貨店、職人技、デザイン、美術品と、ビデをとりまくさまざまな要素を細大漏らさず述べているのはまこと推賞に値する。
読者はビデという、今まで知っていたつもりで実はおぼろげにしか理解していなかった器具の歴史とその背景を知って、人間の歴史、否、人間存在の不思議さに心打たれることだろう。日本の文化は余白を大切にするのに対して西洋では、といった類いの、紋切り型の比較文化論ではなく、あくまで具体的な事物を通じて、人間の文化のありようを考えることこそ、いまの時代には必要であろう。
ひとことで言うなら、本書はビデを通じての文化論から出発した人間論の試みにほかならない。と言って、読者諸兄におかれては、何も肩肘張って頁を繰る必要はさらさらない。ロミやジャン・フェクサスの本がそうであったように、まずは愉しみつつ、ビデをめぐる、愚かしくもいとおしい人間の歴史におつき合い頂ければ幸いである。
道案内を務める加藤雅郁さんは、すでに語学書を何冊も公にしているかたわら、翻訳でも美術論その他で刮目すべき仕事をしている気鋭の仏文学者である。本書を契機にした加藤さんの今後の一層の活躍を大いに期待したいと思う。
二〇〇七年七月
ALL REVIEWSをフォローする