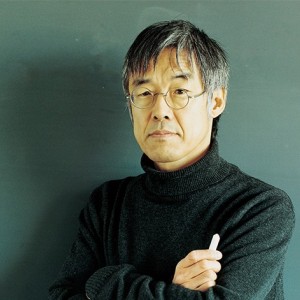書評
『とびきりお茶目なイギリス文学史―アメリカのおまけつき』(筑摩書房)
文学史の正しい書き方
これはもう完全に職業的反応なんだけど、本を読んでいて、「やられたあ!」と思うことがあるんだな。自分の頭の中で何年もかけて考えていたオリジナルのアイデアがある。そのアイデアが本になった時のことを考えてワクワクしていたら、とつぜん、そのアイデアを使って先に書かれたものにぶつかってごらん。もー、目の前マックラになるから。
以前、スティーヴン・キングの『ガンスリンガー』を読んだ時も、「ガーン!やられたあ」と思ったけど、よく読んでみたらキングのアイデアの使い方はぼくが考えていたのとはまるで違っていたのでホッとしたのだった。でも、これ以上詳しいことは書けないよ。大事な秘密だから。
そういうわけで、『とびきりお茶目なイギリス文学史』(テランス・ディックス著、尾崎寔訳、筑摩書房)を読みはじめたら、ひさしぶりに、「やられたあ!」と思ったよ。
著者は元BBCのプロデューサーで、活字離れが進む若者を文学に引き戻す(?)ために、イギリスが誇る偉大な作家たちやその作品をかわゆいイラストとお茶目な文章で紹介している。
たとえば、
(高橋注・コールリッジの)「クリスタルベル」もまた、けったいな中世風の歌謡だ。……。クリスタルベルは彼女を城に連れて戻り、かくまってやる。二人がベッドに入ろうと着ているものを脱いだ時、クリスタルベルはジェラルディーンの身体にただならぬものを見てしまう。
「見よ、女の胸と横腹の半分を――
それは夢に見ても、口にできるものではない」
一体全体、ジェラルディーンの何がどうなっていたのかは、ついに知らされないまま(もしかしたら、胸に入れたシリコンが爆発してたりなんかして!)。……。この詩は未完のままだから、何が何やら結局分かりっこないんだ。
てな調子で、近づきにくい古典の花園にどかどかと土足で入りこんでいる。ほんとの古典はむちゃくちゃやさしく説明してもその価値がさがんないもんだ。だから、テランス・ディックスのやり方はすごくチャーミングだと思うね。ぼくは、このやり方で日本近代文学史をやれないかとかねがね思ってたので、「やられたあ!」と唸ったのさ。装幀も翻訳もよくできたこの本の唯一の欠点は「この本自身は面白いが、この本を読んでも、この本に出てくる作家や作品を猛烈に読みたくなるとは思えない」というところだろう。
やはり、文学史は「本を読みたくなる文学史」じゃなきゃダメだよ。
ぼくは著者のテランス・ディックスさんに関川夏央・谷ロジローのノーベル賞級の傑作、いまなお続く『「坊っちゃん」の時代』(双葉社)を読んでもらいたいと思った。なにしろ、ぼくはこの本を読んで漱石や鴎外を真面目に読み返すようになったんだから。
関川・谷口の本に出てくる作家たちはあまりに魅力的なので、どうしてもその作家の書いたものを読んでみたくなる。文学史にはこの要素がどうしてもなくっちゃいけない。オーソドックスな日本文学史で例をあげるなら、ついに復刻が開始された伊藤整の『日本文壇史』(講談社文芸文庫)がその代表だろう。この『日本文壇史』は要するに最高に面白い小説であり、作家たちはその小説を動き回る登場人物たちなんだ。そういう登場人物たちの書いたものなら読みたくなるっていうのが人情じゃないのお?
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする