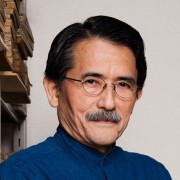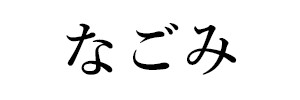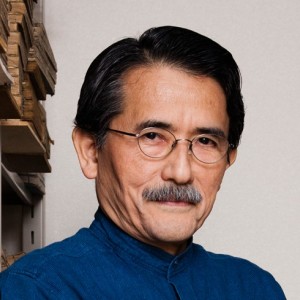書評
『花祭りのむら』(福音館書店)
祭を知ること、心を知ること
もう四半世紀以上も昔のことになる。私は、当時まだ大学院生で、文献の勉強をしていたが、文学の研究というものは、ブッキッシュな方法だけでは限界があるという気がした。それで、文献にあらわれない「古代からの伝承」に拠って日本を考える学問、すなわち折口信夫の民俗学を少々齧ったことがある。
民俗学は、ひたすら「実感の学問」である。書物の上に固定された「記録」なぞをいくら読んでも分ることは高が知れてある。しかし、ひとたび実際の民俗行事やら祭礼やらをおのれの目で見、おのれの肌で感じると、そこに、あっと驚くほど豊かなインスピレーションが湧き起るのを感じるのだ。
それで、民俗採訪の旅もあちこちと行ったが、なかでも印象深かったのは、三駿遠の国境あたり、山深い新野(にいの)の村の雪祭りであった。そこには、ほんとうに神が居なさるという気がしたし、祭というものが、古くは性の解放であるというのも、なにがなし頷けるところがあった。それが具体的にどういうのかということは、ここに簡単に書けるようなことではない。
さて、雪祭りと並んで、奥三河あたりに遍在する祭に「花祭り」というのがあるのだが、これは残念ながら見たことが無い。無いけれど、是非とも見て見たいものだとは思ってきた。が、民俗学関係の書物をいくら読んでも「事柄」が知れるだけで、「実感」はわかなかった。
しかし、ここに一つの面白い本が出て、この「花祭り」について、実感豊かに物語ってくれたので、私は大いに目の鱗を落したことである。
著者の須藤さんは、かつて『写真で見る 日本生活図引』という面白い上にも面白い、庶民の生活の記録図譜をものされた写真家であり民俗学者でもある人だが、その「時代の語り部」のような須藤さんが、こんどは、「月」という集落と「御園」という集落の花祭りを、念入りに記録して、子供にも分る易しい文章で書いてくれた。とりわけ、御園のそれは、いよいよ過疎の進行によって子供の舞手が居なくなってしまった現代に、東京から、稔君という少年が彗星のごとくにやって来て、次第に御園の村に溶け込み、やがて御園小学校廃校直前の一年間をこの村に暮らし、立派に舞の継承者になっていくまでの物語を、春風のように優しい口調で物語る。私は、読みながら、ついつい引き込まれて、あるところでは落涙しそうにさえなった。そうして、祭というものの深い深い意義について、いつの間にか考えさせられていた。
声高にイデオロギーを叫ぶのでもなく、いたずらに学匠沙汰に堕するのでもなく、といって、ジャーナリズム的に軽薄なのでもなく、じんわりじんわりと心にしみ込んでくる本だ。広く見れば、茶の心だって、こういう日本古来の祭の心と必ずどこかで繋がっているにちがいない。日本の祭を知ることは、日本の心を知ることでもある。私は、この本を是非大人子供両方に読ませたいと思った。
ALL REVIEWSをフォローする