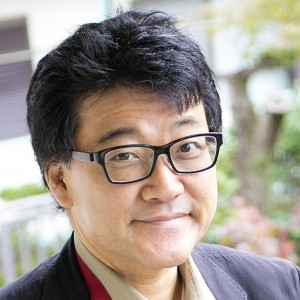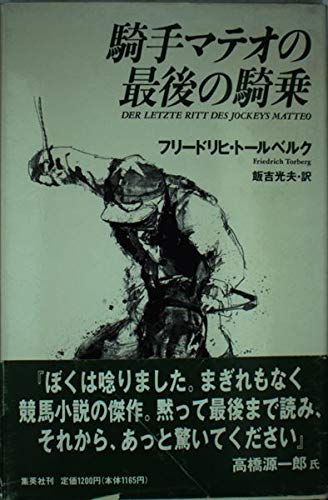書評
『ゴーレム』(白水社)
グスタフ・マイリンク(Gustav Meyrink 1868-1932)
ウィーン生まれの作家。銀行業に従事したのち創作をはじめ、おもにプラハで活動した。ホフマンやポオの伝統につらなる幻想小説の書き手として知られ、とりわけ『ゴーレム』(1915)の出版はセンセーショナルな事件だったと言われる。そのほかの著作に『緑の顔』(1916)、『西の窓の天使』(1920)などがある。また後年、ホルヘ・ルイス・ボルヘス選の短篇集『ナペルス枢機卿』には、三作が収録されている。introduction
『ゴーレム』の舞台はプラハのユダヤ街、いわゆるゲットーである。この地区は一八九五年から「衛生化」がはじまり、建物の近代的改築が進められたという。しかし、マイリンクが描いているたたずまいは、原風景としての旧市街だろう。マイリンクとおなじ時期、プラハのゲットーに生きた作家がカフカだ。彼はこんなふうに書き残している。「ぼくたちの内部にはまだ薄暗い片隅が息づいている。秘密めいた路地、曇った窓ガラス、薄暗い中庭、騒がしい居酒屋、無愛想な食堂が。ぼくたちは改装された街の広い大通りを行く。けれどもぼくたちの歩みと眼差しは不確かだ。心の中ではぼくたちはまだ震えている。悲惨な旧い路地にいるように」。カフカとマイリンクではまったく作品の趣向は異なるが、目に見えていることよりもリアルな世界をさぐっていた点は共通する。▼ ▼ ▼
古い小説を読んでいて、そこで小道具になっている書物が呪物性を備えていることに気づき、はっとすることがある。現在の大量印刷の出版物とはちがった意味を、かつての書物は持っていたのだろう。なにも中世の写本までさかのぼらなくとも、前世紀までの書物は、その内容を引きたたせるためオリジナルの活字が考案されたり、章の最初にくる語の頭文字には大きく緻密なデザインを施すなど、凝ったものが少なくなかった。はなはだしい例では、頭文字だけで一ページを占めるものさえあるという。表現のメディアである以上に、ひとつの工芸品としての書物。精巧に装飾され、丁寧に造本された本には、そこに印刷されたいる内容とは別の、なにか神秘的な意味が隠されているかもしれない。
『ゴーレム』の語り手、美術細工師アタナージウス・ペルナートのもとに届けられた『霊魂の受胎』も、そんな書物だった。本文の金属製の表紙には薔薇模様と印章が彫られ、本文各章の最初のページには、二枚の金の薄板で造られた頭文字がはめこまれている。その頭文字のひとつが損傷しており、それを補修してほしいという依頼のようだ。この本を持参したのは不審な男で、ひとことも口をきかずにそのページを開いたまま、ペルナートに本をさしだす。ペルナートは読むとはなしにページを繰りはじめるのだが、本は「夢のように、ただ夢よりも鮮明に」彼に語りかけてくる。そして彼の脳裏には、ヘルマフロディート、つまりギリシア神話の両性具有の巨人が王座についている姿が浮かびはじめる。
ぼくに話かけてくるのはもはや本ではなく、ひとつの声だった。その声は、いくらあくせくしてもぼくにはわからないなにかを、ぼくから聞き出そうとし、わけのわからぬ、しかし切迫した問いかけでぼくを苦しめた。(略)
その声がぼくに語ったすべてのことを、ぼくは生まれてこのかたずっとぼくの内部に持っていた。それがなにかに蔽われてしまって、そのために忘れられていたにすぎない、そのためそれはきょうまでぼくの想念から姿を隠したにすぎないのだ、とぼくは思った。
これに端を発して、物語はまさに「生まれてこのかたずっと内部に持っているのに、忘れられているなにか」の探求にむけて進んでいく。しかし、その探求の過程で、主人公は、そしてぼくたち読者も、いくつもの“扉”をくぐりぬけなければならない。なにしろこの語り手からして、自分がほんとうに細工師ペルナートなのかどうか判然としないのだ。
頭文字が損傷した『霊魂の受胎』が届けられる前、彼は夢うつつのなかでアタナージウス・ペルナートという名前を思いだしていた。それは遠いむかしに、どこかでまちがえられた帽子の裏地に書かれていた名前ではないか。彼の頭はとても独特なかたちをしているのに、取りかえられた帽子もぴったりと合った。
そして、ペルナートとしてプラハのユダヤ人街に目覚めた彼は、『霊魂の受胎』の件をはじめとして、この界隈で起こっている奇妙な出来事に気づいていく。ただし、わかるのは断片にすぎず、しかもその断片がどう関連しているのか、あるいは関連のないいくつもの出来事なのか、はっきりとしない。ユダヤ人街に暗躍する悪人ドクター・ヴァッソリと、その父である古道具屋ヴァッサートゥルムを倒そうと企てる苦学生カルーゼクの計略。酒場でささやかれている、魔物ゴーレム出現の噂。そして同じアパートの住人が漏らした、ペルナートがかつて精神病院に入院していたという事実(たしかに彼は過去の記憶を持っていない)。
やがて、ひとりの女性がペルナートのもとに助けを求めてくるにおよんで、ユダヤ人街をおおう暗雲の中心へと、彼もいやおうなく巻きこまれていく。彼女は結婚して子どももいるのだが、不倫の恋に身を焦がしている。その相手というのが、ドクター・ヴァッソリの悪事を暴いたカルーゼクの朋友ドクター・サヴィオリだという。そしてそのサヴィオリは、ペルナートの隣の部屋に住んでいたのだった。すでにヴァッソリはカルーザクによって滅ぼされていたが、今後は逆にサヴィオリがヴァッサートゥルムの手で生命の危機に瀕している。ペルナートはカルーザクに協力し、ヴァッサートゥルムを追いつめる決心をする。
ここまできても、物語はいまなお一本の糸にまとまりきらない。眠れぬ夜、ペルナートはアパートから地下へと抜ける秘密の通路を見つけ、ユダヤ人街のしたに広がる迷宮を経めぐったあげく、古い塔へと迷いこむ。そこで彼は、床に落ちたタロットカードから自分の分身が出現するという怪異に遭遇する。朝が来て、記憶がはっきりとしないまま街路へ抜けでるが、その彼の姿を見た通行人は、ゴーレムがあらわれたと恐れおののくのだった。
現実と幻想の境界は消えさり、いくつものエピソードばかりが、相互の関連があいまいのままに積みかさねられていく。そして、こうした物語の錯綜と二重うつしに、複雑な構造を持つプラハの街並が描きだされる。濃霧の立ちこめる路地、陰欝な石造りの家、窓だけで戸のない部屋、そして地下に広がる迷宮。
街だけではない。古い書物、床に落ちたタロットカード、ひそかにささやかれるゴーレムの伝説。それらは、ペルナートが希求する真相へとつづく“扉”であると同時に、容易なことでは開かない、ゆくてをさえぎる“扉”でもあるのだ。本に描かれたヘルマフロディートのイメージ、カードに示されたアレフ(最初の文字)の図案、ゴーレムが担うドッペルゲンガーの物語、そこにペルナートが見た不思議な夢、霊媒の語る予言などまでが重ねあわされる。まさしく「異種な諸概念のアマルガム」(W・ヴェルツィヒ)と言うにふさわしい、入り組んだ世界像である。それらを解釈しながら、またそれらに幻惑されつつ、ぼくたち読者もまた迷路をめぐるように、主人公の彷徨を追っていく。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする