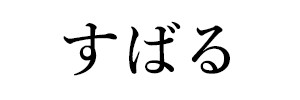書評
『めぐり糸』(集英社)
クピドの矢が約すもの
分身のように、あるいは自分自身であるかのように別れがたい宿命のカップルというのがいる。ふたりだけの調和世界を見つけた彼らは浮世の価値観やしがらみから離れ、必然的に死に近づいていく。クピド(エロス)の矢は人の心臓を射抜き、愛は死を約束する。『めぐり糸』のヒロインもそうした片割れに出会ってしまう。
ヒロインは九段で、祖母が始めた料亭の元売れっ子芸妓の女将を母として育つ。運命の「哲治」が町に現れるが、いつどこから来たのか誰も知らない。ある日、教室で不意に彼の存在を意識してから、彼のことばかり考え、「そのうちわたし自身が哲治になってしまいそう」になる。これはソウルメイトの典型的な症状と言える。しかし哲治の言葉が初めて記されるのは七十四ページもしてからで、それまで会話文は殆んどなく、地の文での濃密な語りが続くのだ。ロベルト・ボラーニョもびっくり。しかしここまで粘り強い叙述があるからこそ、「一度波にさらわれたら」「一生海のなかで生きることになるんだよ」という哲治の最初の台詞が読み手の目に鮮烈に刻まれる。
出自の知れない哲治は「一冊まるまる落丁した教科書のようだった」というが――ちなみにここは『秘密の花園』『嵐が丘』『レベッカ』等を本歌取りしたケイト・モートンの『忘れられた花園』を彷彿とさせる――ヒロインもある事情から自分も同じだと感じ、ますます哲治との一体感を深める。ところが、彼女は年頃になるとある裕福な青年に惹かれ、結婚してしまうのである。
この作品は、ずばり『嵐が丘』をモチーフとしているのではないか。出自のわからない孤児の男子、彼の片割れのようにして育つヒロイン(「わたしの分身」だと言う)、別の裕福な男性との結婚……。これは作者の遊び心か、偶然の一致か、『めぐり糸』の18節は「徹雄さんと雪子と共にした十数年の歳月は、これまでの人生でもっとも心安らかに日々を過ごした……」と始まり、『嵐が丘』の第十八章は「その後の十二年間はあたしの人生のなかで最も幸せな時期でした」と始まる。どちらも宿命の愛が吹き荒れる狭間の平和なひとときが描かれるが、運命の人は戻ってくるのだ。そして、決め台詞。「哲治は……わたしなのよ」/「わたしはヒースクリフなのよ!」
上野、向島、横浜、鳥取、下関、そしてまた上野に戻るという、終わりなき旅路……。本書のラストは愛の成就か破滅か? いや、そのふたつは同じものなのだ。
ALL REVIEWSをフォローする