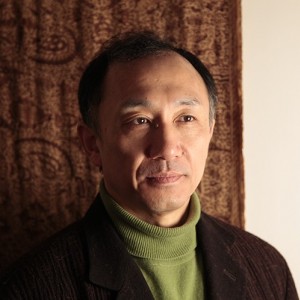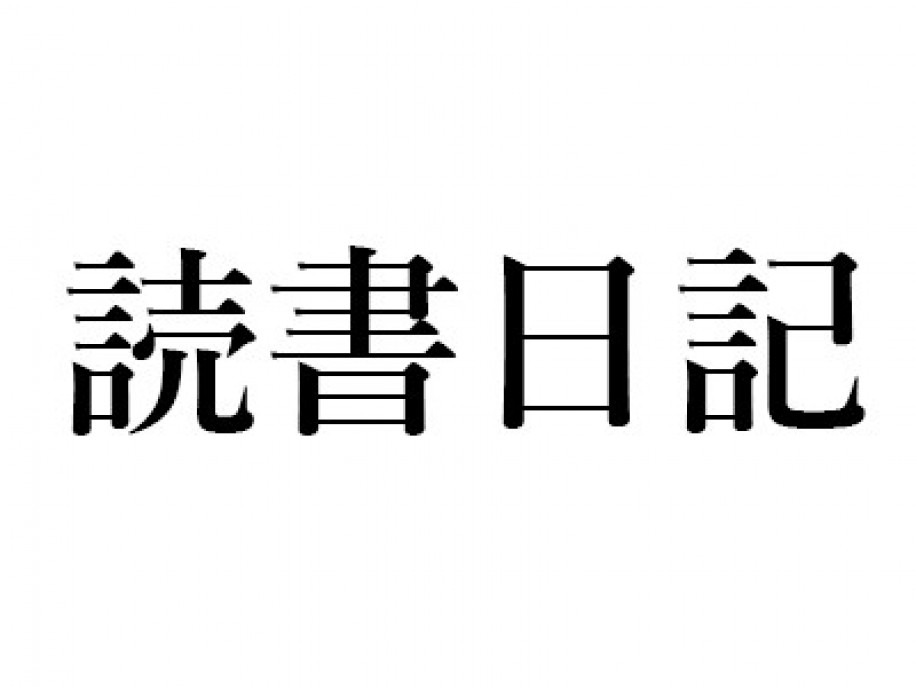書評
『美と礼節の絆 日本における交際文化の政治的起源』(NTT出版)
美を愛でる結社が整えた近代化の基盤
ライブドアによるニッポン放送買収騒動で、買収を仕掛けたH社長が軽装について「礼儀を失している」と貶(けな)されたことは記憶に新しい(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年)。だがなぜ、株の売買に礼儀だの作法だのが必要とされたのか。著者は市場取引を「基本的には心底を知りがたいストレンジャーである人びとのあいだでなされることが多い」とみなし、ゆえに「情緒コスト」が伴うと指摘する。企業の人事担当が採用を断る際に「残念ながらご希望にそえません」と一筆加えるのは、志願者に配慮してのことだ。見知らぬ人同士のつながりには、情緒コストを削減する「シヴィリティー(市民的礼節の文化)」が必要なのである。西欧では、中世身分制の崩壊後、礼節をいかに整えるかが問題となった。
著者は前著『名誉と順応』で、中世日本の武士たちにおける「名誉」追求の文化が、主従関係が常に反故(ほご)にされる不確定性にさらされていたからこそ意義を持ったという斬新な解釈を示した。本書では、礼節の文化が「座」など中世における自発的結社を起源とすると見ている。連歌や茶の湯など集団で営まれるセッション型の芸能は、礼法にもとづく社交の典型だというのだ。
こうした「美的なパブリック圏」は、徳川期に爆発的に拡大する。商品市場の広がりとともに都市では消費文化が花開き、高い識字率を背景に出版産業が勃興(ぼっこう)して、俳諧やファッション、貸本などで美を愛(め)でる結社が人々をヨコにつないだ。身分制や分割統治といったタテ割りの幕藩体制が全国を支配する一方で、それは私的な領域をつなぐ「弱い紐帯(ちゅうたい)」としてのみ容認された。こうした「徳川ネットワーク革命」によって美意識や礼節、教養が育まれ、日本は経済発展と近代化の準備を整えたというのである。
コーヒーショップやパブにおける政治的討議が西欧における民主制の揺籃(ようらん)となったとしばしば言われるが、そうした理想の「市民社会」を経由しなかった日本がなぜ発展を実現したのか。「文化資本」や「社会資本」を繁栄の基盤とみなす近年の諸説を駆使しつつ、重厚かつ説得的な説明が展開されている。
朝日新聞 2005年8月28日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする