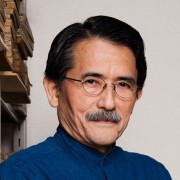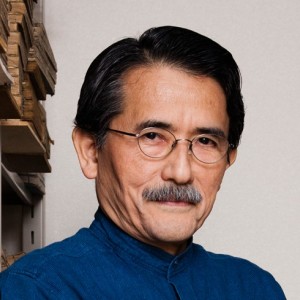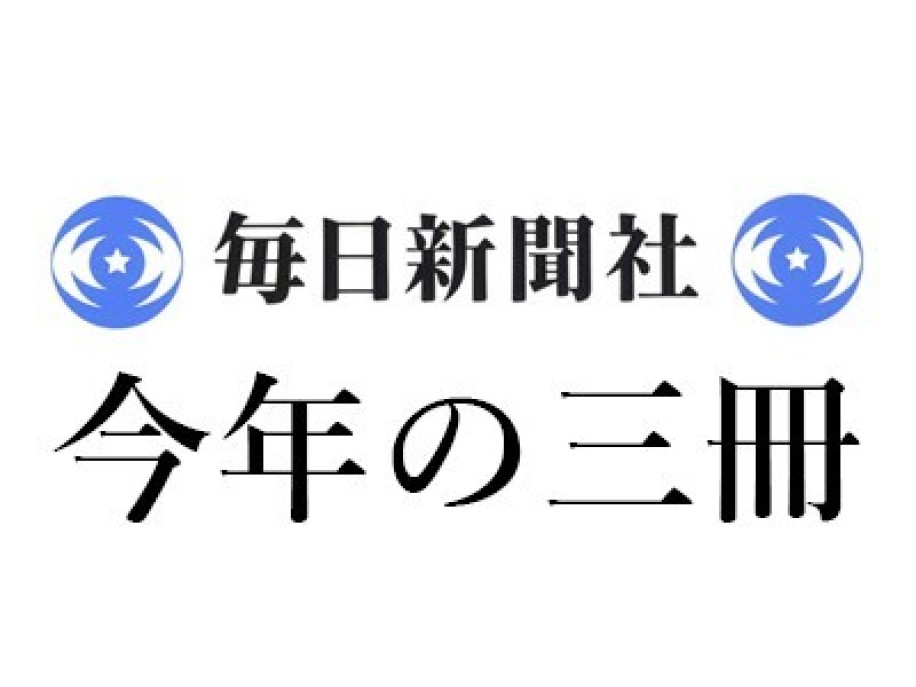書評
『青年小泉信三の日記―東京‐ロンドン‐ベルリン 明治四十四年‐大正三年』(慶應義塾大学出版会)
健全な若き魂
後に慶応義塾の名塾長と謳われ、皇太子殿下の御養育にも当った小泉信三の青年時代の日記がこのほど初めて公開された(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2003年)。小泉家に秘蔵されて今まで全集にも未収録のその日記は、明治44年、彼の大学卒業前後から始まり、ロンドン、ベルリンの留学時代を通過して世界大戦勃発によるベルリン脱出前夜に終っている。
時代的にも、また個人史的にも非常に興味深いもので、漱石のロンドン日記と双璧をなすであろう。
一読、あたかも五月の清冽な風が心に吹き抜けるような感動を味わうことができる。
小泉信三という人は、ほんとうによく学びよく遊ぶ人であった。
ロンドン大学のLSEで経済の勉強を進めるのと同時に、実にマメに観劇もし、テニスなどの運動もして、一時も無駄にしていないような感じがする。それでいて、文章の行間からは、なにかこう余裕綽々たる明るさ、ほほ笑みのような柔らかさが立ちのぼって来、健全な青年の魂が躍如としていて、じつにすがすがしい。この意味では、精神ごく不健全であった漱石のロンドンとは正反対であるが、しかし、それでもそこに私は一脈の「通いあうもの」を感じる。
例えば大正二年の初夏のころには、「心哀しみて堪え難し」などというような望郷と憂愁をしきりと訴えるところもあり、しかしその一方で、たまたま見た『ジュリアス・シーザー』を散々にこき下ろしているなど、常に意気軒高たる批判精神が息づいてもいる。
つまり、イギリスに暮らし、そこで壮烈に学びながら、しかしあくまでもそこにインボルブされない独立の魂というものを、私は両者に共通して読むのである。
小泉は、ロンドンの日本人社会にもイギリス人社会にも一定の距離を保った。そうして悠々と自立して、学ぶべきは学び、批判すべきは批判して譲らなかった。この不羈独立の精神が、後に慶応の塾長として大きく開花するのだと、この日記は示唆している。
初出メディア
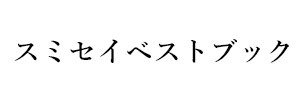
スミセイベストブック 2003年3月号
ALL REVIEWSをフォローする