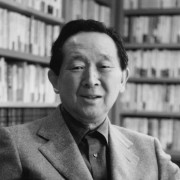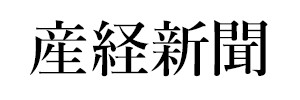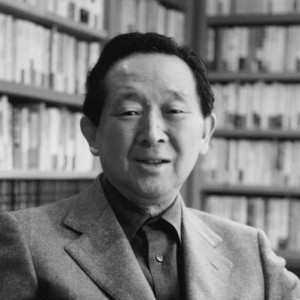書評
『優雅で感傷的な日本野球』(河出書房新社)
フランス文学、および演劇学の渡辺守章さんから、表象文化論を専攻する組織の発足にあたってシンポジウムを開くから、と招集がかかった。氏は〈芸術表象〉の対象を拡大して、民芸的表現や民族芸能、イメージ文化のネットワークを支える商業デザインやコマーシャル映像まで考えているようだ。場所が、最近知名度が高くなった東大教養学部というのにも興味をひかれて参加することにした。同じメンバーの浅田彰氏も「僕がここにいてもいいんですか」などと皆を笑わせていた(というのも、浅田氏と同じように「新しい知」の代表者と見られていた中沢新一の招聘を巡って、教養学部が混乱したばかりだったからである)。その際の議論を整理してみて、私は絶え問なき差異の製造、そのことによって自動的自己増殖過程に入ってしまったかに見える擬似差異を追うのに疲れてきている社会の姿が見え隠れしていたように思った。また、我が国には、かつて表象を求める強大なエネルギーであった〝集団的無意識〟が存在しないのでビッグ・ロマンは生れないのではないか、それならば文学はどこに行くのかというようなテーマも流れていたようであった。
私は議論に耳を傾けながら、実は『優雅で感傷的な日本野球』の印象と、この作品が三島賞に選ばれた時の文壇(というようなものがあればの話だが)の戸惑いの表情を想起していた。
この作品は、無限に不確かな差異を生み出している今日の社会を、「日本野球」という記号で見事に捉えてみせた芸術表象である。第一章〝偽ルナールの野球博物誌〟にはじまって七篇に分れている全体は、小説の構成としても効果が綿密に計算されているように見えるが、おそらく書いてゆくうちにそうなってしまったのであろう。そこに作者の凡庸ではない才能が感じられる。またいくつかの表現手法を使い分ける力と同時に、鋭く過激なまでの批評精神を読者は受取らなければならないと思う。就中(なかんずく)〝日本野球創世譚〟は、〝文学的芸術表象〟とは何かを示す、今日的な範例のような気が私にはしたのである。
と同時に、文学表現の両義性、多義性を、古い権威主義の立場から認めようとしない人々がいることも、毀誉褒貶の間から見えてきたのであった。このような非文学的文学者の無理解に接しては、シンポジウムの参加者ならずともイロニーに満ちた笑いを浮べざるを得ない状況であるだろう。
三島由紀夫の晩年の〝政治的〟行動から、賞の名前に拘泥するような愚論は論外としても、かつて安部公房の『赤い繭』その他の作品が芥川賞を受賞した時、当時の文壇の権威、宇野浩二が示したような烈しい拒否反応が現れなかったことも、今回の三島賞決定の特徴であった。〝文壇〟に元気と自信がなくなっているのかもしれない。
この作品の文学的過激さが充分に理解されていないとすれば、これは文壇が時代からはずれてしまっているからではないか。三島賞の名にふさわしい作品が選ばれたと思うだけに、私にはその事が気懸りである。
【この書評が収録されている書籍】
私は議論に耳を傾けながら、実は『優雅で感傷的な日本野球』の印象と、この作品が三島賞に選ばれた時の文壇(というようなものがあればの話だが)の戸惑いの表情を想起していた。
この作品は、無限に不確かな差異を生み出している今日の社会を、「日本野球」という記号で見事に捉えてみせた芸術表象である。第一章〝偽ルナールの野球博物誌〟にはじまって七篇に分れている全体は、小説の構成としても効果が綿密に計算されているように見えるが、おそらく書いてゆくうちにそうなってしまったのであろう。そこに作者の凡庸ではない才能が感じられる。またいくつかの表現手法を使い分ける力と同時に、鋭く過激なまでの批評精神を読者は受取らなければならないと思う。就中(なかんずく)〝日本野球創世譚〟は、〝文学的芸術表象〟とは何かを示す、今日的な範例のような気が私にはしたのである。
と同時に、文学表現の両義性、多義性を、古い権威主義の立場から認めようとしない人々がいることも、毀誉褒貶の間から見えてきたのであった。このような非文学的文学者の無理解に接しては、シンポジウムの参加者ならずともイロニーに満ちた笑いを浮べざるを得ない状況であるだろう。
三島由紀夫の晩年の〝政治的〟行動から、賞の名前に拘泥するような愚論は論外としても、かつて安部公房の『赤い繭』その他の作品が芥川賞を受賞した時、当時の文壇の権威、宇野浩二が示したような烈しい拒否反応が現れなかったことも、今回の三島賞決定の特徴であった。〝文壇〟に元気と自信がなくなっているのかもしれない。
この作品の文学的過激さが充分に理解されていないとすれば、これは文壇が時代からはずれてしまっているからではないか。三島賞の名にふさわしい作品が選ばれたと思うだけに、私にはその事が気懸りである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする