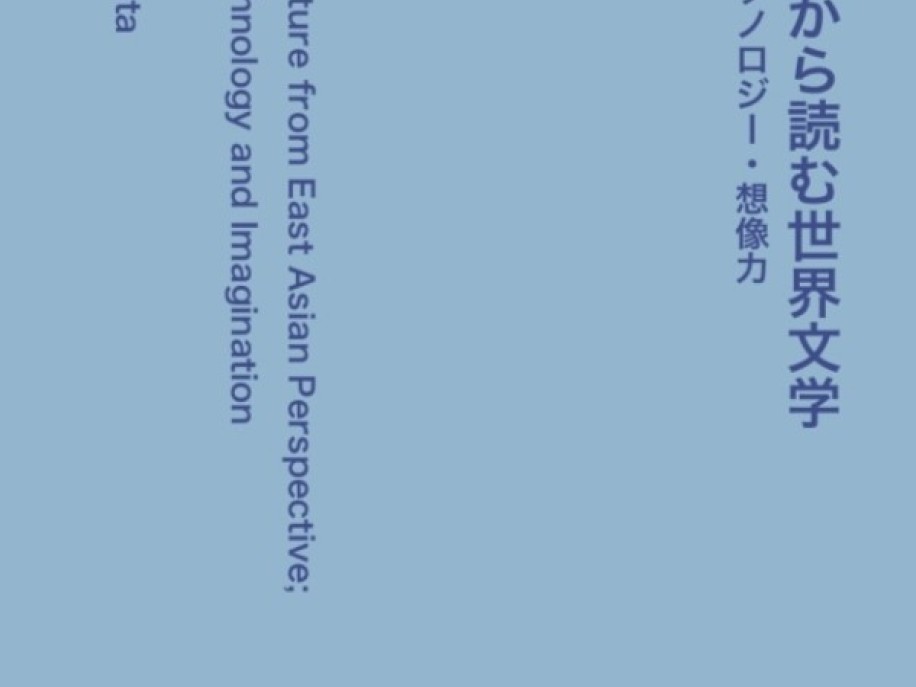書評
『中国奇想小説集: 古今異界万華鏡』(平凡社)
奇想のなかで重んじる論理
魯迅は幼いころの思い出をつづった「阿長(アチャン)と『山海経(せんがいきょう)』」のなかで、奇想の動物誌というべき『山海経』を手にしたときの驚きを述べている。ふしぎな鳥がいる。怪しい獣がいる。少年は胸おどらせながらページをくった。一本足の牛。水中の黒い亀は鳥の首をもち、木を裂くような声を出す。まるで雷に打たれたように全身がふるえたという。それは「私がはじめて手に入れ、もっとも愛した宝の書」になった。のちに魯迅は、中国小説の歴史的変遷をめぐる講演において、文芸作品の発生を語った冒頭に、神話を含む大きな作品のうちで最も重要な一つとして『山海経』をあげた。また『中国小説史略』のなかでも、この奇想書に大きな意味を認めている。
井波律子『中国奇想小説集』は、井波版『中国小説史略』というものだ。三世紀に始まる六朝時代から二十世紀の清末にいたるまで、中国小説の一つの流れである奇想小説を追っていく。六朝の時代には「志怪小説」といわれる怪異譚(たん)が一大ブームをみた。時代が下って七世紀から十世紀の唐の御世、「唐代伝奇」と称される短編が世をにぎわした。さらに下って宋代になると――
「私は昔から中国の奇想小説が好きで」とあるとおり、著者はいかにもたのしげにエピソードをおりまぜて語っていく。あいだにそれぞれのエポックの代表的な作品がはさまれて、計二十六篇。「怪」の物語であって、常とはちがう何か。その常ならぬ何かを前触れする出だし。
鵝鳥(がちょう)を入れた籠を背負って山中を歩いていた男が、十七、八歳の書生と出会った。書生は路傍に寝ころがって「足が痛い」と言い「その籠のなかに入れてほしい」と頼んだ。言うなりサッサと籠に入ってしまった。
出だしはいたって日常的である。鵝鳥と書生が並んで座っているのも日常的でユーモラスだが、以下、奇想天外な経過にあっても日常性のルールは保持されていく。美少女の口から吐き出された若い男は「きちんと時候の挨拶(あいさつ)」をして、スキをうかがい、自分は美少女を愛しているわけではなく、別に女を同行していると言って口から女を吐き出して長々と戯れていた。口から吐き出す前半に対して後半では、次々と飲み込んでいく。奇想と日常性の一方で、物語はきわめて論理的につくられている。思うに中国の読者には、たとえ「怪」の出来事でも、論理をわきまえなければ愉(たの)しめないのだろう。
奇想をとりあげるのに、時代によって記録型と物語型の二つがあったようだ。二つのスタイルが追いつ追われつしながら、「奇」をつむいでいく。おおかたが世にいう「文人」たちの筆のすさびによった。筆の持ち主たちは「事多き現実」にうんざりで、「この世の外ならどこへでも」という心境から、得意の筆を走らせた。つまるところ、奇想小説を読んだり書いたりするのが、何よりの「消遣」だった。
興味深い指摘である。消遣は「シャオチェン」と読み、「気晴らし」にあたる。「牡丹(ぼたん)灯籠(どうろう)」をはじめとして、順次わが国に渡ってきた奇想がいくらもあるが、同じように怪が物象に触れて山川に形をあらわしたり、木石に姿を見せても、根本的にちがう何かがある。中国の人には、異常は我にあって、物それ自体が異常なのではないとする考え方があるのではなかろうか。
だからこそ「シャオチェン」とうそぶいて、論理の輪をどこまでもからませた語りは、私にはどうもそんな気がするのだが、誰でも愉しめるわけではなく、愉しむためには「天下の賢者」でなければならない。
ALL REVIEWSをフォローする