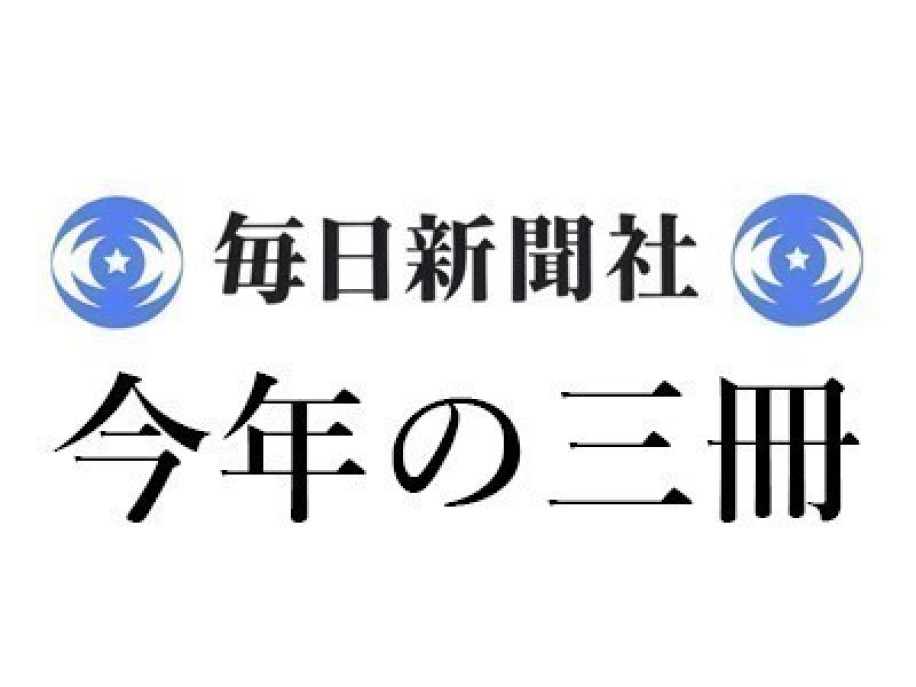書評
『天才伝説 横山やすし』(文藝春秋)
テレビの国の淋しい天才
小林信彦の『天才伝説 横山やすし』(文藝春秋)の中に、〈漫才ブーム〉の最中、萩本欽一が「日本の大衆の笑いの質が変りますよ、きっと」と著者に予言するシーンがある。萩本欽一の勘の良さは定評がある。ぼくは一年後に、彼の予言がいかに的確かに感心していた。
いまは、もっと良くわかる。……。日本のテレビ史上最悪の荒野。笑いの半素人と素人の〈もんじゃ焼き状態〉で収拾がつかなくなっている。頭を使って作り出された台本で笑いを演じているSMAPの番組に人気が集中するのは当然である。一九七〇年までは、この方式が主流だったのだが。
そして、横山やすしとは、
漫才の国から漫才を世にひろめるために生まれてきた男であるが、時代が悪かった。テレビジョンなどという下らないものがはびこっていたからであろう。
テレビの世界というところは奇妙なところで、たとえば、そこには視聴率という怪物が住んでいる。それは一分毎に計測されたグラフになっていて、そのグラフは同時刻の他番組のそれと色分けされ、絶えず比較される。そして「×時十五分から十七分にかけて視聴率が二%ほど下がるのは、Aチャンネルの同じ時間帯のBコーナーの企画と視聴者の十代の女の子を取り合っているためだから、このコーナーは十分スタートにしてはどうか」というようなことをプロデューサーたちはたえずしゃべり、テレビの世界の住人ではない(週末通ってはいるけれど)ぼくは、そんな瑣末なことどうだっていいじゃんと思い、それから、ふと考える。
テレビの世界にも深く関わった小林信彦の苦々しい述懐を待つまでもなく、いまのテレビが面白いとか、ためになるとか思う人間はたぶん皆無に近く、つまらない、くだらないとおそらくはテレビの世界の住人でさえ内心では感じている。だが、どうしようもないのだ。なぜなら、テレビの世界の住人の前にはなにかを作って埋めねばならない空間が広がっていて、彼らはその空間を、過去の経験によって埋めてゆくのだが、そのためには何かの「基準」がなければならず、そして彼らにとって唯一の「基準」とは「目に見える」視聴率なのである。
なぜ、そんな誰もが考えるような当たり前のことを書くのかというと、視聴率しか「基準」がないというテレビの世界のあり方は、実はぼくたちの国のあり方なのかもしれないからだ。
かつてAV監督のバクシーシ山下が吐き捨てるように「『JJ』を読むこと自体がAVギャルへの第一歩なんですよ」といい、「物欲を煽るだけ煽って、手に入れる方法は買うしかないわけだから。そうすると金が必要になってくるわけで、そこでみんなAVギャルになっちゃうわけですよ」と付け加えた。そこは目に見える「物欲」しか基準のない、そう、やはりテレビの国だったのである。
人は日々、埋めなければならない空間を持ち、そのためには「基準」が必要であり、それを「倫理」とか「世界観」と呼びならわしてきた。しかし、いまテレビの世界の「視聴率」という基準を笑う余裕はぼくにはない。ただ、テレビの世界がこの国の特殊な部分ではなく、もしかしたら資本主義の最後の形として、ここは国そのものがテレビの国になったのではないかという恐ろしい思いにとらわれるのだ。
テレビの国に〈天才〉はいらない。〈天才〉は基準を壊すからだ。『天才伝説』は、テレビの国について誰よりも詳しい著者によって書かれた、テレビの国が完成していく時代に生まれた不幸な〈天才〉についての物語である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする