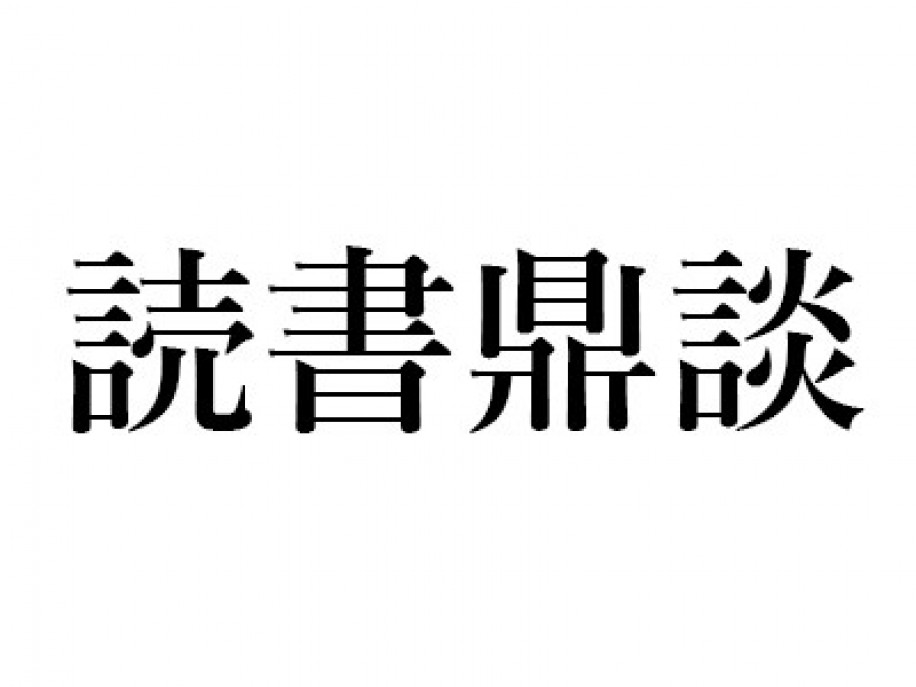書評
『世界温泉文化史』(国文社)
海外温泉事情
たっぷりとした湯につかり、思うぞんぶん手足を伸ばす。このときほど、「ああ、日本人だなあ」
と実感することはない。シャワーの国の人たちには、この気持ちよさはわかるまい、と。
温泉にいたっては、いよいよその感を強くする。私たちは、風呂好きを自認する国民といえるだろう。
が、広く世界を見渡せば、温泉の風習は、何も日本だけのものではないようだ。ヨーロッパの温泉の文化と歴史をまとめたのが、『世界温泉文化史』(ウラディミール・クリチェク著、種村季弘他訳・国文社)。ロシア、アジア、イスラム圏、アフリカ、アメリカの温泉事情にもふれている。
古代ギリシャの時代からすでに、温泉のまわりに治療区が生まれ、巡礼の地、あるいは保養地として、人々を集めていたようだ。入浴が第一次全盛期を迎えたのは、ローマ時代。そういえば、カラカラ浴場なんていうのができたのも、この頃。
再び盛んになったのは、中世である。都市のブルジョアジーの成長とあいまって、公衆浴場が次々と誕生する。それは、共同体のコミュニケーションセンター的役割も果たしていた。
十五世紀には長くつかるほどよいとされ、温泉では客は、湯の中で飲み食いし、ときにはそのまま眠ったりもした。溺死した例も少なくないという。
十七世紀後半からは、代わって飲用療法が流行する。尿の色が湯の色と同じになるまで飲むのがよいとされ、人々は歩数計ならぬ杯数計をぶら下げて、庭を散歩した。
「飲む風呂」では、裸のつき合いならぬ、服を着たままのつき合いのため、温泉はリゾート化、上流階級の社交界化する。音楽をはじめ、造園、劇場建築など、さまざまな芸術が花開いたことはいうまでもない。
そうした流れが、さまざまな文献から引いたエピソードによって、語られていく。
こうしてみると、洋の東西を問わず、人々が温泉を、たんなる治療の場としてだけでなく、いかに付加価値をつけて楽しんできたかがわかる。その時代その時代の、健康神話のようなものが広まるのも、今と同じ。
驚くべきは、ヨーロッパにおける温泉研究の、歴史の長さ。何百年分もの文献と治療の経験に支えられ、十九世紀後半には、「温泉学」が大学の医学部の専門教科にもなったとか。医学者である著者が、文化史を編んだことそのものが、ヨーロッパにおける温泉の自然科学的研究と人文科学的研究と、ふたつの伝統の合わさるところといえるだろう。
訳者は「あとがき」で、日本には、諸外国とわが国の温泉事情の比較文化史の研究には「いまのところこれといったものがない」と嘆く。
想像するに、日本では、
「風呂が好きなのは、日本人だからなのさ」
で通ってしまうからでは。温泉大国ならではの、逆説というべきか。
「本書は、わが国のこうした温泉文化研究水準の現状からして、刺激的な一書となるだろう」と、訳者。そうありたい。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする