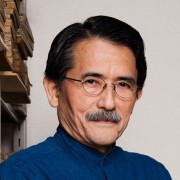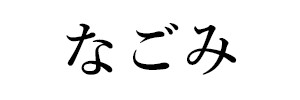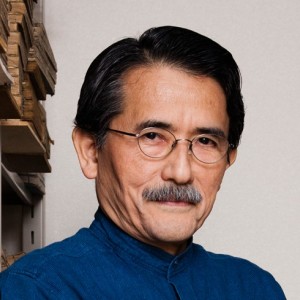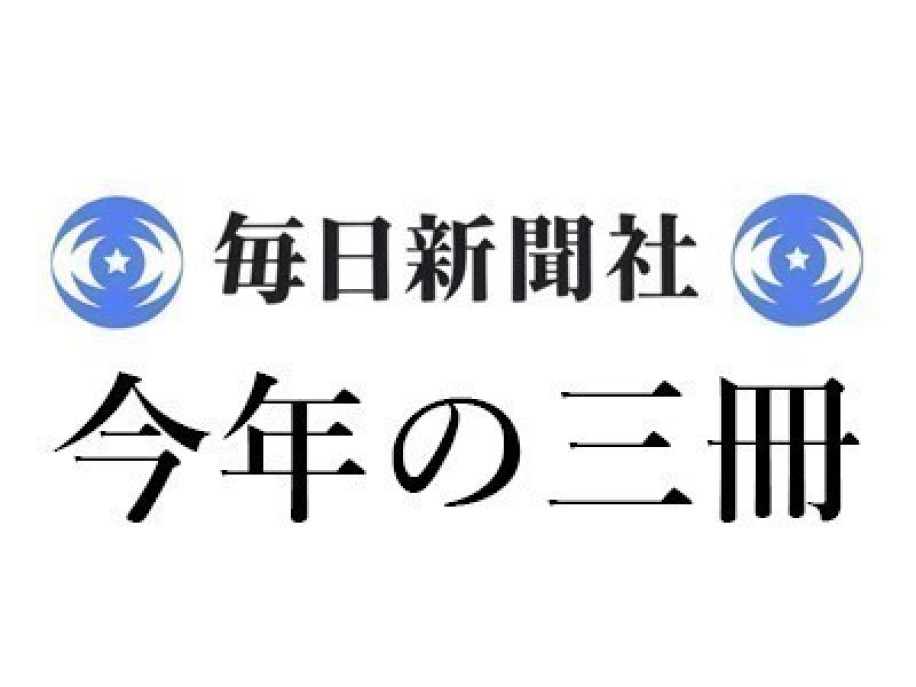書評
『情報文明の日本モデル―TRONが拓く次世代IT戦略』(PHP研究所)
たまにはこういう本も読んでみた
コンピュータは、ものを書いたり、インターネットで情報を検索したりするために、とても役に立つ機械であって、今からの時代は、誰もこのことに無関心や無能力ではいられないに違いない(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆年は2001年)。かく言う私は、1987年以来、すべての著作はコンピュータで書いているので、この十年あまりの技術的進歩には、非常に大きな恩恵を蒙ってきた。
が、しかし、現在の日本のコンピュータの基礎的技術はハード・ソフトの両面にわたり、アメリカにほぼ制圧されている現実があって、そのことは、文化的にも国防的にも、まさに累卵の危うきにあるがなあと思っているのは、たぶん私だけではあるまい。
この現状を許してしまったのは、1982年に、アメリカの戦略的罠に引っ掛かったIBM産業スパイ事件という椿事が出来し、日本のコンピュータメーカーがすっかり萎縮し恭順してしまったという事実があって、これが一つの分かれ目であった。
けれども、その少し後でコンピュータに取りついた私にとって、大きな期待を抱かせてくれたものは、純国産のOS(オペレーション・システム)であったTRONのプロジェクトの立ち上がりであった。これは、東大の坂村健(本書の著者)が提唱し構築した、きわめて優秀な、またオープンなシステムで、それを用いれば、あらゆる言語のあらゆる文字が、ほぼ無限に扱えることになっていた。このシステムは直ちに国産コンピュータに応用され、それを組み込んだコンピュータが教育用に採用されることにもなっていた。
ところが、その時アメリカの通商代表部がこのシステムを関税外障壁として言いがかりをつけてきたのだった。情けなかったのは、その時の日本政府の対応で、直ちに断乎たる反論をするでもなく、たちまちアメリカに迎合して教育用のコンピュータに採用するのを取りやめてしまったのである(たしか宮沢喜一首相の政府であったが・・・)。これこそ、日本が起死回生の大きなチャンスを逃した画期的転換点で、以後アメリカの独走を許してしまった戦後最大のミスであったと私は思う。
爾来しかし、坂村さんとTRONのチームは幾多の妨害にもめげず、産業用の組み込みシステムとしてこのTRONを洗練し、今や携帯電話などには、100%このシステムが組み込まれているのだそうである。
その坂村さんが、現在の時点で、いったい日本と日本人がどういう立場で、このIT化に立ち向かえばよいのかということを、TRONの考え方を基底に据えながら分りやすく説くのがこの本である。
ひとことでいえば、日本には日本のモデルがあり、アメリカ型のモデルに追随することがグローバライゼーションなのではないということを、言語や文字や、また文化・国民性などまで含めて広く論じたものである。そこには見るべき卓論が頗る多い。
現今の諸事情にかんがみても、いま自分たちが何をどう考えるべきなのかじっくり再検討し、現代と未来に思いを致してみるのも決して無駄ではないと思うのである。
ALL REVIEWSをフォローする