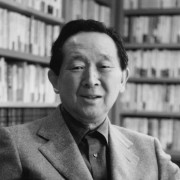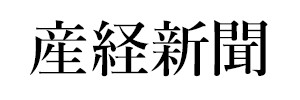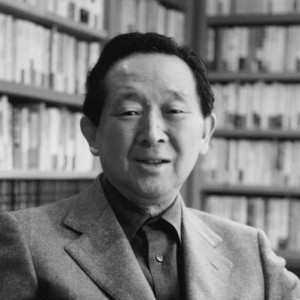書評
『身がわり―母・有吉佐和子との日日』(新潮社)
肉親のことを書くのは難しい。それは世間が見ている肉親と自分が見ている人との間に差異があるからである。親が有名であればあるほどこの乖離は大きくなり、幼い子はそれをどう埋めたらいいのか分からない。
有吉佐和子は、生前かなり怖れられた作家であった。歯に衣を着せない批評、優れた分析力と集中力。しかし娘から見れば猪突猛進型で、することがチグハグで、この本の行間からは、愛すべき人間像が浮び上ってくる。
だが娘は、その愛すべき特性の被害者なのだ。母親に言わせれば「この娘は天才」なのだから。天才にされた方はたまったものではない。娘にとって母親を客観的に眺めるのは、息子が父親のことを見る以上にむずかしいのかもしれない。親に才能があればあるほど嫉妬心は内側にこもる。
親も必死だったのだ。親は踠(もが)いたりつまずいたりしながら自分に納得のゆく生き方を貫こうとしていたのだ、と知るまでには時間がかかる。娘や息子は屡々、親の死のあとで、その偉さや苦しみ、自分への愛情表現の独特のかたちなどに気づく。
この作品は、著者の目を通して眺められた有吉佐和子が主人公である。『身がわり』という題は英語の表現 She's survived by her daughter、から取られている。「彼女はその娘によって生きながらえた」と直訳できるとおり、有吉佐和子はいい〝身がわり〟を持った。
勿論、「身がわり」は本人そのものではない。生きている時代や環境が違うし、身がわりの方がより知的であるかもしれないし、より素直かもしれない。少くとも作品を読む限り、有吉佐和子とは異質の著者の文学性はまぎれもない。「母親は子供を〝たあちゃん〟と呼んだ」と書いた時、作家有吉玉青が誕生したのだ。ここには成長するにつれて変化してゆく心境に導かれた母親という人物への認識過程が、素直に描き出されている。その素直さを美しさとして現出させているのは、簡潔な描写を可能にした観察眼であり、素材を選別する著者の才能である。娘は、親の期待や感情移入に視点を乱されずに親を見なければならない。年齢ばかりではなく、優れて強靱な文学性が必要なのだ。いくら年をとっても、親の顔が見られない人も多いのである。
有吉佐和子は実に魅力的な作家だったと、この本を読んで思った。頭の良さが生活人としての不器用と混じって個性を形成していた。この作品にはよく、娘の方が大人のように見える母娘の関係が登場する。しかしムラ状況を作ることが多い日本の社会は、彼女の魅力をどれくらい認識していただろうか。文壇よりは読者や観客の方が、有吉佐和子のことをよりよく理解していたように思える時がある。それだけに彼女が稀有の身がわりを得て蘇ったことを一人の若い作家の誕生と共に喜びたい。
有吉佐和子は、生前かなり怖れられた作家であった。歯に衣を着せない批評、優れた分析力と集中力。しかし娘から見れば猪突猛進型で、することがチグハグで、この本の行間からは、愛すべき人間像が浮び上ってくる。
だが娘は、その愛すべき特性の被害者なのだ。母親に言わせれば「この娘は天才」なのだから。天才にされた方はたまったものではない。娘にとって母親を客観的に眺めるのは、息子が父親のことを見る以上にむずかしいのかもしれない。親に才能があればあるほど嫉妬心は内側にこもる。
親も必死だったのだ。親は踠(もが)いたりつまずいたりしながら自分に納得のゆく生き方を貫こうとしていたのだ、と知るまでには時間がかかる。娘や息子は屡々、親の死のあとで、その偉さや苦しみ、自分への愛情表現の独特のかたちなどに気づく。
この作品は、著者の目を通して眺められた有吉佐和子が主人公である。『身がわり』という題は英語の表現 She's survived by her daughter、から取られている。「彼女はその娘によって生きながらえた」と直訳できるとおり、有吉佐和子はいい〝身がわり〟を持った。
勿論、「身がわり」は本人そのものではない。生きている時代や環境が違うし、身がわりの方がより知的であるかもしれないし、より素直かもしれない。少くとも作品を読む限り、有吉佐和子とは異質の著者の文学性はまぎれもない。「母親は子供を〝たあちゃん〟と呼んだ」と書いた時、作家有吉玉青が誕生したのだ。ここには成長するにつれて変化してゆく心境に導かれた母親という人物への認識過程が、素直に描き出されている。その素直さを美しさとして現出させているのは、簡潔な描写を可能にした観察眼であり、素材を選別する著者の才能である。娘は、親の期待や感情移入に視点を乱されずに親を見なければならない。年齢ばかりではなく、優れて強靱な文学性が必要なのだ。いくら年をとっても、親の顔が見られない人も多いのである。
有吉佐和子は実に魅力的な作家だったと、この本を読んで思った。頭の良さが生活人としての不器用と混じって個性を形成していた。この作品にはよく、娘の方が大人のように見える母娘の関係が登場する。しかしムラ状況を作ることが多い日本の社会は、彼女の魅力をどれくらい認識していただろうか。文壇よりは読者や観客の方が、有吉佐和子のことをよりよく理解していたように思える時がある。それだけに彼女が稀有の身がわりを得て蘇ったことを一人の若い作家の誕生と共に喜びたい。
ALL REVIEWSをフォローする