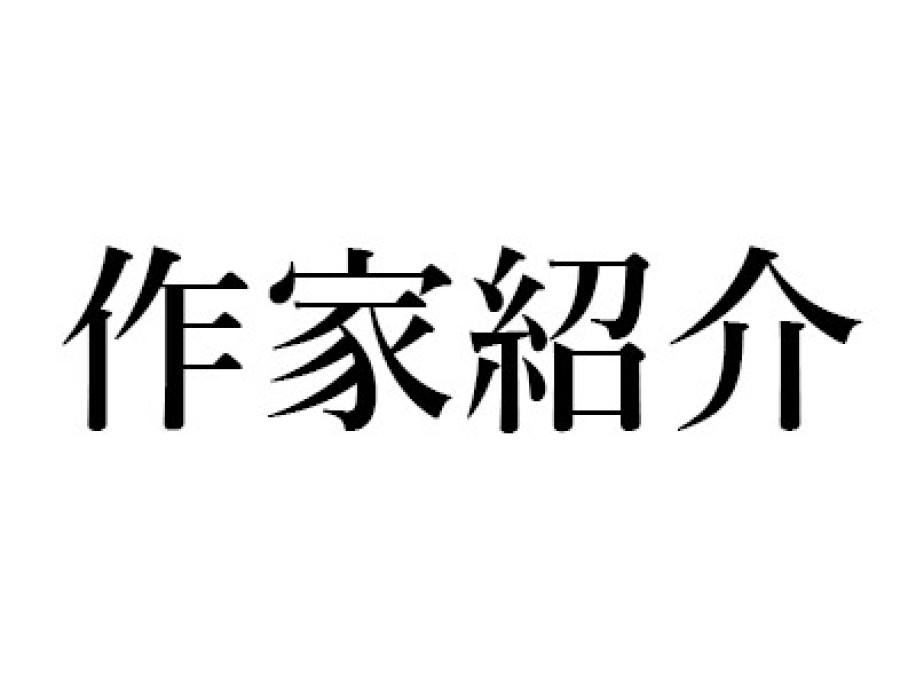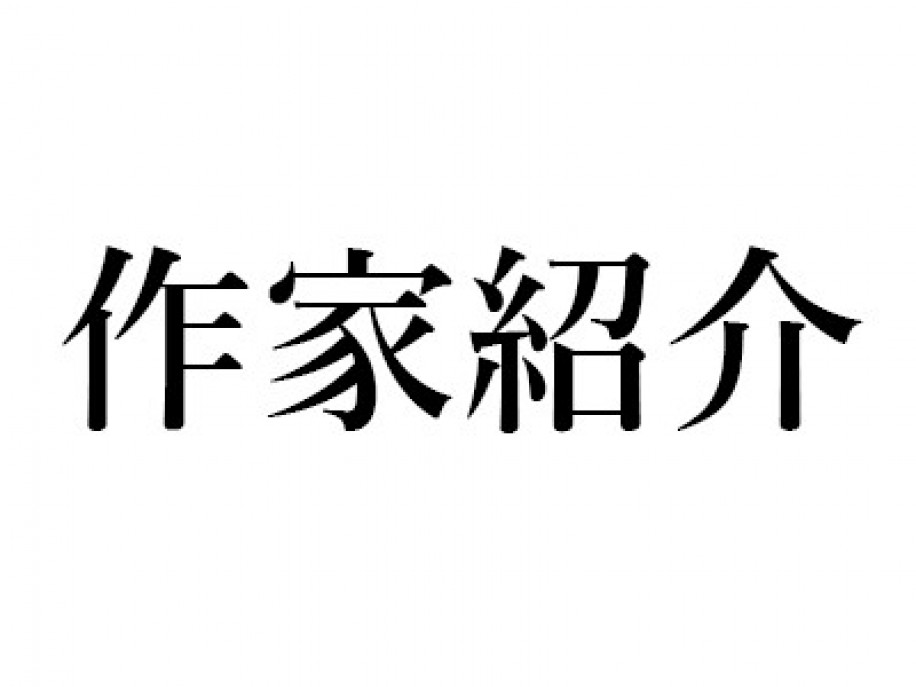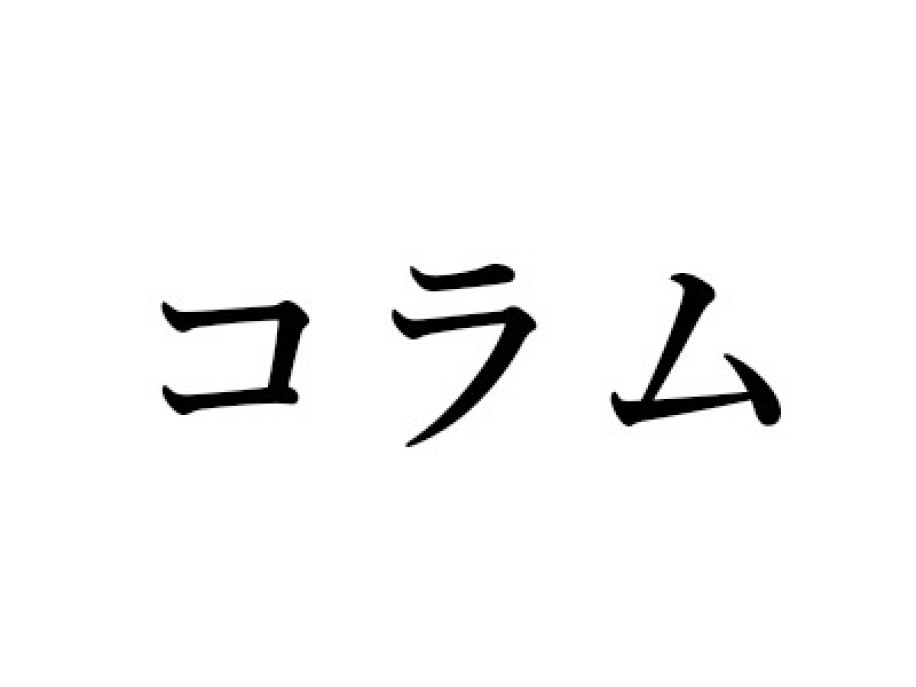書評
『リオデジャネイロに降る雪――祭りと郷愁をめぐる断想』(岩波書店)
愛と郷愁のブラジル
オリンピックもパラリンピックもひとたび競技が始まると、多くのメディアで扱われるのは自国選手のことだけになり、開催地の文化や社会背景については選手もコメンテーターも観客も、ほぼ無視と無知を貫くのが毎度のことでがっくり。こんな本を読んでからリオに行けば、行った先で見えてくるもの、見たくなるもの、買ってくるものがだいぶ違ってくるだろう(ALLREVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2016年)。ブラジル、あるいはリオといえば、サッカー、サンバ、カーニバル、それに加えてファヴェーラ(丘の斜面にできた居住地区)と犯罪、というのがステレオタイプの基本五点セットだろう。ところがこの本は、それとはかなり異なったブラジル像を描き出す。基本五点セットが主に貧困層にかかわる大衆文化のあらわれであるのに対して、中産階級の生活の実感や、詩や文学、建築などの芸術文化のほうに重点がある。
ブラジル文学の中でも詩の専門家である著者は、音楽に接近するにしても歌詞の側から入って、そこからブラジル人の世界を読み取ろうとする。だから、ボサ・ノヴァの名曲「イパネマの娘」を語るにしても、曲を書いたアントニオ・カルロス・ジョビンよりも、その詞を書いたヴィニシウス・ジ・モライスのほうが前面に出る。そして、ボサ・ノヴァが一九六〇年代前半の数年間を越えてブラジルを代表する音楽でありえなくなった事情を、政治情勢との関係であざやかに示す。また、五年間もリオに暮らした若き日の堀口大學について、ここで読むことになるとは予想外だった。
といっても、この本はまったく文学論の本ではない。もっと個人的なリオに対する愛と郷愁をこまやかな表現で描き出した、あまりにも繊細で、あまりにも気取った、今時めずらしい、きまじめで美しい一冊である。そしてまた、日本がブラジルに見習うべき点を指摘する提言の書でもある?? 日本の家族も友人も恋人も、もっとハグしあいましょう、と。
ALL REVIEWSをフォローする