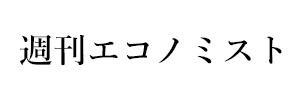書評
『ロミー・シュナイダー事件』(集英社)
ある女優の死
ロミー・シュナイダーは魅惑的だった。「夕なぎ」「離愁」「ルートヴィヒ」……凛として気品高く、虚飾のない自由な女。四十二歳の突然の死からもう十五年もたつのか、と感慨深い(ALLREVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1996年頃)。『ロミー・シュナイダー事件』(ミヒャエル・ユルクス著、平野卿子訳、集英社)はドイツでベストセラーになったロミーの伝記である。なぜ「事件」と銘うったのか。すなわちロミーの死がどうも自然死とはいいにくいからである。他殺ではない。自殺でもない。しかし読んでいるとその両方ではなかったかと思う。他者からの脅迫、恐喝と内部からの精神の崩壊と。それを描くため著者は、アンナというジャーナリストを設定、彼女が「ロミー・シュナイダー事件」の連載をある雑誌に書く、というフィクションの部分を一章おきに挿入する。ノンフィクションの伝記部分は、雑誌「シュテルン」の編集長だった著者が綿密なデータを駆使して正確に書いているが、それはアンナが書いた記事とも読め、一方、仮定や推理はフィクションの章で自由に羽ばたかせられる。この手法はかなりアクロバティックだが、本書の場合、必然的であり、成功しているといえよう。すなわちロミーを「間接的に殺した」連中は生存していて、何ら刑事罰を適用されていないからである。著者ユルクスはジャーナリズムによって彼らを社会的に断罪しようとした。
ロミーは女優としては「このうえなく成功」したけれど、「私生活はまったくダメな人」だった。生みの父親には捨てられ、育ての父親に誘惑され、二度の結婚は破綻して、財産をめぐって争いになった。数多くの恋愛リストは、最後まで愛したアラン・ドロンをはじめ、カラヤン、ブラント首相、ブルーノ・ガンツ、そして同性愛者でもあったから、ココ・シャネルやシモーヌ・シニョレの名がある。もちろん無名の恋人もいた。撮影中、監督は彼女にあてがう男を用意さえした。
なんて寂しい女性だろう。子ども時代の不幸を追い、スターになれるだろうか、いつまでスターでいられるかという不安とたたかい、彼女からうまい汁を吸おうという人間はたくさんいた。最初の夫は自殺、最愛の息子は突然死。こんな環境でロミーはアルコールと薬物にはまり込んでゆく。そして、半裸で麻薬をやっているビデオをネタに二番目の夫ビッシーニからゆすられていたことを本書は暗示する。
もう一つの通奏低音は、ロミーへのドイツ人の仮借なさである。ドイツはアラン・ドロンに走って祖国を捨てた彼女を許さなかった。ドイツ人でありながらナチスに抗し、SS(親衛隊)に犯される女を演じたロミーを許さなかった。本書は深い同情をもって華麗なスターの寂しい実生活を描くとともに、ドイツの触れられたくない狭量な戦後史をも浮き彫りにする。
ロミーは言った。
「しあわせのなかでだらしなく眠りこけているより、ふしあわせな情熱のほうがましよ」
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする



![夕なぎ HDリマスター版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41MRwDflGsL.jpg)
![離愁(スペシャル・プライス) [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51GS+JsHyXL.jpg)
![ルートヴィヒ デジタル完全修復版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51XuvjiU3WL.jpg)