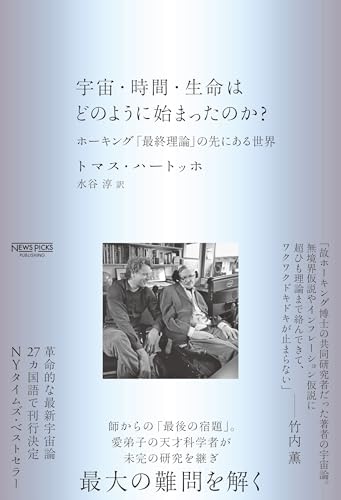書評
『反穀物の人類史――国家誕生のディープヒストリー』(みすず書房)
農業は自然と向き合っているか
一見無関係に見える二冊をたまたま同時に読み、現代文明がもつ自然との向き合い方を考えた。切り口は「農業」と「国家」である。人類は農業革命によって原始的な狩猟採集生活から脱却し文明への道を歩み始めたとされ、そこには定住生活こそ魅力的であり、それが国家を生み出したという前提がある。そこでの狩猟採集民は、「未開で、野生の、原始的な、無法の、暴力的な世界」にいるとされ、闇雲に山野を駆け回る姿で描かれる。実際は協働で堰(せき)や罠を作り、獲物を乾燥したり、更には野生種の穀草を育てるなど計画的に動いていたことがわかっている。
『反穀物の人類史』は、「種としての夜明け以来、ホモ・サピエンスは動植物種だけではなく環境全体を飼い馴らしてきた」とし、狩猟、採集、遊牧、農耕は組み合わされて「人間による自然界の再編という巨大な連続体」の上でわずかずつ滲み出してきたという見方を示す。
その中での定住である。一万二〇〇〇年前には永続的な定住、農業、牧畜が登場したが、それは農業革命に直接つながりはしなかった。一つには農業が重労働だったからだが、最大の問題は集合生活に見られる疫病だ。流行が始まると人々は移動し狩猟を始める。その間数千年の歴史を追うと交易なども始まっていくのだが、上手に生きようとする試みは、農業革命、更には国家の形成へとはなかなかつながらないのである。
現在の文明へとつながる国家の登場は、紀元前三一〇〇年頃と著者は書く。そこでの国家の定義は、税(穀物、労働など)の査定と徴収を専門とし、支配者への責任を負う役人階層を有する制度とされる。穀物栽培の始まりは定かではないが、紀元前五〇〇〇年には、いわゆる肥沃な三日月地帯で主食としての穀物が栽培されていた。それは目視、分割、査定、貯蔵、運搬、分配に適しており、課税の基礎となる。こうして穀物が国家を生み、国家が灌漑を行って農耕を大規模化し、農業革命を起こした。初期の定住社会にも支配者の搾取はあったろうが、制度化に到るには穀物栽培が必要だったのだ。
ここで「アラル海」に移る。カザフスタンとウズベキスタンの間にある面積が琵琶湖の一〇〇倍もあった湖アラル海の九〇%が今では失われてしまい、二〇世紀最大の環境破壊と言われている。湖が数年で砂漠に変化した原因は、ソ連という国家の農業政策にある。そこに流れ込むシルダリア川、アムダリア川から取水した運河が砂漠の地平線まで伸び、綿花畑や水田が生まれた。水が流れこまないアラル海の湖岸線は、一日に二〇〇メートル後退する地域もあったという。湖水の塩分濃度上昇、魚類の減少、飲料水水質悪化、砂嵐の多発など、急速な環境悪化が見られた。
そして、「砂漠を緑に」と宣伝された綿花畑も、塩害での放棄が見られる。しかも排水は砂漠にしみ込みシルダリア川に戻ることはないのだ。著者らの地道な研究による実態解明と植樹を通しての環境改善の努力には語りたいことがたくさんある。ただここでは「国家」、「灌漑」という問題に注目した紹介に止める。
狩猟採集(一・〇)、農業(二・〇)、工業(三・〇)、情報(四・〇)と来た文明の五・〇への移行が言われるが、自然との関わりを考えるなら、国家という問題を含めて、農業革命から見直してみる必要があるのではないか。今思うことだ。
ALL REVIEWSをフォローする