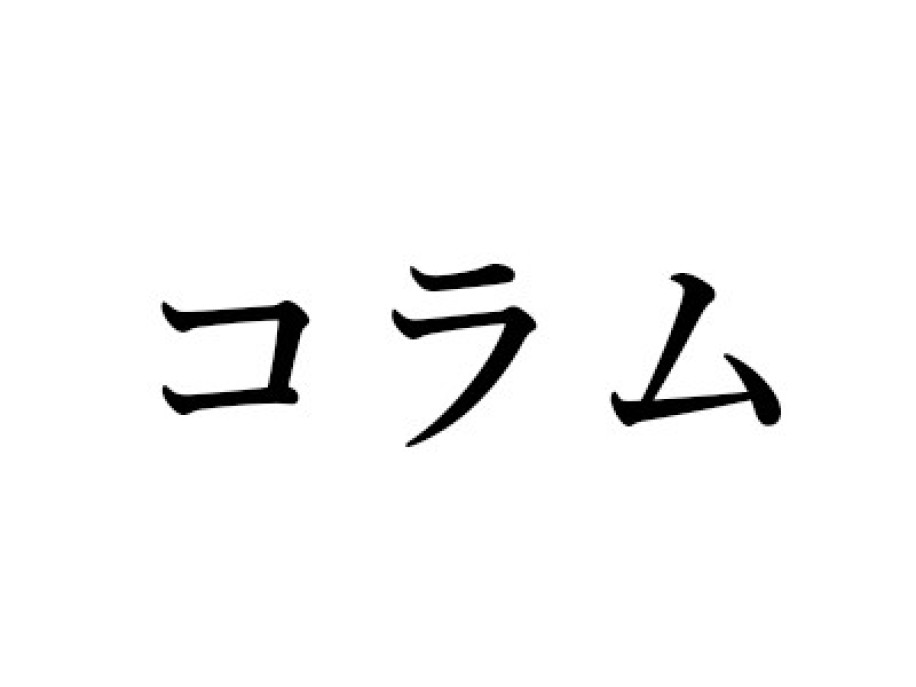書評
『よくできた女』(みすず書房)
「立派な英国女性」と過ごす心地よい時間
読み始めて、ひとたび中に入りこむと、でてきたくなくなる。小説の中があまりにも快適で愉快なので、つい長居をしてしまう。先が知りたくて読むというより、そこにとどまっていたくて読む。これはそういう小説だ。第二次世界大戦直後のロンドンに住む、未婚女性ミルドレッドの、生活と観察と意見。彼女は三十歳なので、いまならば若い女性の一種だろうが、当時はそうは分類されず、本人もそのことを十分に自覚している。オールドミスであることに、諦念と同時に誇りを持っているのだ。
立派なオールドミスであるためには教養が要る。育ちのよさも、良識も、謙虚さも。「よくできた女(ひと)」しかそれにはなれない。「よくできた女」だから、みんなに何かと頼りにされる。
イギリスの地域社会の風俗習慣、人間模様をシニカルに丁寧に、徹底的に細部にこだわりながら一人称で綴った小説で、細部にこだわることが好きな読者にとっては金脈を掘りあてたみたいにすばらしい本だ。可笑しみに溢れている。
ミルドレッドの語り口は穏やかで軽く、深刻ぶったところはないのだが、そのようにして語られる彼女の言葉はときに辛辣で、語り口が穏やかなぶん、余計にこわくておもしろい。「もちろん口には出しませんでしたが、どうせ私のような女は、人生にほとんど、いえ、なんの期待もしていないのです」と語ったり、クリスティーナ・ロセッティの詩の一節、「最愛の人よ、私が死んだら……」にふれて、「でも、ひょっとしたら、たいていは最愛の人などいないのかもしれません。あんがい人間なんてそんなものじゃないのでしょうか?」と語ったりする。案外大胆なのだ、ミルドレッドの言うことは。
読んでいて、笑ってしまうところがたくさんある。一例は名前で、どういうわけか、彼女にとってはファーストネームが非常に大事な意味を持つらしい。階下に越してきたネイピア夫人から、夫の名がロッキンガムだと聞かされたときのミルドレッドの反応は、「ロッキンガム! 私の耳はその名に飛びつきました――まるでゴミ箱の中に宝石を見つけたときのように。ネイピア氏のファーストネームがロッキンガムだなんて。そんな名前の持ち主なら、共同バスルームを嫌がるのは目に見えています」というもので、そうなの?と、ちょっと驚く。エヴァラード・ボーンという男性のことは、「名前といい、あのとがった鼻といい」気に入らないのだし、そうかと思えば、最初からあまり好感の持てなかったネイピア夫人のファーストネームがヘレナだと知ると、「こんな古典的な名前の方だったら、ひょっとすると私もうまくお付き合いできる」かもしれないと考えたりする。結構変っている。
食生活も興味深い。「善良で俗っぽさのない人にありがちなことですが、ジュリアンもウィニフレッドも食べ物には無頓着でしたから、彼らの家で食事を楽しもうというのはほとんど無理な注文です」と友人について率直に語る彼女はなかなかの美食家で、でも慎み深いので、一人のときの食事は「手軽で簡単なべークト・ビーンズの缶詰」だったり、「外国産の卵を一つゆでて昼食にし」たりする。「土曜の夜にひとりでとても小さな肉を食べるのも、さして悪くない」。
バーバラ・ピムの邦訳小説は『秋の四重奏』に次いで、これが二作目。刊行が一年前なので新刊レビューにしては遅いと叱られるかもしれないが、もっと知られて読まれてほしいので、書いた(ALLREVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2011年)。
ALL REVIEWSをフォローする