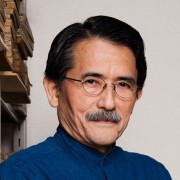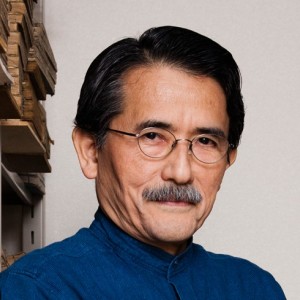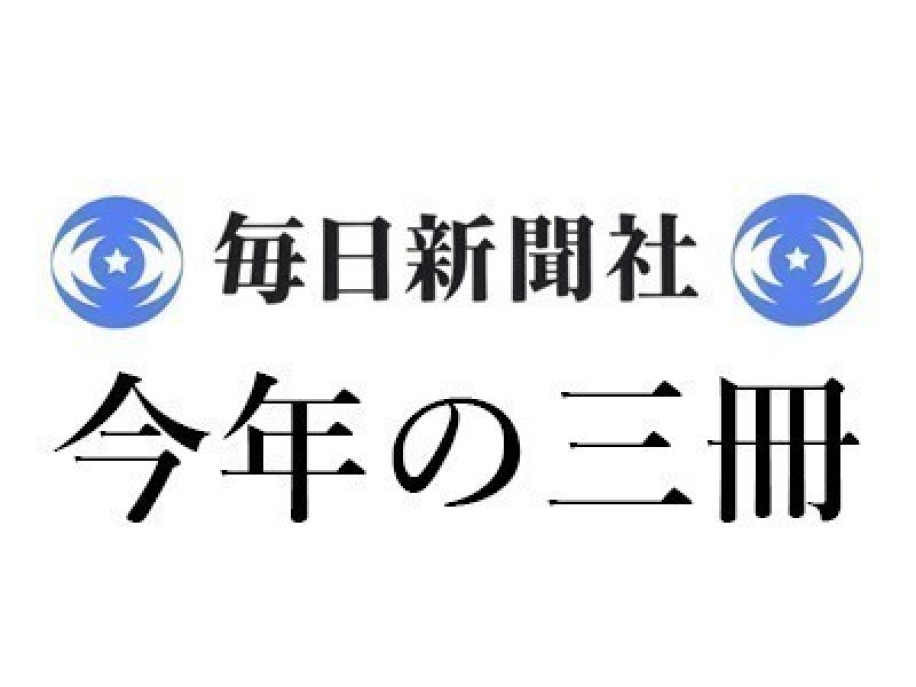書評
『作家の臨終・墓碑事典』(東京堂出版)
作家の臨終・墓碑事典
なべて不定(ふじょう)なる現(うつ)し世に誰も死ぬということだけは必定だが、それがいつどのような形で訪れてくるかということはまた絶対の不定である。人がどのように死んだかということは、彼がどのように生きたかということと一如であって、その死に方はよくその人の生き方を物語る。そういう意味で、死は厳粛である。
本書の著者は自宅付近の染井霊園を散策するうちに墓標とその背後の生に興味もって、一種の掃苔録として「文学者の一人ひとりの死因・最後の言葉・近親者の回想などを簡素にまとめた点鬼簿である」という。まさにこの通りの本なのであるが、しかし、題名こそ「事典」と謳っているものの、実は好個の読み物として推賞するに足る掌伝集である。
たとえば、わが愛する独文学者・随筆家・小説家、内田百間は、昭和四十六年四月二十日、八十二歳にして自宅で老衰死する寸前に「何があっても取り乱しちゃいけないよ」と語り、ストローでシャンパンを飲みながら死去したという。
ああ、これほど見事なる往生があるであろうか。その死に際の見事さは、とりもなおさずこの人の生き方の脱俗的風韻をよく物語っている。
また日本浪漫主義文学の旗手泉鏡花は、昭和十四年九月七日、六十七歳を一期に肺腫瘍で死ぬ間際、夫人に「ありがとう」と言い、枕元の手帳に「露草や赤のまんまもなつかしき」の句を残して逝った。これまた文学者らしい見事な死である。
こういう死の実相をあれやこれやと見ていると、つくづく人間というものは愛すべきものだと思われる。そうしていつか来るその日のためにも、かかる書を座右にして然るべく心がけをしておきたいものである。
初出メディア
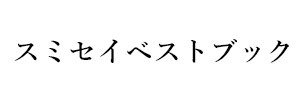
スミセイベストブック 2007年7月号
ALL REVIEWSをフォローする