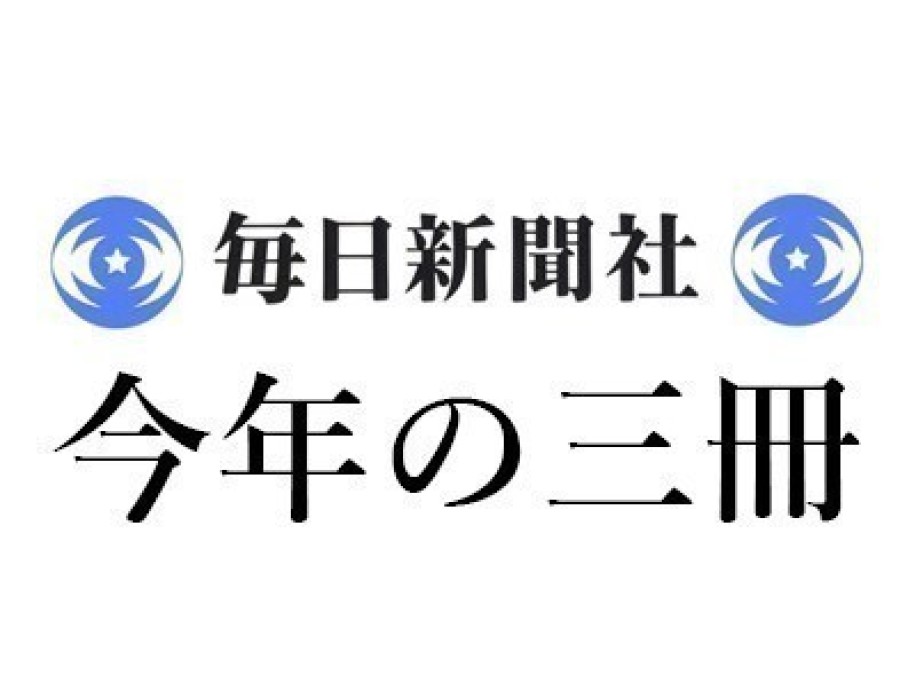書評
『役にたたない日々』(朝日新聞出版)
強烈なもの、唯一無二のもの
タイトルに「日々」とあるとおり、これは日記のかたちで書かれたエッセイ集で、二〇〇三年の秋から二〇〇八年の冬までの、著者の暮しと思うところが綴(つづ)られている。ここには、だから最初六五歳で、やがて七〇歳になんなんとする、一人の女の人がいてその日常がある。彼女は「絶品」のレバーペーストを作ったり、「鍋に昆布をしいてその上にさんまを並べ、にんにく一個分全部むいて、入れ、しょうゆと酒を同量入れて弱火で煮た」りする(他にもいろんな料理がでてくる)。テレビを観(み)たり買物に行ったり、友達に電話したりする。自分が呆(ぼ)けてしまったのではないかと不安になって、「老人病院」に行く。ほんとうに呆けてしまったお母さんに、会いにも行く。昔のことをたくさん思いだす。かと思えば韓流ドラマにはまって韓国に行ったりもする。ときどき友達を訪ねたり、友達が訪ねてきたりする。「子孫」に買ってもらった真っ赤な携帯電話でメールを打つこともするし、年若い女友達と抱擁し、その子の「でっかいオッパイ」に感じ入ったりもする。そうするうちに季節は移り、日々は流れる。
語り口は率直で大胆、木綿豆腐のようにざらりとした滋味がある。私はこの人の文章を読むたびに、人間の上等さということを考える。品のある人にしか書けない文章というものがあるのだ。本質的な、性質の美しさのようなもの。
ところで、この本はおそろしく壮絶な本でもある。綴られている日々のなかで著者がガンになり、余命を医者から聞いて具体的に知る、ということとそれは無関係ではないけれど、必ずしもそれでというわけではなくて、たぶんただ、必然的に壮絶な本なのだ。
ここにある壮絶さというのは、著者の身に起きたことのそれではなくて、著者の目に映る世界のそれである。人間一人一人の色あざやかさ。人生一つ一つの、と言いかえてもいい。おもしろさ、おそろしさ、悲しさ、不可解さ、苦しさ、滑稽(こっけい)さ、やるせなさ、何でもいいのだ。ともかくおそろしく強烈なもの、唯一無二のもの。
世の中を見る著者の視線がそもそもあまりにも率直で、そこにぶれがないために、たとえば冒頭近くにでてくるよその女たち――ある朝コーヒー屋で見かけただけの、名も知らぬ他人たち――でさえ、鮮烈な存在感を放ってしまう。「朝めしバアさん達」として一度だけ描写されるその女たちは、それぞれ一人で、セルフサービスのコーヒー屋で朝食をとっている。おもいおもいの服装で、「誰も人と話をしないで」坐(すわ)っている彼女たち一人ずつに、どんな事情と人生があるのか知りたくなった。無論知りようはないのだが、もしこの世の誰も知らなくても、間違いなく、事情も人生もあるのだ。そのことの壮絶さ。
通りすがりの人たちでさえそうなのだ。日記のあちこちに登場する、著者の記憶のなかの家族や、周囲の人々――ユユ子とかササ子とか、ミミ子とかノノ子とかぺぺオとか、ふしぎな名前を与えられた友人知人の一人一人――の、生気の放ち様にはびっくりする。おもしろくて、でも打ちのめされる。人々というのは、なんて強烈なものなのだろう。
そして、日々は地味にたんたんと続いていく。不機嫌な文房具屋がいたり、失礼な水道局員がいたり、「大工とつるんで自分のベッドを作った」おばあさん(くわしくは本文参照のこと)がいたりする、奇妙で鮮やかな世の中で。
ALL REVIEWSをフォローする