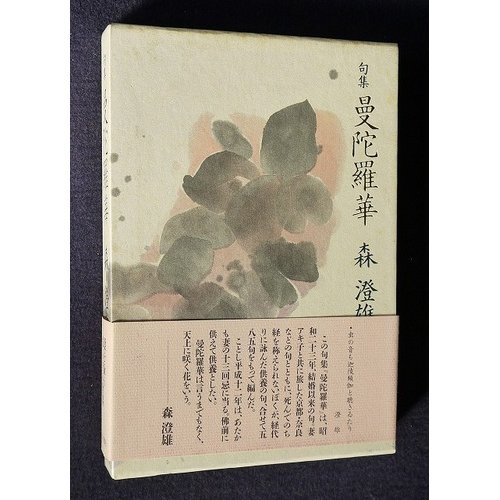解説
『或る女』(中央公論社)
『或る女』はいつまで経っても今日性を失わない作品である。その秘密はどこにあるのか、何が原因なのか。
この作品をモデル小説、あるいは私小説のように読んで、その巧拙、前篇と後篇との優劣を論じるような批評があった。たしかに、主人公(葉子)には作者が認めているように国木田独歩の恋人であった佐々城信子という実在のモデルがいた。彼女は婚約者森広(作中では木村)と暮すためにシアトルへ出発する。しかしその船の事務長(郵船会社の倉地)に魅かれ、目的地についても下船せず、そのまま彼と一緒に日本に帰ってきてしまう。この事件はやがて報知新聞に「鎌倉丸の艶聞」として報道される。有島武郎はこのことを知り、作家として興味を抱いた。醜聞に登場する幾人かの人物は彼が知っていたのである。
この作品は、最初『或る女のグリンプス』という題名で、明治四十四年(一九一一年)一月から大正二年(一九一四年)の三月まで同人雑誌「白樺」に掲載された。それから数年経った大正八年(一九一九年)、有島武郎四十一歳の年に大幅に改稿され、三月に前篇が、その数カ月後に後篇が、一気に書きあげられている。
この数年のあいだに、有島武郎のなかに決定的な「何か」が起り、他に類例を見ない一人の作家が誕生したのである。
彼は明治以後の近代文学の歴史の流れのなかにそのまま組入れることのできない、モダンな性格と深い思想性を持っていた。本多秋五は彼について、
「私は彼の文学を本当に理解したと思ったことがない」
と告白し、最も深く有島武郎を研究したと言ってもいい安川定男も、
「有島は大変わかりにくい人」
と述懐するのである。これらの言葉は『或る女』についてだけ言われたのではなく、作家全体についての言葉なのだけれども。しかし、このような評価は、彼の文章が晦渋だとか、作品が難解だとかいうことを少しも意味しない。『或る女』にしてもそうだが、他の作品にしても、たとえばマキシム・ゴオリキイの翻訳ではないかと言われた最初の小説『かんかん虫』にしても、最晩年の『惜みなく愛は奪う』にしても、つまり一貫して彼の作品はきわめて平明であり、作者が作中人物に与えた思想と性格はむしろ単純であり、文章にも澱みはないのである。
では、読者には分りやすい作品が、なぜ専門家にはむずかしい、と感じられるのか。作家有島武郎の秘密はこうした、一見不思議な矛盾のなかに隠されているのではないか。言いかえれば彼の文学は、専門家が近代文学を解説する場合に使う思考枠や分析手法を受付けないような性格を持っているのではないか。
通常、専門家は作品をまずリアリズムかロマンチシズムか、自然主義的か理想主義的か、日本的抒情性かヨーロッパ的明晰さか……という具合に分類し、その分類に従ってそれぞれの測定器で完成度を点検し、またそのなかから作者の個性を抽出してくるような手法を採用している。あるいは、ひとつの価値基準を設け、その基準を、作家がいかにリアリティを失わずに表現し得ているかを考察する。この際、描かれる対象は確固として揺ぎない実在性のなかに在ることが前提とされている。
だが、有島武郎の文学はそのような手法を受付けないようなところがある。彼は志賀直哉、武者小路実篤、里見弴、長与善郎らと共に「白樺」の同人であった。仲間には詩人の千家元麿や画家の岸田劉生もいた。彼等は反自然主義を標榜していても耽美主義、浪漫主義というよりは倫理的で理想主義的な作風に特徴があったと言っていいだろう。そうしてその倫理の基礎は個我の主張であった。彼等の多くが当時は主に華族階級の子弟が入学していた学習院の出身であり、あるいはその周辺にいた貴族の家に生れた者だったところから、現実離れした理想主義とか坊ちゃん的ヒューマニズムなどと揶揄されもしたのであった。しかし、有島の場合はその「白樺」に属しながら、彼等の誰とも異質な面を持っていた。作家としての出発をする前に、四年間アメリカに留学し、ヨーロッパを歴訪し、帰国後、札幌郊外の農場経営に携わっていた彼は、同人達のように自我の立場からのみ眺めた社会を無条件に肯定することができなかった。同じ理由から、自らの主張を貫くために他を傷つけても止むを得ないとする楽天主義を心の砦にすることができなかった。そこには、有島の個性も絡んでいたのであったが、彼の人道主義は相手への共感を基礎としていて、優越者の同情や憐みよりは人々との共生を求める志向が強かったのである。
有島武郎の生き方を評して、父親(横浜税関長から大蔵省の幹部エリートへと出世の道を歩み、最後に大臣と衝突して退官している)との葛藤がなく、その指示に従って農場経営者になったことを彼のひよわさと見る意見が強い。また、志賀直哉や武者小路のように「家」の問題と格闘しなかったところに彼の背骨の弱さを指摘する意見も多い。だが、これらの意見は今日から見ると、前近代的家父長制と成長する個我との相克に近代文学の骨格を見るという物差しを強引に有島武郎の文学にあてはめようとしている議論のように思えるのである。こうした分析手法では有島の独自性を捉えることはできないのではないか。
(次ページに続く)
この作品をモデル小説、あるいは私小説のように読んで、その巧拙、前篇と後篇との優劣を論じるような批評があった。たしかに、主人公(葉子)には作者が認めているように国木田独歩の恋人であった佐々城信子という実在のモデルがいた。彼女は婚約者森広(作中では木村)と暮すためにシアトルへ出発する。しかしその船の事務長(郵船会社の倉地)に魅かれ、目的地についても下船せず、そのまま彼と一緒に日本に帰ってきてしまう。この事件はやがて報知新聞に「鎌倉丸の艶聞」として報道される。有島武郎はこのことを知り、作家として興味を抱いた。醜聞に登場する幾人かの人物は彼が知っていたのである。
この作品は、最初『或る女のグリンプス』という題名で、明治四十四年(一九一一年)一月から大正二年(一九一四年)の三月まで同人雑誌「白樺」に掲載された。それから数年経った大正八年(一九一九年)、有島武郎四十一歳の年に大幅に改稿され、三月に前篇が、その数カ月後に後篇が、一気に書きあげられている。
この数年のあいだに、有島武郎のなかに決定的な「何か」が起り、他に類例を見ない一人の作家が誕生したのである。
彼は明治以後の近代文学の歴史の流れのなかにそのまま組入れることのできない、モダンな性格と深い思想性を持っていた。本多秋五は彼について、
「私は彼の文学を本当に理解したと思ったことがない」
と告白し、最も深く有島武郎を研究したと言ってもいい安川定男も、
「有島は大変わかりにくい人」
と述懐するのである。これらの言葉は『或る女』についてだけ言われたのではなく、作家全体についての言葉なのだけれども。しかし、このような評価は、彼の文章が晦渋だとか、作品が難解だとかいうことを少しも意味しない。『或る女』にしてもそうだが、他の作品にしても、たとえばマキシム・ゴオリキイの翻訳ではないかと言われた最初の小説『かんかん虫』にしても、最晩年の『惜みなく愛は奪う』にしても、つまり一貫して彼の作品はきわめて平明であり、作者が作中人物に与えた思想と性格はむしろ単純であり、文章にも澱みはないのである。
では、読者には分りやすい作品が、なぜ専門家にはむずかしい、と感じられるのか。作家有島武郎の秘密はこうした、一見不思議な矛盾のなかに隠されているのではないか。言いかえれば彼の文学は、専門家が近代文学を解説する場合に使う思考枠や分析手法を受付けないような性格を持っているのではないか。
通常、専門家は作品をまずリアリズムかロマンチシズムか、自然主義的か理想主義的か、日本的抒情性かヨーロッパ的明晰さか……という具合に分類し、その分類に従ってそれぞれの測定器で完成度を点検し、またそのなかから作者の個性を抽出してくるような手法を採用している。あるいは、ひとつの価値基準を設け、その基準を、作家がいかにリアリティを失わずに表現し得ているかを考察する。この際、描かれる対象は確固として揺ぎない実在性のなかに在ることが前提とされている。
だが、有島武郎の文学はそのような手法を受付けないようなところがある。彼は志賀直哉、武者小路実篤、里見弴、長与善郎らと共に「白樺」の同人であった。仲間には詩人の千家元麿や画家の岸田劉生もいた。彼等は反自然主義を標榜していても耽美主義、浪漫主義というよりは倫理的で理想主義的な作風に特徴があったと言っていいだろう。そうしてその倫理の基礎は個我の主張であった。彼等の多くが当時は主に華族階級の子弟が入学していた学習院の出身であり、あるいはその周辺にいた貴族の家に生れた者だったところから、現実離れした理想主義とか坊ちゃん的ヒューマニズムなどと揶揄されもしたのであった。しかし、有島の場合はその「白樺」に属しながら、彼等の誰とも異質な面を持っていた。作家としての出発をする前に、四年間アメリカに留学し、ヨーロッパを歴訪し、帰国後、札幌郊外の農場経営に携わっていた彼は、同人達のように自我の立場からのみ眺めた社会を無条件に肯定することができなかった。同じ理由から、自らの主張を貫くために他を傷つけても止むを得ないとする楽天主義を心の砦にすることができなかった。そこには、有島の個性も絡んでいたのであったが、彼の人道主義は相手への共感を基礎としていて、優越者の同情や憐みよりは人々との共生を求める志向が強かったのである。
有島武郎の生き方を評して、父親(横浜税関長から大蔵省の幹部エリートへと出世の道を歩み、最後に大臣と衝突して退官している)との葛藤がなく、その指示に従って農場経営者になったことを彼のひよわさと見る意見が強い。また、志賀直哉や武者小路のように「家」の問題と格闘しなかったところに彼の背骨の弱さを指摘する意見も多い。だが、これらの意見は今日から見ると、前近代的家父長制と成長する個我との相克に近代文学の骨格を見るという物差しを強引に有島武郎の文学にあてはめようとしている議論のように思えるのである。こうした分析手法では有島の独自性を捉えることはできないのではないか。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする