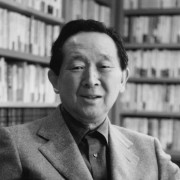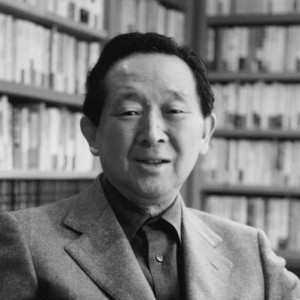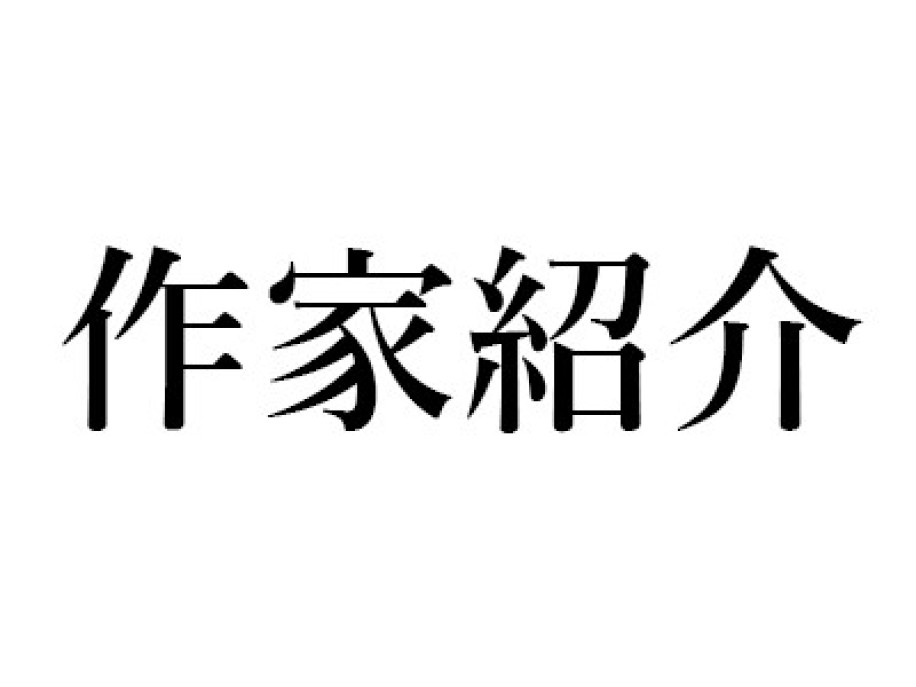解説
『或る女』(中央公論社)
有島にとっての父親とは、日本的自然主義文学が、個我を抑圧する権力として現れる家父長制を舞台とした際の父親ではなかったのではないか。
また、多くの評論家が、社会の進歩への願いをこめて、作品の価値基準をそこに置いたような、近代へと一歩進む営為としての文学行為の標的となったような旧価値の墨守者としての父親でもなかったのではないか。当時の官は権力の象徴ではあっても同時に〝進歩〟の推進者としての性格を残していたのである。有島武郎にとっての父親は家族制度の長としての父親であると同時に知的権威、あるいは進歩へ向っての社会的規範の体現者としての父親でもあったように思われる。それだけに、有島武郎はいじけざるを得なかったという観察もできるのだが、彼は農場経営について、
「我あえて大材を以て任ぜずといえども願わくはもって農業革新の魁(さきがけ)とならん」
と、日記に農場経営者としての主体的決意を述べているのである。
従来の有島武郎論はなぜか彼のこの主体性を持った意思表示を避けて通り、父親に言われていやいや札幌に連れてゆかれたと観察するのである。そうした評論には、アメリカで素朴な社会主義に触れ、キリスト教から離れるというような経過もあって、挫折し、本来の気弱が昂じていたという状況が一面的に受取られていた趣が看取できる。このような一面的理解は、明治維新の革命としての不徹底、そこからもたらされた古いものの残存、半封建制の状況、それと闘う進歩主義、その主義を支える自我の自覚、その前に立ちはだかる国家権力という思考の系譜学にとって必要な〝誤解〟であった。
たしかに、有島は帰国後迷い、父親の反対にあって新渡戸稲造の姪の河野信子との結婚を諦めてしまう。彼は「癒すべからざる深き疵を受けた」と告白する。それ以後、結婚を巡って、職業の選択について、幾度もの迷いや不安、懊悩の状態を記してもいる。しかしこれらは青春の悩みと言えるものなのではないか。そこには、若者らしい純粋の追求と並んで甘えが見え隠れしているのである。
この近代文学理解の系譜で見るかぎり、時代変化のなかで多くの明治、大正、昭和の作品が色褪せてしまったのに『或る女』が主題の今日性、登場人物の現代性で魅力ある作品として在り続けていることの理由を把握することはできないであろう。
家父長制との対決と挫折はこのような誤解の上に成立しているのだが、一方、彼の性格的な不安定性、すなわち自分と他者とのあいだに恒常的な距離を保つことの不得手な、長所であると同時に大きな弱点を指摘しておく必要もあるだろう。それはキリスト教を巡る彼の彷徨によく現れている。
有島武郎を信仰へと導いたのは森本厚吉という札幌農学校時代の友人であった。二人の友情はほとんど愛人に近い関係になり、有島は森本を救うためには自分が死ななければならないのではないかという妙な考えに取憑かれる。これは青春の悩みだとしても異常と言えるが、この入信をめぐる挿話のなかには、有島の自我の独自性が現れている。それは、自己中心の個の主張であるよりは、相手の主張を認め、それを自らの生き方に取入れ、共生(シンビオズム)を考えるという、共感を基礎におく対他認識なのである。と同時に、こうした態度と密接に関連するが、彼にとっての思想の位置も、我が国の小説家としては極めて脱日本的な独自の性格を持っていたと言うことができる。
彼は思想を自らの生活の外に置いた上での、知識や世界認識の方法論とは考えなかった。彼にとっての思想とは生き方そのものであった。かといって、その思想は実感とか諦観と呼ばれるようなものであってはならないと考えていた。そこに当為(ゾルレン)が入ってくる。
その結果、有島にとっての思想とは実生活とのあいだに緊張した関係を持つ、自らの在るべき姿となった。いささかもたてまえであってはならなかった。
このように考えてくると、『或る女』の主人公の葉子の生き方は、有島の一面を見事に体現していることが分る。通常の感情移入ではなく、思想をも含めた生き方そのものの移入なのであった。この点でも彼は、田山花袋、岩野泡鳴、徳田秋声と連なる、そして正宗白鳥、近松秋江と続いて昭和文学に至る、一本の道筋としては秀れている日本的自然主義の文学とも、白樺派流の理想主義の人々とも異質な幻視の人とも呼ぶべき作家であった。
彼が自らの所有権を放棄し、農場を小作人達へ解放し、経営から手を引くのは大正十一年(一九二二年)、最晩年の四十四歳の時であった。『或る女』を四十一歳で出版し、四十五歳に他界したことを考えれば、文学者としてのほとんどの期間、彼は農場経営者であったことになる。このことも、今までの近代文学史家からすれば、なるべく避けて通りたい事柄であったのかもしれない。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする