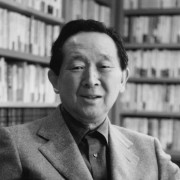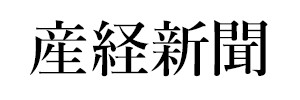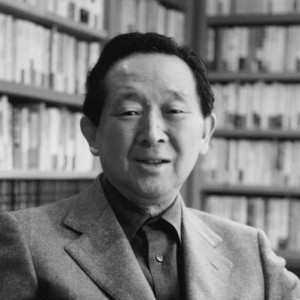書評
『人生の親戚』(新潮社)
その人の文学的資質は出発の時から動かしがたいものとしても、ひとりの作家が小説を書き続けてゆく過程には何度か転回点とも呼ぶべき作品が登場する。その契機は戦争体験であったり、家族の不幸というようなことである場合もある。勿論、大きな外的変化ばかりが回心をもたらすとは限らないけれども。
この本の著者は『個人的な体験』で新しい領域に踏み出し、『懐かしい年への手紙』で第二の転回点に到達したように思われ、今度の作品はそれに続くものとして読むことができる。その間、作者の言によれば、三島由紀夫が『個人的な体験』に寄せた批判が心にかかっていたようだ。三島由紀夫はその作品について鳥(バード)と名付けられた主人公が「われわれの近くに位する、もっとも正常で弱く『人間らしい人間』になりえているのである。が、このような人物像は、大江氏の方法論に背致してはいないだろうか」と問い、「一般人の間から絶対に理解不可能な人間、しかも鋭い局部から人間性を代表しているようなものを、言語の苦闘によって掘り出して来ることが、氏の仕事ではなかったか」と書きその作品の末尾の明るい展望の部分に特に苦言を呈したのであった。
今読めば、それは大きな才能を認めるがゆえに、通念めいたものに妥協しないでほしいという励ましを籠めた批評であったと理解することができる。そうして著者は、今この三島由紀夫によって課せられた苦い任務に応えようとしはじめているようだ。
この作品の主人公は倉木まり恵という、知的で行動的な女性である。ベティ・ブープを想起させる性的魅力をも身につけている彼女は、その美徳ゆえに災厄を呼び寄せてしまう存在として設定されている。別れた夫はアルコール依存症になり、最初の子であるムーサンは脳に障害を持っている。次男の道夫は明晰な少年であったが、トラックにはねられて車椅子で暮すようになる。この二人は無断で家を出、伊豆高原で互いに協力したようななりゆきで海に落ちる。
このように、考えられないような不幸に見舞われたまり恵が、どのようにしてこの不条理な打撃を乗り超えてゆくのか。悲劇の主題は同じ障害児を持つ「僕」の家庭との係り合いのなかで、音楽でいう対位法的な展開によって次第に生の肯定へと上昇してゆく。ここには、技法や表現の円熟というレヴェルを超えた作者の前方への踏み込みがある。自作に触れて作者は、「死の側に立ち、時には自己の死をバネにして個の生の意味を相対化してはならぬ」と語っている。秘儀や神話に限りなく接近しながらも、その都度、むしろそのような情況を跳躍台にして、生きぬいた一人の女性の物語を描くことによって、彼は二十五年前(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1989年)、三島由紀夫に与えられた課題に屈折に満ちた回答を行ったのだと思われる。
【この書評が収録されている書籍】
この本の著者は『個人的な体験』で新しい領域に踏み出し、『懐かしい年への手紙』で第二の転回点に到達したように思われ、今度の作品はそれに続くものとして読むことができる。その間、作者の言によれば、三島由紀夫が『個人的な体験』に寄せた批判が心にかかっていたようだ。三島由紀夫はその作品について鳥(バード)と名付けられた主人公が「われわれの近くに位する、もっとも正常で弱く『人間らしい人間』になりえているのである。が、このような人物像は、大江氏の方法論に背致してはいないだろうか」と問い、「一般人の間から絶対に理解不可能な人間、しかも鋭い局部から人間性を代表しているようなものを、言語の苦闘によって掘り出して来ることが、氏の仕事ではなかったか」と書きその作品の末尾の明るい展望の部分に特に苦言を呈したのであった。
今読めば、それは大きな才能を認めるがゆえに、通念めいたものに妥協しないでほしいという励ましを籠めた批評であったと理解することができる。そうして著者は、今この三島由紀夫によって課せられた苦い任務に応えようとしはじめているようだ。
この作品の主人公は倉木まり恵という、知的で行動的な女性である。ベティ・ブープを想起させる性的魅力をも身につけている彼女は、その美徳ゆえに災厄を呼び寄せてしまう存在として設定されている。別れた夫はアルコール依存症になり、最初の子であるムーサンは脳に障害を持っている。次男の道夫は明晰な少年であったが、トラックにはねられて車椅子で暮すようになる。この二人は無断で家を出、伊豆高原で互いに協力したようななりゆきで海に落ちる。
このように、考えられないような不幸に見舞われたまり恵が、どのようにしてこの不条理な打撃を乗り超えてゆくのか。悲劇の主題は同じ障害児を持つ「僕」の家庭との係り合いのなかで、音楽でいう対位法的な展開によって次第に生の肯定へと上昇してゆく。ここには、技法や表現の円熟というレヴェルを超えた作者の前方への踏み込みがある。自作に触れて作者は、「死の側に立ち、時には自己の死をバネにして個の生の意味を相対化してはならぬ」と語っている。秘儀や神話に限りなく接近しながらも、その都度、むしろそのような情況を跳躍台にして、生きぬいた一人の女性の物語を描くことによって、彼は二十五年前(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1989年)、三島由紀夫に与えられた課題に屈折に満ちた回答を行ったのだと思われる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする