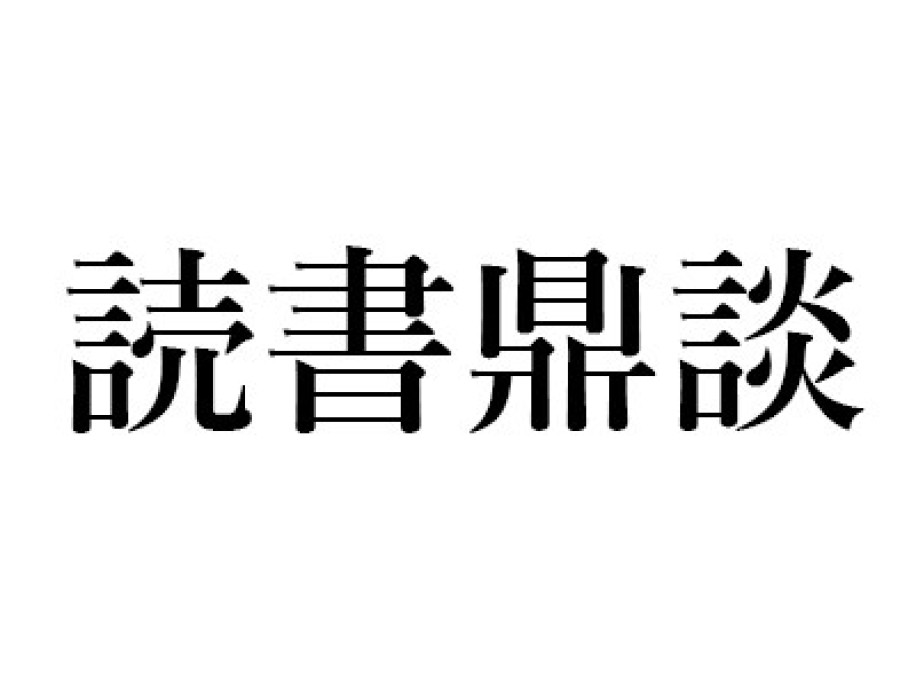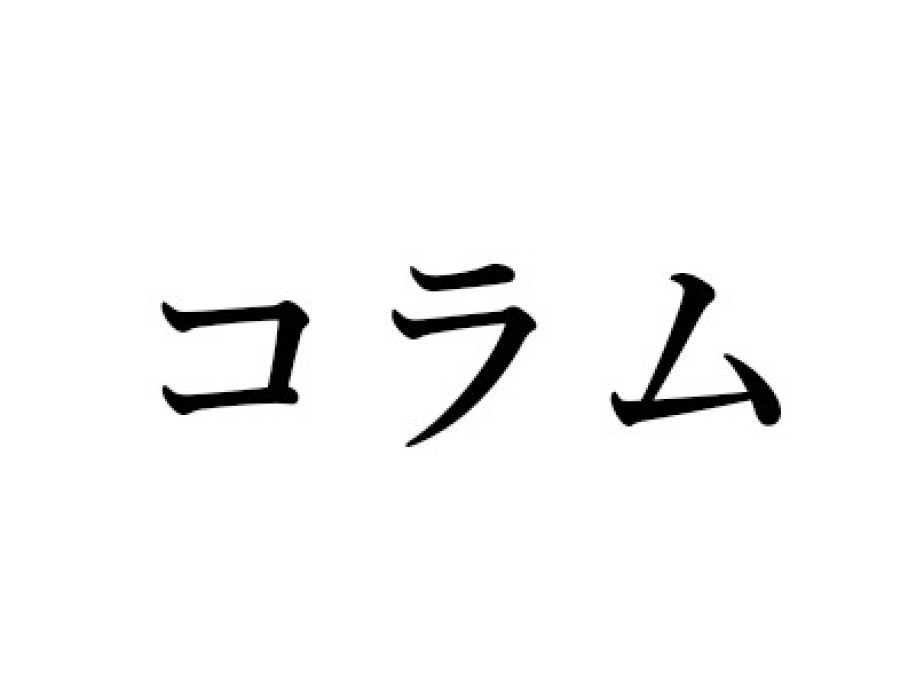解説
『親子丼の丸かじり』(文藝春秋)
東海林さだお作品(マンガもエッセーも)は長期にわたって、しかも高い水準で人気を保って来た。文春文庫だけでもこれがちょうど五十冊目だという。もはや国民的マンガ家、国民的エッセイストと言っていい。東海林さだおファンが層厚く、この国に存在しているのだ。その事実は、私には何とも頼もしくうれしいことに思える。何だかわからないけれど、「日本はだいじょぶ」「日本人はいい人だ」と思えるのだ。日本人の多くが、まだまだまともな羞恥心を持っているということじゃあないか。ショージ君やタンマ君の赤面のわけをわかるということじゃあないか。それは私に言わせれば「民度が高い」ということなのだ。偉そうな言い方になるけれど。
たとえ田中真紀子支持者のオバハンであっても、「丸かじり」シリーズの愛読者だったら、私は和気あいあいとお話しできるような気がする。たとえ未だにギョーザ靴(甲の部分にギャザーが寄っていて横にチマチマした金具飾りがついている靴)をはいて、グラデーション眼鏡(レンズの上部が茶色のボカシになっている眼鏡)をかけているオヤジでも、「丸かじり」シリーズの愛読者だったら、一メートル以内の至近距離にいてもイヤじゃあないような気がする。「丸かじり」シリーズには、何だかそういう力があるのだ。親和力。
私にとっては、そこのところも落語と同じ。超党派的にというか、いろいろな違いをすっ飛ばして、連帯感や親密感をかき立てられてしまうのだ。
もう一つ、落語と似ているなあと思うのは、反復に耐えるところだ。何度読み直しても面白い。あの章のあの一言、あの一節、あのフレーズをもう一度楽しみたいという気持にさせる。
例えば、「板ワサ大疑惑」の章における「板ワサどまり」「板ワサ上がり」というフレーズ(何気ないが「板ワサいてくれたか」というのも私は好きですね)。「名古屋エビフライ事情」の章における「噛みでがあるでよ」というフレーズ、および「で」についての考察。「民衆の敵カニクリームコロッケ」の章における「(クリームコロッケは)パセリなんかちょこっと頭にのっけて小首をかしげたりしている」というフレーズ(かわいいじゃないか?!)。「チャーシューメンの誇り」の章における「かんな感」というフレーズ、および「かきわけ感」というフレーズ……。
などと挙げて行ったらキリがない。とにかく各章必ず一つは卓抜なフレーズと出合うことができるのだ。
食べ物の擬人化のおかしさ。当然のごとく、落語の世界にもそういう擬人化テクニックがある。桂文楽の『鰻の幇間(たいこ)』で、たいこもちの一八(いっぱち)が鰻屋の料理や器にケチをつけるところが有名だが、私はここでまた志ん朝さんの『居残り佐平次』の一節を思い出してしまう。品川遊廓で無銭飲食をたくらんだ佐平次が、酒を呑んで寝て、起きてから迎い酒をして、さらにまた酒を頼む。その時の言い草が「迎いにやった酒が、ゆうべの酒と話し込んじゃった」「しようがねえなあ、すぐに帰って来いよーって言ったのに。また迎いをやらなくちゃ」――。
「丸かじり」シリーズは、話題を食べもの周辺に限定しているけれど、その根本精神は落語だと思う。「丸かじり」シリーズを読むたび、私の心はこの俗世への愛で満たされる。この世の中も捨てたもんじゃない、ばかばかしくおかしいことがたくさんある。普通の人の普通の心のおかしな動き。私自身の恥ずかしい心の動き。食べものと自分との関係。
そうだ、私もじっくり見よう。しっかり考えよう。無意識下の心のドラマをつかまえよう。
と心に誓うのだが……やっぱり根が鈍感なのかな、粗雑なのかな、一日も続かない。すぐに忘れてしまう。で、また「丸かじり」シリーズを読むことになるのだ。
やっぱり東海林さだおさんは、人間という生きものの生態観察のプロですね。ただ一点、「キンピラ族の旗手は誰だ」の章における「そういえばキムタクも顔が小さい」という指摘にだけは納得いかないものを感じたけれど、ね。
【この解説が収録されている書籍】
たとえ田中真紀子支持者のオバハンであっても、「丸かじり」シリーズの愛読者だったら、私は和気あいあいとお話しできるような気がする。たとえ未だにギョーザ靴(甲の部分にギャザーが寄っていて横にチマチマした金具飾りがついている靴)をはいて、グラデーション眼鏡(レンズの上部が茶色のボカシになっている眼鏡)をかけているオヤジでも、「丸かじり」シリーズの愛読者だったら、一メートル以内の至近距離にいてもイヤじゃあないような気がする。「丸かじり」シリーズには、何だかそういう力があるのだ。親和力。
私にとっては、そこのところも落語と同じ。超党派的にというか、いろいろな違いをすっ飛ばして、連帯感や親密感をかき立てられてしまうのだ。
もう一つ、落語と似ているなあと思うのは、反復に耐えるところだ。何度読み直しても面白い。あの章のあの一言、あの一節、あのフレーズをもう一度楽しみたいという気持にさせる。
例えば、「板ワサ大疑惑」の章における「板ワサどまり」「板ワサ上がり」というフレーズ(何気ないが「板ワサいてくれたか」というのも私は好きですね)。「名古屋エビフライ事情」の章における「噛みでがあるでよ」というフレーズ、および「で」についての考察。「民衆の敵カニクリームコロッケ」の章における「(クリームコロッケは)パセリなんかちょこっと頭にのっけて小首をかしげたりしている」というフレーズ(かわいいじゃないか?!)。「チャーシューメンの誇り」の章における「かんな感」というフレーズ、および「かきわけ感」というフレーズ……。
などと挙げて行ったらキリがない。とにかく各章必ず一つは卓抜なフレーズと出合うことができるのだ。
食べ物の擬人化のおかしさ。当然のごとく、落語の世界にもそういう擬人化テクニックがある。桂文楽の『鰻の幇間(たいこ)』で、たいこもちの一八(いっぱち)が鰻屋の料理や器にケチをつけるところが有名だが、私はここでまた志ん朝さんの『居残り佐平次』の一節を思い出してしまう。品川遊廓で無銭飲食をたくらんだ佐平次が、酒を呑んで寝て、起きてから迎い酒をして、さらにまた酒を頼む。その時の言い草が「迎いにやった酒が、ゆうべの酒と話し込んじゃった」「しようがねえなあ、すぐに帰って来いよーって言ったのに。また迎いをやらなくちゃ」――。
「丸かじり」シリーズは、話題を食べもの周辺に限定しているけれど、その根本精神は落語だと思う。「丸かじり」シリーズを読むたび、私の心はこの俗世への愛で満たされる。この世の中も捨てたもんじゃない、ばかばかしくおかしいことがたくさんある。普通の人の普通の心のおかしな動き。私自身の恥ずかしい心の動き。食べものと自分との関係。
そうだ、私もじっくり見よう。しっかり考えよう。無意識下の心のドラマをつかまえよう。
と心に誓うのだが……やっぱり根が鈍感なのかな、粗雑なのかな、一日も続かない。すぐに忘れてしまう。で、また「丸かじり」シリーズを読むことになるのだ。
やっぱり東海林さだおさんは、人間という生きものの生態観察のプロですね。ただ一点、「キンピラ族の旗手は誰だ」の章における「そういえばキムタクも顔が小さい」という指摘にだけは納得いかないものを感じたけれど、ね。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする