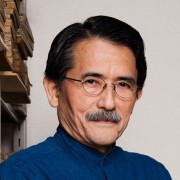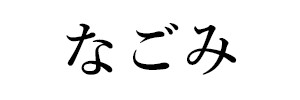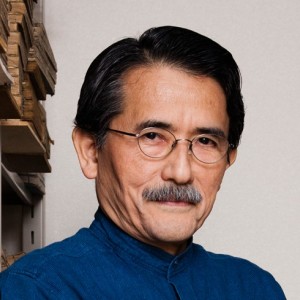書評
『妖怪草紙―くずし字入門』(柏書房)
ちょっとこんな本も
今回は少し風情の変わった本を紹介しようかと思う。もともと私は文献学者であって、古い時代の、あのくにゃくにゃした崩し字を読むことについては、れっきとしたプロなのである。で、よく床の間にかかっている掛け軸などを読んでくれと頼まれて、さっさと解読することがあるのだが、そういうとき、素人のかたがたは、どうしたらそのように崩し字を読めるようになるのかと、知りたがる。
私がこういう崩し字の文献に遭遇したのは、18歳の大学一年生の時のことだった。井原西鶴の『好色五人女』を原典の複写で読んだのである。もちろん最初はちんぷんかんぷんであった。けれども、その不思議な文字が読めてくると俄然面白くなってきたのだった。そこで私は、すらすら読めるようになるまで、毎日の通学電車の中で、ひたすら解読練習をして過ごした記憶がある。
お茶などをやっている人は、とかく床の間の掛け物などがすらすら読めたらなあと思うことがおありかと思うが、しかし、そのために私が大学生のときにやったような独学の努力をすることは、誰にもできるというものではないだろう。そういう人の為に、この『妖怪草紙』という書物は、ちょっとした福音になるかもしれない。
著者はニューヨーク生まれのアメリカ人学者だが、なぜか日本の古い文献に取りつかれて、ついにそれを専門とするようになった篤学の人である。それで、彼もまたどうやったら崩し字が読めるようになるかと、種々苦心の末、その獲得した能力を、こんどは、日本人の若い人たちの為に伝授しようというので、この珍しい本を書いたらしい。
テキストは、江戸時代の妖怪変化を素材とする絵本のたぐいで、それらの文献に出てくる崩し字を教材として、初めはやさしいものから、順次難しいものへと進んでいって、それもクイズみたいな趣向を立てながら、へへえ、面白い面白いと思っているうちに、いつしか崩し字が読めるようになっている、とそういうことが期待されているわけである。
日本人の学者でさえ、こういう崩し字の翻読についてはかならずしも正確ではなくて、けっこう間違いだらけなのだが、彼の解読はまことに正確である。
ひとつ一念発起して、こんな本で遊びつつ学んでみては如何であろう。人が知らぬうちに、独り学んで、崩し字が読めるようになれば、さりげなく掛け軸の俳句なぞを読んだりして、大いに人を驚かすことができるかもしれない。それはちょっと愉快だとは思われぬか。
とはいえ、この本の教材は、江戸時代後期の文献が多く、しかも対象となっている字は、多く平仮名で、漢字は少ない。また漢籍や和歌ものなどは、対象になっていないので、漢字の墨跡や、堂上方の草仮名ものなどは、必ずしもすぐには読めるようにもならないけれど、しかし、少なくとも大方の変体仮名に慣れるだけでも、大いなる進歩だと言わねばなるまい。
ALL REVIEWSをフォローする