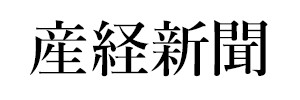書評
『じっとしている唄』(白水社)
映画についての洞察を明晰な言葉で表現する
小栗康平といえば、「泥の河」や「死の棘」で有名な映画監督。オダギリジョーが藤田嗣治を演じる新作「FOUJITA(−フジタ−)」が全国で上映中である(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2016年1月)。映画監督のエッセー集というと、何となく日々の雑感を記した文章が多いんだろうとの予断を持って読んだ。たしかにそういう短文もある。亡くなった、太田省吾や高野悦子や辻井喬への惜別の文章もある。文章の巧(うま)さが光る。でも巧いだけじゃない。
この本は慎ましい感じの第一印象とはまったく違うタイプの文章が大部分をなす。映画についての深い洞察が、短い文章の中に埋まっていて、それを見つけては、ああ、こんなところまで語ってしまっていいのか、映画の秘密についてこんなにも明晰(めいせき)に語っていいのか!と驚くことが少なくない。
たとえば「述語が主語を包摂する」という文章。日本語で「鐘の音が聞こえる」というとき、「私は聞く、鐘の音を」という西洋の、主語を中心にした理解とはまったく違った場面の把握を、私たちはしている。そのことを哲学者の西田幾多郎は「場の論理」と呼んだが、小栗はそれを「眠る男」という映画の具体的な場面に即して語るのだ。
ものや色が現実の縮尺を変えて、映像として再構成される。そうした人為の『場』に人がたたずみ、映画の中で人とものとが、あらたに出会う。(中略)そこには主語はなく、述語だけがある。
「私」という主語が突出しないこと。そこに生まれる関係性の「場」がどんなに重要か、小栗は書いている。特に、大震災の後はそうなっている、と小栗は言う。
素晴らしい説得力と具体性だと思う。こんなに深い洞察が、あの映像美には流れていたのか、と嘆息する。もう一度、小栗監督の映画をすべて見直したい気持ちにさせられる。
ALL REVIEWSをフォローする