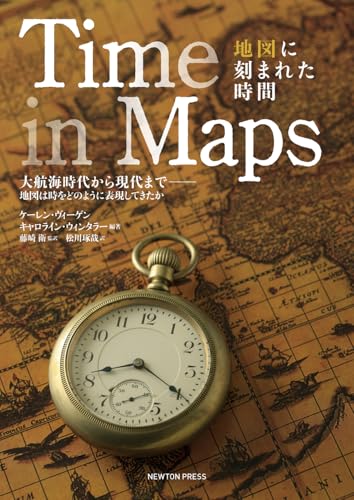書評
『時代を「写した」男 ナダール 〔1820-1910〕』(藤原書店)
一生涯大志を抱いたボヘミアン
「青年よ、大志をいだけ」と鼓舞されても、若いころは、気ままで自由なボヘミアン暮らしをしてみたいものではないだろうか。ところが、大志をいだきながらボヘミアンな生き方をすることだってできる。それも生涯にわたってだから、およそ桁外れな人間がいる。百科事典をひもとけば、ナダールという男は「19世紀フランスの写真家」で通る。じっさい、『悪の華』の詩人ボードレールや『レ・ミゼラブル』の作家ユゴーをはじめ、当代の芸術家・文化人の多くが彼のカメラの前に立っている。渡仏した二十七歳の福澤諭吉すら被写体になっている。今のように瞬時に写るわけではないから、数分間もじっとしているのは写される側にも難儀な時代だった。
しかも、この男はどこまでも貪欲だから、空にも地下にも視野を広げる。偶然にも気球に乗る機会がくると、すかさず自分の職業意識と結びついて空中写真の撮影という欲望が湧き出るのだ。野心的な試みだが、事はかんたんではなかった。何度やっても煤(すす)で覆われたような真っ黒な画像しか得られない。
失敗の連続だったが、悪戦苦闘の末、ついに報われるときがきた。パリ郊外にある小村の農家、旅籠(はたご)、憲兵隊兵舎の「三軒の特徴的な建物」がくっきり見分けられたのだ。かくして、一八五八年一○月二三日、世界で最初の空中写真が撮られた。後日、ドーミエは石版画「写真を芸術の高みまで浮上させるナダール」で称揚している。
ところで、『レ・ミゼラブル』のクライマックスの一つに、ジャン・バルジャンが負傷した仲間を背負って迷路のような下水道を逃げまどう場面がある。パリの下水道は一四世紀にさかのぼるが、徐々に整備されてきたとはいえ、排水溝の惨状はすさまじいものだった。そこは真っ暗闇の世界であったが、ナダールは人工照明を持ちこみ、悪臭のたちこめる下水道を撮影する。この果敢な挑戦のせいで、パリ住民は自分たちの足元に広がる地下の世界を目にすることができるようになった。
ふりかえってみれば、ナダールは若いころから写真家として生きていたわけではなく、一筋縄ではいかない男であった。そもそも医学校に学びながら医師の道をあきらめ、雑文を書きながら糊口(ここう)をしのぐ生活だった。三十代の半ばまでは、批評や小説を書きながら仲間たちと気ままな時間を過ごして、文字通りボヘミアン暮らしの日々だった。やがて、写真に関心をいだくようになったが、ナダールの名が世に知られるようになったのは諷刺(ふうし)画家としてであった。写真家として注目をあび名声を博したのは壮年時代になってからである。
これらの肖像写真におさまった人々のなかには、詩人や作家のみならず、画家ドラクロワ、作曲家ベルリオーズ、歴史家ミシュレ、政治家クレマンソーなどと多士済々だった。被写体となった有名人は枚挙に遑(いとま)もなく、その人脈の広さは瞠目(どうもく)すべきものがある。さらには空中にも地下にも視野を拡(ひろ)げ、人間世界の諸相を浮かび上がらせる。目まぐるしく顔を変えているのであり、まさしく時代を写した男であった。
かのロラン・バルトは「世界中でもっとも偉大な写真家は、誰だと思いますか?――ナダールです」と記している。ナダールのまなざしは昨今の歴史家が唱える社会史の核心をついており、その細部を掘り起こす評伝は一九世紀フランス社会のめざましく変容する生態を写し出す。添付された二五○点の写真とともに、狭義では歴史家ではない著者の社会史研究者もどきの力量に敬服せざるをえない。
ALL REVIEWSをフォローする