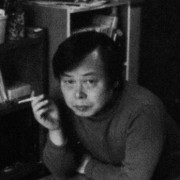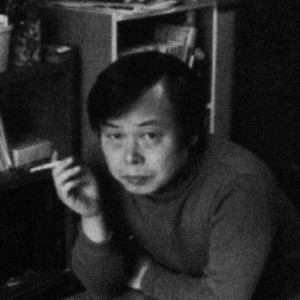書評
『江戸の釣り―水辺に開いた趣味文化』(平凡社)
へえ、釣りバカの故郷は大江戸か…
東京住まいのときは晴海埠頭(ふとう)の岸壁でダボハゼが釣れた。いま住んでいる湯河原でも、十五分もあれば海に出られて釣り糸を垂らす。気がつくと、このところ女性や子ども連れの釣り客がおやというほどふえている。釣りブームなのかな(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2003年)。さて、これほど庶民に人気の釣りが十七世紀後半の江戸時代にようやく始まったと聞くと意外な気がする。漁師の職業的な漁労は別として、趣味としての釣りは江戸勤番の武士たちのあいだから始まったのだそうだ。上方では仏教の殺生戒のおかげで釣り道楽はながらくご法度。一方、孔子は釣り好き。武士たちは儒教を奉じて釣りを武道の延長とこじつけ、仏教の基盤の浅い江戸にようやく趣味としての釣り文化を花咲かせた。やがて地方や町人や女性のあいだにも釣り趣味は波及し、下町には遠出をせずに釣れる釣り堀が繁昌(はんじょう)した。ただし十五年間だけ空白がある。五代将軍綱吉の生類憐みの令。これがお魚様にも累を及ぼした。密漁がバレて死罪になった釣り人もすくなくないという。
けれども綱吉の死後、前にもまして釣り道楽は栄えた。仕掛け、テグス糸、釣り針、継ぎ竿(ざお)に工夫が凝らされ、釣り具も高級化し、獲物ねらいも食用魚よりタナゴのように見た目がきれいなばかりの小魚にしぼられる。釣り道楽のデカダンス。
そんな釣り文化の江戸以降の通史を、本書は主に大名や旗本、好事家たちの遺(のこ)した『何羨録(かせんろく)』『漁人道しるべ』といった釣りの奥義書を手がかりに発掘していく。寄り道して釣りにまつわる怪談奇談、今も昔もたえることのない釣りバカの逸話も聞かせてくれる。小体(こてい)ながら要領よくまとまった釣り通史である。
不景気で小遣いが乏しい。道具に凝ればキリがないけれども、安上がりにもいける釣りにでも行くか。しかし、都市における水の表層露出度はいつしか江戸とは比較にならないほど手狭になっている。コンクリート道路を掘り返して東京を水の都に再生させ、釣り人が海辺や川岸で日がな一日のんびり過ごす日が、いつかはくるのだろうか。
朝日新聞 2003年6月29日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする