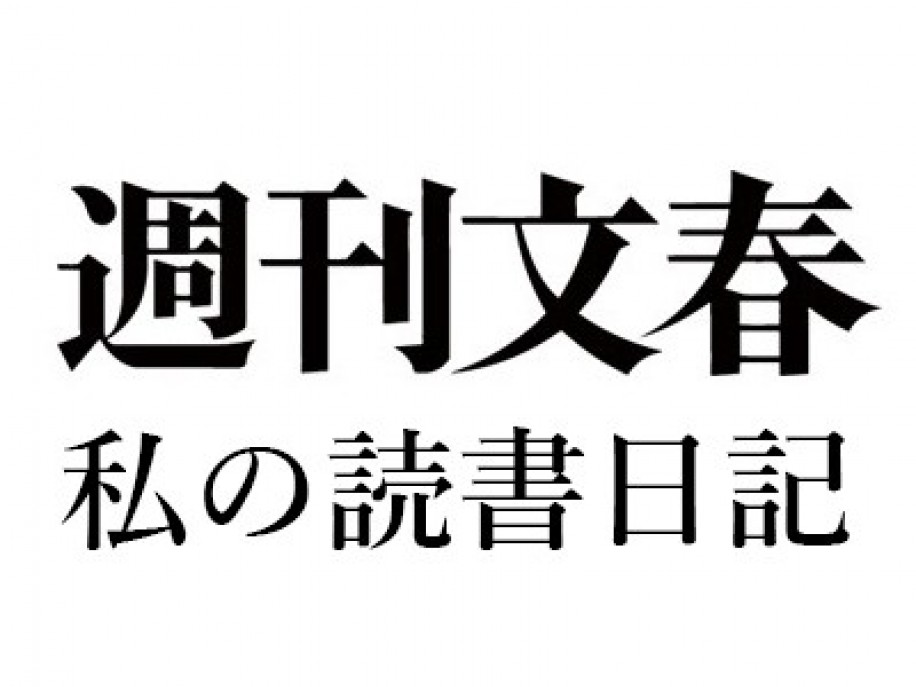書評
『ブルデュー 闘う知識人』(講談社)
日本定着に「役に立つ」本
フランスの現代思想はフーコーにしろ、デリダにしろ、ドゥルーズにしろ難解極まりないものばかりだ。社会学の巨星と呼ばれるピエール・ブルデューも例に漏れず猛烈に難解ではある。しかし、ブルデューのつくりあげたハビトゥス、界(シャン)、文化資本、象徴資本、再生産などの概念は難解でも「血と汗の結晶」という感じがするし、その著作を読んだときにはわからなかったこれらの概念が日常生活の中で突然、腑(ふ)に落ちたように理解できることが少なくない。なぜだろう? 本書はこの疑問に明快に答えてくれる好著である。
ブルデューの翻訳者・紹介者である著者は、ブルデューの出世作『遺産相続者たち』を一九六四年の刊行直後に読んだとき、「ブルデューを読めば日本が分かる、自分が分かる」という思いに駆られたと回想する。思うに、それは、「元農民の子」であるブルデューが共和国の教育原理のおかげで最高学府エコル・ノルマルで学ぶという幸運を得たにもかかわらず、敢(あ)えて一兵卒として参加したアルジェリア戦争で苛酷な現実に直面し、「いまある自分はなにゆえにいまある自分となったのか?」という根源的な疑問から社会学を志願したというそのキャリアと深く関係している。つまり、ブルデュー社会学とは、読む人を「いまある自分はなにゆえにいまある自分であるのか?」という問いかけへと誘うという意味でとても「役に立つ」学問なのである。
ブルデュー社会学を理解するためには、この『役に立つ』という言葉が決定的に重要である。(中略)[ブルデューは]人間の思考と行動は社会的に決定されているが、人々が意識していないその仕組みを客観的に明らかにすることが、社会的拘束から解き放つ働きをすると信じ、そのことを繰り返し述べている。
すなわち《必然性の認識の進歩は自由の可能性の進歩です。必然性を認識しないのは必然性を認めることにつながります〔……〕。それに対して、(中略)必然性を認識することにより選択の可能性が見えてきます》と。
実際、本書は、様々なレベルで「役に立つ」ように巧みに編集されている。
第一章では、辺境の元農民の子がコレージュ・ド・フランス教授というアカデミズムの頂点に昇りつめるまでの履歴が、フランス特有の複線型教育システムやアルジェリア戦争といった時代的・社会的背景の解説とともに辿(たど)りなおされるので、読者はブルデューという「人」とその「思想」との密接な関係を理解することができる。また、発言する知識人となったブルデューのポジションが全体的知識人サルトルや種的知識人フーコーとの対比で測定される第二章、バルト、デリダなどの同時代人との関係が多少ゴシップ的に紹介される第三章はフランスのインテリ「界」におけるブルデューの位置を掴(つか)むのに最適である。
しかし、本書の白眉(はくび)はブルデューの諸概念がかみ砕いた言葉で解説されている第五章だろう。たとえばハビトゥスの定義。
ひとはまず、生まれ育った家族環境で受ける教育をとおして社会化していく。(中略)だから、これら知覚・評価・行動の様式は知識として蓄積されるのではなく、身体化される。つまりひとはそれぞれの場面で、意識的な推論・計算にもとづいて知覚・評価・行動するのではなく、身体化されているそれら様式にしたがって、いわば無意識的に知覚・評価・行動する。
ブルデューを日本に定着させるのにこれ以上「役に立つ」本はない。
ALL REVIEWSをフォローする