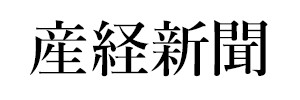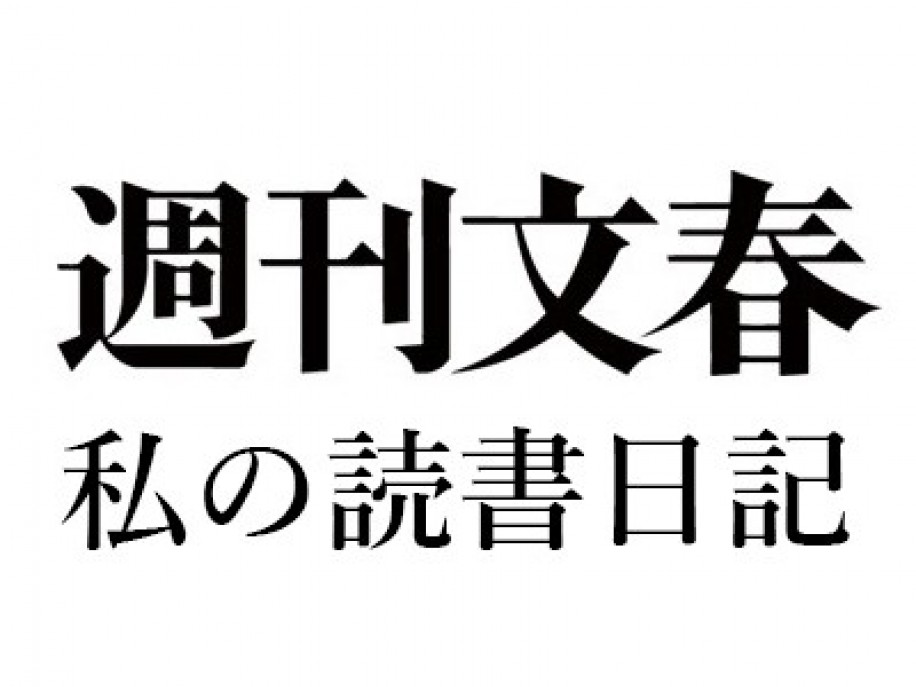書評
『ピエール・ブルデュー――1930‐2002』(藤原書店)
ピエール・ブルデューは、現代フランスを代表する社会学者。一昨年十月に一週間あまり日本に滞在、精力的にこなした一連の講演や座談の記録がこのほど出版された(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1991年)。哲学、人類学、教育学、経済学……と「超領域」的なブルデュー理論の全貌を窺い知るのに重宝な一冊である。
まず興味をひかれたのは、編者の加藤晴久氏による巻頭のインタビューである。レヴィ=ストロース、アルチュセール、フーコー、バルト、ブローデルといったそうそうたる顔ぶれの学者たちとの関わりや、社会学に賭けるブルデュー自身の思いがきわめて率直に語られている。エコール・ノルマルで哲学を学んだのち、社会学に転じ、構造主義人類学やウェーバー社会学などをへて独自の「人間学」を構想するに至った経過が、思想的な格闘の同時代史としてすっきりわれわれに伝わってくる。
たとえばブルデューのいう「ハビトゥス」概念は、どういうねらいで提案されたのか。本書を読むと、その舞台裏がわかるようだ。この概念は、主体/客体の二元論を乗り越えるためのもの。言わば、身体化された歴史なのだ。これを鍵概念として、権力、資本、場といった、ブルデュー独自の問題系が広がっていく。
収録された講演は、差別化の構造、学歴資本、文学の場、知識人の役割をテーマとする四本。巻末は今村仁司、廣松渉両氏との座談で、これも楽しめる。両氏はブルデューが、実体論から関係論へ、議論を大きく転回した点は評価できるが、その割には不徹底なところがまだ沢山残っているではないかと批判する。ブルデューは誤解だと応戦するが、みあわない印象だ。彼の仕事がどこまで本質的なのかは同じ版元から次々出版されるという翻訳をまって、見極めるべきだろう。
とまれ本書は、いま注目のブルデューがどういう場所から発言しているのか、明確に伝えてくれる。入門書としては成功だと言えよう。
【この書評が収録されている書籍】
まず興味をひかれたのは、編者の加藤晴久氏による巻頭のインタビューである。レヴィ=ストロース、アルチュセール、フーコー、バルト、ブローデルといったそうそうたる顔ぶれの学者たちとの関わりや、社会学に賭けるブルデュー自身の思いがきわめて率直に語られている。エコール・ノルマルで哲学を学んだのち、社会学に転じ、構造主義人類学やウェーバー社会学などをへて独自の「人間学」を構想するに至った経過が、思想的な格闘の同時代史としてすっきりわれわれに伝わってくる。
たとえばブルデューのいう「ハビトゥス」概念は、どういうねらいで提案されたのか。本書を読むと、その舞台裏がわかるようだ。この概念は、主体/客体の二元論を乗り越えるためのもの。言わば、身体化された歴史なのだ。これを鍵概念として、権力、資本、場といった、ブルデュー独自の問題系が広がっていく。
収録された講演は、差別化の構造、学歴資本、文学の場、知識人の役割をテーマとする四本。巻末は今村仁司、廣松渉両氏との座談で、これも楽しめる。両氏はブルデューが、実体論から関係論へ、議論を大きく転回した点は評価できるが、その割には不徹底なところがまだ沢山残っているではないかと批判する。ブルデューは誤解だと応戦するが、みあわない印象だ。彼の仕事がどこまで本質的なのかは同じ版元から次々出版されるという翻訳をまって、見極めるべきだろう。
とまれ本書は、いま注目のブルデューがどういう場所から発言しているのか、明確に伝えてくれる。入門書としては成功だと言えよう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする