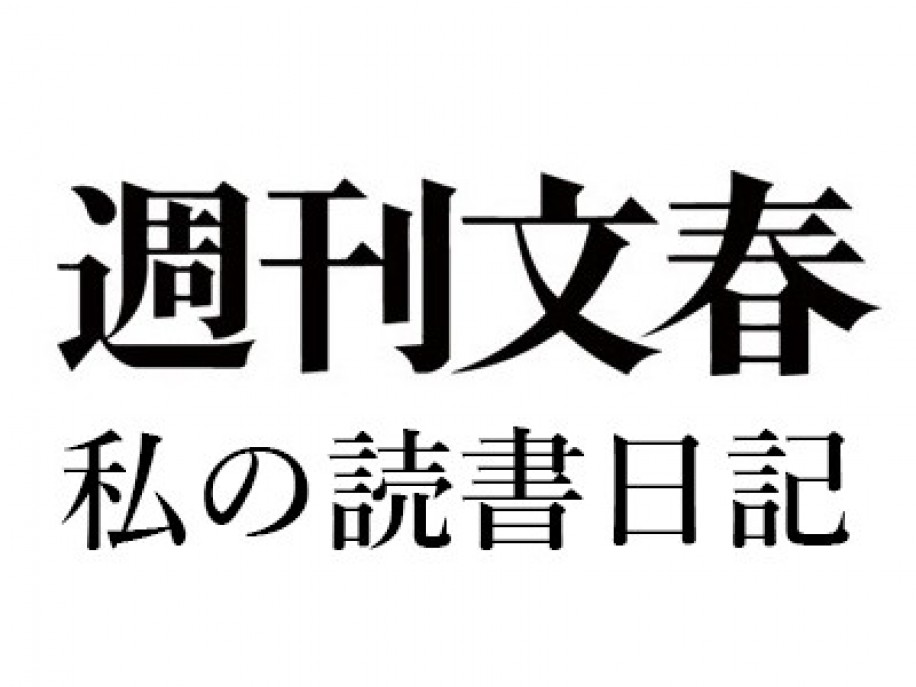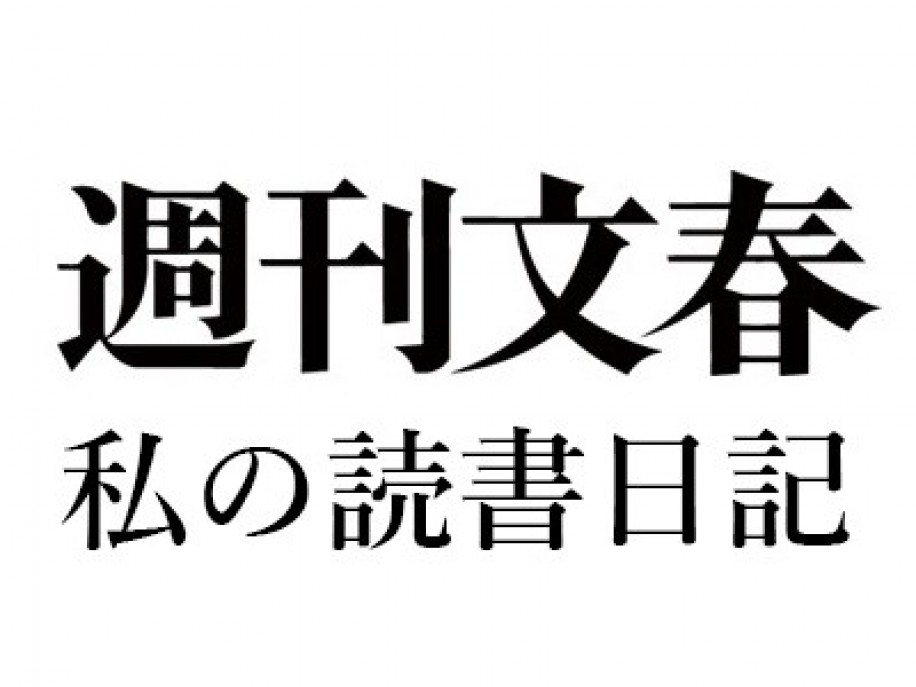書評
『万物の黎明 人類史を根本からくつがえす』(光文社)
実証実験を繰り返してきた祖先
文字記録のない先史を人類史としてとらえ直す著作が出版界で快進撃を続けている。歴史学者Y・N・ハラリ『サピエンス全史』や進化心理学者S・ピンカー『暴力の人類史』、進化生物学者J・ダイアモンド『昨日までの世界』等だ。本書も書店ではその最新作として扱われるだろうが、それら非専門家による「ポップ人類史」に対しては「子どもたちからはおもちゃをとりあげなければならない」と手厳しい。考古学や人類学が積み上げてきた調査や発見の全体を踏まえていないというのだ。
だが本来の標的はその先、これらの人類史が暗に依拠する社会科学の古典である。それらは未開社会の「自然状態」を想定し、そこから複雑な現代社会を理論化している。A・スミスの『国富論』(1776年)は、太古において物々交換が行われ、商品群から便利さゆえに貴金属が貨幣に選ばれたとしている。「商品貨幣説」はいまなお経済学の根幹を支えているが、著者の一人グレーバーは2011年の大著『負債論』において人類学の知見にもとづき、「そんなことが起こっていないことの方を膨大な量の証拠は示している」と批判した。経済学にとって痛烈な指摘である。本書では政治学の古典であるT・ホッブズの『リヴァイアサン』(1651年)とJ・J・ルソーの『人間不平等起源論』(1755年)が推定した未開社会の「自然状態」においても考古学と人類学で確認された多くの事実から否定している。
ホッブズは、国家が成立し政府や裁判所、官僚機構や警察を創設する以前、人々は孤独で貧しく辛く残忍で短い、いわゆる「万人が万人と争い合う戦争状態」にあったとした。ルソーは正反対に、農業と冶金(やきん)の勃興を機に土地の分割と私的所有、貴金属の蓄積と支配隷属関係が始まる前、豊かな実りを採集できる森で小さな集団にしか属さなかった野生人は欲望を競わず平等かつ平穏に暮らしていたとした。だが狩猟採集社会はそんな「原初」形態ではなく、「単一のパターン」も存在しなかったと本書は断言している。
1990年代にトルコで発掘されたモニュメンタルな世界最古の神殿「ギョベクリ・テペ」では、とくに1トンもある200の巨石の柱が大規模な集団の動員を想像させる。それは農耕が始まる1万年前よりも1000年も前に建造されている。そうした例から著者は、未開社会の多くは獲物の群れを追って移動し、季節によりヒエラルキーを組織しては解体していたと主張する。農耕や国家の選択が可能な状態に達しても導入せず敢(あ)えて余暇を楽しんだ、もしくは実証実験を繰り返した創造的な人々が我々の祖先だ、というのだ。重度の低身長症者を共同体で丁寧にケアし、埋葬した1万年前の例も挙げられる。
グレーバーは考古学者のウェングロウと10年間語り合って本書を完成させ、3週間余り後の2020年9月に急逝している。「ウォール街を占拠せよ」運動の煽動者は、氷河期以降の3万年を俯瞰してオルタナティブな人類史を展開、社会科学界をも根底から揺るがして、去っていった。国家が地主や株主の私的所有権の擁護に奔走する新自由主義社会だけが不動の到達点ではないことを示唆して。
ALL REVIEWSをフォローする