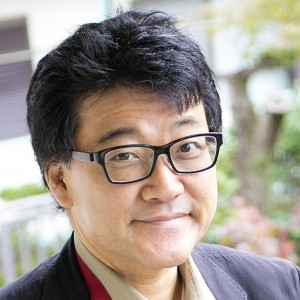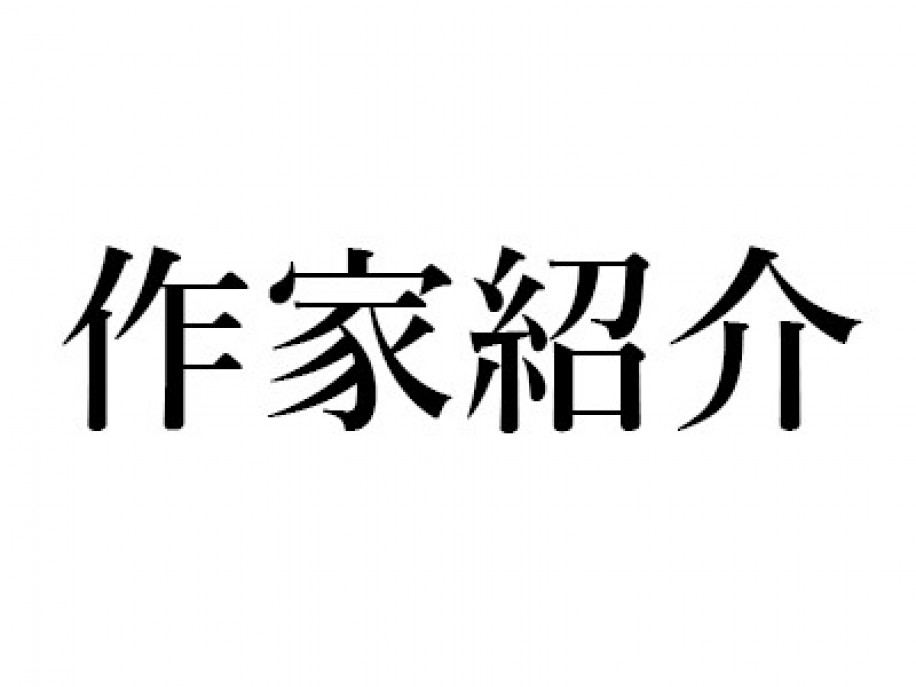書評
『世界終末戦争』(新潮社)
マリオ・バルガス=リョサ(Mario Vargas Llosa 1936- )
ペルーの作家。短篇集『ボスたち』(1959)が最初の単行本だが、その次に出した長篇『都会と犬ども』(1963)が文学賞を受賞して、一躍脚光を浴びる。そして、大作『緑の家』(1966)により、ラテンアメリカ文学を代表するひとりと目されるようになる。1990年、大統領選に出馬したが、アルベルト・フジモリに敗れる。そのほかの著作に『パンタレオン大尉と女たち』(1973)、『フリアとシナリオライター』(1977)などがある。introduction
ぼくがバルガス=リョサにはじめて接したのは、国書刊行会《ラテンアメリカ文学叢書》に収められた短篇集『小犬たち/ボスたち』だ。一九七〇年代後半に刊行がはじまったこのシリーズは、イキのいい海外文学に飢えていたぼくにとって恵みの雨だった。当時は魔術的リアリズムなんて言葉もまだ流通しておらず、ガルシア=マルケスの名を出してもプロ野球の助っ人選手とまちがえられておわりだった。さて、正直なところ、バルガス=リョサのこの短篇集はあまりおもしろく感じられなかった。そのころのぼくは超現実や奇想性をひたすら求めていたので、「なんだリアリズムか」とガックリしたのである。リアリズムと幻想性が相反するものでないことを理解するまでには、もうしばらく時間が必要だった。▼ ▼ ▼
ラテンアメリカの現代文学を語るさい、その特徴として、魔術的リアリズムと呼ばれるスタイルがしばしば取りあげられる。しかし、ぼくがいま気になっているのは、そうした表現の面よりも、血族や地縁から国家にいたるまで共同体の問題が主題化されていることだ。いや、おそらく、この表現と主題はふかいところで結びついているのだ。
魔術的リアリズムを代表する傑作といえば、なにをおいてもガルシア=マルケスの『百年の孤独』があがるだろう。一方、これから紹介するバルガス=リョサの『世界終末戦争』は、物語叙述や文章技法を基準にすれば、伝統的リアリズム文学に属する。だが、あとで述べるように、ぼくはこの作品に『百年の孤独』に匹敵するほどの幻想性を感じた。(事務局注:『百年の孤独』の牧眞司さんの書評はこちら)
『百年の孤独』は架空の村マコンドの年代記だったが、『世界終末戦争』ではブラジルに実在したカヌードスという村の運命が描かれる。実際の歴史のなかでおこった大きな騒動をもとにして、バルガス=リョサはこの小説を書いた。
一八二二年に独立国となったブラジル帝国は、一八八八年の奴隷解放をへて共和制へと移行する。この時期、新政府に対して叛旗をひるがえした一群があった。中心となったのは、放浪しながらキリスト教の教えを説いてまわっていたコンセリェイロという人物。教会はこの男を異端者として退けたが、民衆は彼を聖者とみなして追随した。コンセイリェイロ派のなかには、凶悪な犯罪者や山賊なども含まれているが、おおかたは純朴な農民たちだった。
彼らが共和制に反抗した理由は、国勢調査であり、結婚制度の法律化であった。人種や出自を調べる国勢調査は奴隷制を復活させるものであり、神による結婚の秘蹟に法律が介入するのは容認しがたい不敬行為だというのだ。そうした日常的な事情に加えて、迫りつつある世紀末への宗教的期待感もあった。コンセイリェイロが新しい教会の建立地として選んだブラジル北東部の村カヌードスでは、世界の終末がしきりに語られた。何世紀にもわたって動植物を育み、人間を保護してきたために大地は疲弊しており、やがて父なる神に休息を乞うことになるだろう。神は大地に休息を認めて、すると、破壊がはじまるだろう。聖書のなかにある「わたしは平和をもたらすために来たのではない! 火を投じ、燃えあがらせるために来たのである!」という一節は、そういう意味なのだ。
民衆にとっては風俗・常識・政治・信仰は渾然一体であり、激情につき動かされたおよそ三万人がカヌードスに立てこもる。コンセリェイロは、共和国政府こそアンチ・キリストであると人々に告げ、彼のみちびきで貨幣制度のない宗教的楽園が実現する。政府はコンセイリェイロを逮捕すべく軍隊を派遣するが、その最初の一隊は、信者たちの手であっさりと返り討ちされてしまう。やがて、旧王政派がカヌードスをあと押ししているのだ、いやイギリスがひそかに武器を援助しているのだ、などという噂が流れ、政府はすっかり浮き足だってしまう。かくして泥沼のような戦闘が約一年もつづく。最後には軍がカヌードスを制圧するのだが、信者のほとんどはその過程で殉死していた。累々と死体が残る廃墟の村に踏みこむ兵隊たちも、かなりの痛手をおっている。規律は乱れに乱れ、制服もボロボロだ。
この作品を読んでいるあいだ、ぼくの頭にずっとあったのは、大江健三郎の『同時代ゲーム』である。バルガス=リョサがブラジルのなかに潜むもうひとつのブラジル(カヌードス)を見出したように、大江も日本のなかにもうひとつの国家(四国の山村)を設定する。いずれも俗的外界とは切りはなされた、宗教的(神話的)価値観に基づくユートピアだ。そのユートピアを無化、吸収しようとする近代的国家への抵抗が描かれているところも似ている。また、『同時代ゲーム』は日本文学には珍しく、多種多様な登場人物と豊富なエピソードを抱えていて、その点も『世界終末戦争』に共通する。
にもかかわらず、両作品の手ざわりは正反対といっていいほど、異なっている。
『同時代ゲーム』は、ひとつのコスモロジーを内包している。語り手は、幼いころ森のなかで体験したヴィジョンを思いおこす。無数の空間×時間のユニットからなる〈村=国家=小宇宙〉。作品中で語られるエピソードはすべて、このめくるめくヴィジョンに結びついていく。饒舌に語られるエピソードは、多であると同時に一である。まるで、ひとつひとつの要素のなかに全体が反映されているホログラムのように。
一方、こうしたコスモロジーを喪失したところから、『世界終末戦争』は書きはじめられている。カヌードスで実現した秩序は、たかだか「貧しきものはさいわいである」という信仰にすぎない。それぞれのエピソードもカヌードスに集約されるわけではなく、登場人物どうしの関係によってさまざまに生起し、分岐していく。いくつもの物語が交差し、新しい結び目をつくったかと思えば、突如として断ちきられることもある。カヌードスに集った人間ばかりではなく、外部の者――たとえばヨーロッパからわたってきたアナーキスト、軍隊に同行する新聞記者、信者たちに土地を剥奪された男爵――の視点からも物語が語られる。それぞれの物語は、決してひとつところに収束しない。
デフォルメされた人物造形や、夢を見ているかのような叙述はあっても、バルガス=リョサの基調はあくまでリアリズムであり、超自然や非現実的な要素はない。しかし、たくさんの人物による視点の重層性、エピソードそれぞれを語る声の多彩さは、読者がふだん体験しているリアルの域を大きく超える。そうした想像力の質を、ぼくはとりあえず幻想性と呼ぶことにする。ひるがえっていえば、異世界で魔法合戦が繰りひろげられるファンタジイであっても、時間や次元を往来するサイエンス・フィクションであっても、平板な視点や語りで綴られているものは、旧弊なリアリズム小説と同程度のおもしろさしかない。リアリズム/非リアリズムという二分法を超えた地平からこそ、ほんとうに想像力を刺激する文学がはじまるのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする