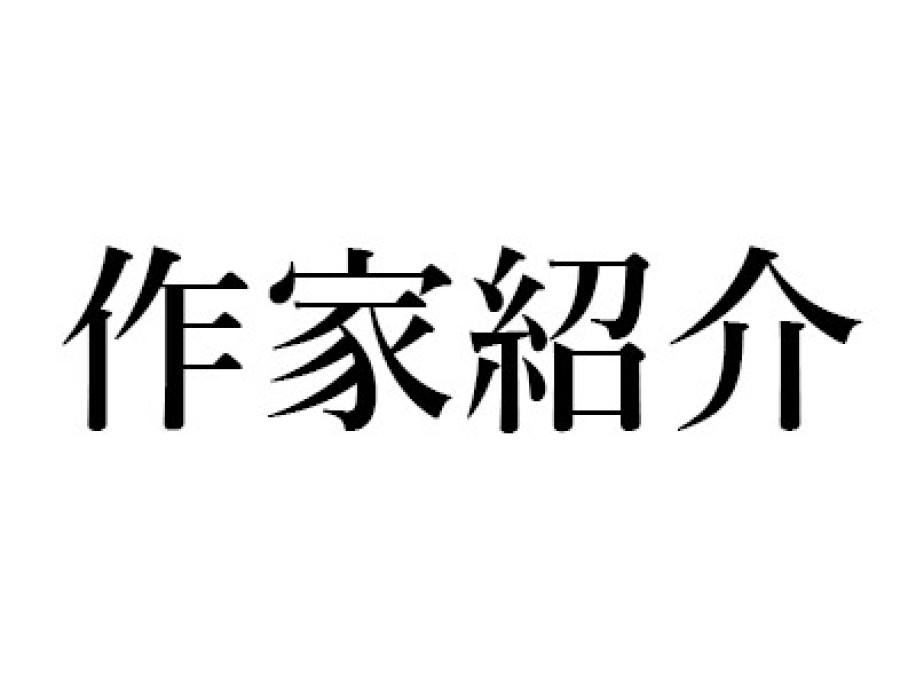書評
『継母礼讃』(中央公論新社)
偏執的な性愛描写が見事なウルトラ・リアリズム
もう二年以上前のことになるが、スペインの新聞に「バルガス=リョサの官能小説」というコピーとともに本書の広告が載った。ラテンアメリカの現実を力強いリアリズムで描き続けてきたこの作家の作品としては意外な気がしたが、考えてみればフロベールと『ボヴァリー夫人』を論じた評論『果てしなき饗宴』の中で、彼は、主観的な生よりは客観的な生の描写に、また省察よりは行動の記述に自分は惹きつけられると言い、幻想的なものよりも現実的な創作のほうが好きだが、非現実なものの中では、抽象よりも具象に近いもの、たとえばサイエンス・フィクションよりはポルノグラフィーを好むことを告白しているのである。
さらに、小説が魅力的であるためには、反抗と暴力とメロドラマとセックスが物語の中に組みこまれていることが必要だと語っている。
実際、彼の小説にとって性は欠かせない要素である。とはいえ、この要素を拡大したのはなぜか。一つには、彼の友人でスペインの映画作家ベルランガが編集する「エロチカ叢書」の一冊として書かれた作品だということがある。もう一つ、巻頭に掲げられたエピグラフが、ペルーの生んだシュルレアリスト詩人で彼のフランス語の教師でもあったセサル・モーロの作品の一節であることが注意を惹く。美こそが悪であるとうたうこの詩人は画家でもあった。
このように見てくると、本書はエロティシズムを追求したシュルレアリストたちへのオマージュであり、モーロの作品をモチーフにしていると読めてくる。
本書の面白さは、そうした事実を知れば知るほど作品の重層性が見えてくるところにある。ことに中に使われている六つの絵が、物語をふくらませるとともに神話性を与える働きをし、読者はフラ・アンジェリコからフランシス・ベーコンに至るまでの作品を物語に重ねつつ、夢と現実の間を行き来することになる。
さて、その物語だが、時代は現代、舞台となるのはペルーの首都リマにあるリゴベルトの屋敷である。リゴベルトは保険会社に勤める裕福な男で、先妻に死なれ、美しいルクレシアを後妻に迎えた。リゴベルトと先妻の間にはアルフォンソという一人息子がいた。色白で金髪、まるで天使のようなこの少年は、無邪気さの陰に悪魔の顔を隠していた。
結婚に一度失敗しているルクレシアの熟した肉体に酔い痴れるリゴべルト。彼女も夫との交わりに大いに満足していた。ところがこの二人の間に息子が割り込んでくる。継母の入浴する姿を覗き見していた彼は、さらに彼女の愛を求める。彼女もまた、罪の意識に駆られながらも、息子の求愛に応じていく。こうして、ギリシャ悲劇風の近親相姦による三角関係が出来上がる。だが(あるいは予想通り)、ついに破局が訪れる。
プロットだけで言えば、小説や映画でさんざん使われてきたものであり、少しも目新しくはないのだが、リゴベルトの偏執的な排泄行為や沐浴、夫婦の性愛の描写がさすがウルトラ・リアリズムの作家だけあって見事である。しかも絵画の効果もあって時空間がワープし、読者は一種のアナクロニー(時間の混乱)を味わうことになるだろう。
今まで述べたことからだけでも、本書が著名な作家の単なる手慰みといったレベルの作品でないことが分かるだろう。しかも、リゴベルトはかつてカトリック行動派の熱狂的信徒として世界変革をめざしたが挫折したなどという件(くだり)を読めば、バルガス=リョサの作品や人物を知っている読者ならそこに彼の目くばせを感じるに違いない。短い作品だが、とにかく様々な事物が詰まっている。
ちなみに訳書でマルセリーノ・メネンデス・ピラルとなっているスペインの学者は、マルセリーノ・メネンデス・イ・ペラヨの誤りだろう。ブニュエルの映画『銀河』に霊感を与えたこの人物のスカトロジックなエピソードを、バルガス=リョサはマドリードに留学していたころに聴きかじったのだろうか。主人公の声に時折、作者の声が混ざり合う。
初出メディア

月刊Asahi(終刊) 1990年11月号
ALL REVIEWSをフォローする