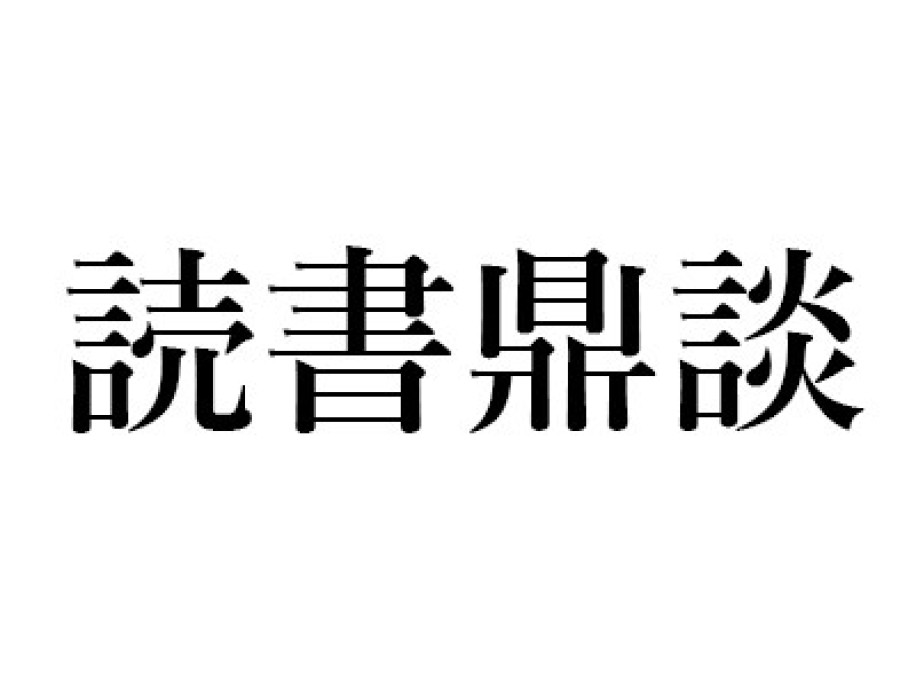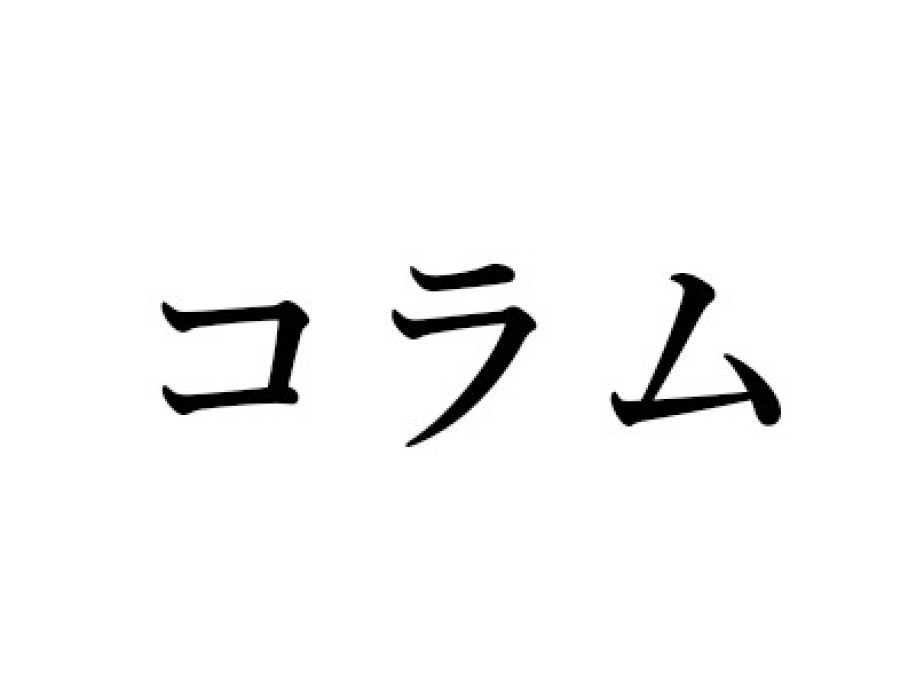解説
『親子丼の丸かじり』(文藝春秋)
東海林さだおさんのことを書きたいのだが、まず私自身の話で失礼してしまう。おまえの話なんか聞きたくないわいと思うかたも多いだろうが、だいじょぶ、すぐに済みます。ちゃんと話はつながるように持って行くから。
で、心置きなく自分のことを書くのだが……二〇〇一年は私にとって失意の年であった。十月一日に落語家の古今亭志ん朝さんが亡くなってしまったからだ。身内はともかく、こちらが一方的に知っているだけの有名人の死にあんなにショックを受けたことはない。
私はこの十数年、すっかり落語至上主義者と化していたのだが、古今亭志ん朝さんという現代落語界ではほとんど唯一最強の支柱を失ってしまい、大げさではなく、心の底がパカーッと抜け落ちたかのような気持になった。ガックリ来た。
この先、落語がどういう運命をたどるかわからないが、少なくとも私にとっての落語は終わった、自分が最も愛した芸能の滅びの瞬間に立ち合ってしまった……などと口走ってみたい気持を抑えられない。
けれど、東海林さだおさんの「丸かじり」シリーズを読むと、そんなに簡単に「落語は終わった」なんて言えないな、表現の形は違っていても落語の心はちゃんとしぶとく生き続けて行くんだな、と思える。落語を聴いた時とほぼ同質の喜びを感じることができる。
「丸かじり」シリーズを読むたび、東海林さだおさんの独得のデリカシーにホレボレさせられる。人間のせこい心の動きに関してこれほど繊細で敏感な書き手が他にいるだろうか(いや、いない)。
「丸かじり」シリーズのどこでもいいが、例えば本書の「チャーシューメンの誇り」の章。
以下、ラーメン注文男とチャーシューメン注文男の問に生じる、曰く言い難い心理的葛藤(というほどのものではないが)が活写されて行く。
(というほどのものではないが)というのが重要なのだ。気にしなければ全然気にならないような、些細で淡い心の動き。ほとんど無意識下のドラマ。そこの部分に関して東海林さだおさんは抜群の視力を持っている。ひとのチャーシューメンについ視線が走ってしまう人間の性や業や煩悩(というほどのものではないが)をけっして見逃さない。そして、それをほほえみとマンガ的な誇張をもって描き出すのだ。
志ん朝さんの「唐茄子屋政談」の一節を思い出さずにはいられない。
吉原通いで勘当になった若旦那。心を入れ替え真面目に働かなくてはというので唐茄子(カボチャ)売りになる。道ばたで転んでしまった若旦那に同情した人が、親切にも知りあいに唐茄子を売りつけてくれる。売りつけられた男は「唐茄子なんてそんな野暮なものは食えねえ」などとさんざん文句を並べていたのだが、いざ買うとなったら、少しでも大きいのをと選んでいるというくだりのおかしさ。
せこい奴と思いながら、つい、笑ってしまう。かわいくなってしまう。愛さずにはいられなくなる。
話はちょっと飛ぶようだが、私は東海林さだおマンガの主人公が頬を染める場面が好きだ。「ショージ君」にしても「タンマ君」にしても、けっこう赤面しがちな男だと思う。羞恥心が強いのだ。いや、私に言わせれば、まともな羞恥心の持ち主なのだ。
東海林さだおさんがなぜ、人間のせこい心の動きに関して抜群の視力を持っているかと言ったら、その大もとは羞恥心なんじゃあないだろうか。もしかして違うかもしれないが「差恥心だ」と決めつけて話をすすめる。
(次ページに続く)
で、心置きなく自分のことを書くのだが……二〇〇一年は私にとって失意の年であった。十月一日に落語家の古今亭志ん朝さんが亡くなってしまったからだ。身内はともかく、こちらが一方的に知っているだけの有名人の死にあんなにショックを受けたことはない。
私はこの十数年、すっかり落語至上主義者と化していたのだが、古今亭志ん朝さんという現代落語界ではほとんど唯一最強の支柱を失ってしまい、大げさではなく、心の底がパカーッと抜け落ちたかのような気持になった。ガックリ来た。
この先、落語がどういう運命をたどるかわからないが、少なくとも私にとっての落語は終わった、自分が最も愛した芸能の滅びの瞬間に立ち合ってしまった……などと口走ってみたい気持を抑えられない。
けれど、東海林さだおさんの「丸かじり」シリーズを読むと、そんなに簡単に「落語は終わった」なんて言えないな、表現の形は違っていても落語の心はちゃんとしぶとく生き続けて行くんだな、と思える。落語を聴いた時とほぼ同質の喜びを感じることができる。
「丸かじり」シリーズを読むたび、東海林さだおさんの独得のデリカシーにホレボレさせられる。人間のせこい心の動きに関してこれほど繊細で敏感な書き手が他にいるだろうか(いや、いない)。
「丸かじり」シリーズのどこでもいいが、例えば本書の「チャーシューメンの誇り」の章。
ラーメン屋のカウンターで三人の客がラーメンをすすっている。そこへもう一人の客が入ってくる。「チャーシューメン」客はゆっくりと言い放つ。一瞬、三人の手が止まる。止まりはしたものの、三人は何事もなかったように再びラーメンをすすり始める。チャーシューメンが出来上がり、客の前にトンと置かれる。そのとき、ほとんどいっせいに、三人はチャーシューメンの丼を横目でチラと見る。必ず見る。いつか必ず見る
以下、ラーメン注文男とチャーシューメン注文男の問に生じる、曰く言い難い心理的葛藤(というほどのものではないが)が活写されて行く。
(というほどのものではないが)というのが重要なのだ。気にしなければ全然気にならないような、些細で淡い心の動き。ほとんど無意識下のドラマ。そこの部分に関して東海林さだおさんは抜群の視力を持っている。ひとのチャーシューメンについ視線が走ってしまう人間の性や業や煩悩(というほどのものではないが)をけっして見逃さない。そして、それをほほえみとマンガ的な誇張をもって描き出すのだ。
志ん朝さんの「唐茄子屋政談」の一節を思い出さずにはいられない。
吉原通いで勘当になった若旦那。心を入れ替え真面目に働かなくてはというので唐茄子(カボチャ)売りになる。道ばたで転んでしまった若旦那に同情した人が、親切にも知りあいに唐茄子を売りつけてくれる。売りつけられた男は「唐茄子なんてそんな野暮なものは食えねえ」などとさんざん文句を並べていたのだが、いざ買うとなったら、少しでも大きいのをと選んでいるというくだりのおかしさ。
せこい奴と思いながら、つい、笑ってしまう。かわいくなってしまう。愛さずにはいられなくなる。
話はちょっと飛ぶようだが、私は東海林さだおマンガの主人公が頬を染める場面が好きだ。「ショージ君」にしても「タンマ君」にしても、けっこう赤面しがちな男だと思う。羞恥心が強いのだ。いや、私に言わせれば、まともな羞恥心の持ち主なのだ。
東海林さだおさんがなぜ、人間のせこい心の動きに関して抜群の視力を持っているかと言ったら、その大もとは羞恥心なんじゃあないだろうか。もしかして違うかもしれないが「差恥心だ」と決めつけて話をすすめる。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする