書評
『和数考』(白水社)
郡司正勝先生は、早稲田大学退職後、新たに四冊の書物をまとめられた。『童子考』(一九八四)、『風流の図像誌』(一九八七)、『鶴屋南北』(一九九四)、そして本書『和数考』(白水社、一九九七)である。
『風流の図像誌』と『鶴屋南北』との間に『郡司正勝刪定集』(白水社、1990-92)の刊行という大きな出来事があり、先生はそれまでのお仕事を解きほぐし組み換えて、六つの領域に再配列することに専念された。「刪定(さんてい)」という言葉を私などははじめて教えられたのだが、著作集ではなく、あえて刪定集という表現にこだわったところに先生の確固たる美意識のようなものが感じられた。「かぶき門」「傾奇(かぶき)の形」「幻容の道」「変身の唱」「戯世の文」といった、それぞれの巻のタイトルの斬新さに一驚したのは、もとより私ひとりではあるまい。
第六巻「風流の象」だけは、しかし、『童子考』と、『風流の図像誌』を「山と雲――風流の図像誌――」という題名に変更して、そっくりそのまま収め、あと関係する論考を何篇か付け加えている。ここでは「刪定」は施されていないわけである。それほどにこれらの著作の内容にまとまりがあったともいえるし、先生が愛着をもたれていたともいえるだろう。
実際、退職後の先生は、芝居の創作・演出に執筆にと驚くほど奔放な活躍をされた。年齢を感じさせないパワーだったが、このお歳でなければできないようなお仕事でもあった。『童子考』『風流の図像誌』『和数考』は、比肩するもののない日本的宇宙論(コスモロジー)の三部作となった。体系とか集大成とかいった言葉を好まれなかった先生だが、これらの著作は日本的想像力の論理をめぐる、これもお嫌いだという言葉をあえて使えば、「郡司学」のまぎれもない集大成となった。
集大成にならざるをえなかったといってもいい。先生は、今度は日本の色について書きたいとおっしゃっていた。どんなに特異な色彩論、日本文化論が登場することかと期待に胸をふくらましたが、これはついに実現を見なかった。『和数考』が、先生の遺著となった。
さて、その『和数考』である。本書は、「一の章」から「十の章」までの十章に「算術の章」が付け加わり、「あと算」で締め括るという洒落た構成になっているが、「一の章」の冒頭に、こうある。
うまい書き出しだ。数の話をしようとしながら数ではないという。思わず引き込まれる。
書き出しのうまさは、書物全体のおもしろさということにほかならないのだが、これは『童子考』や『風流の図像誌』についてもいえる。『童子考』は、こう始まる。
『風流の図像誌』の「はじめに」は、こうである。
本文の「動く山」は、こういう書き出しである。
ごく個人的な思い出、私的な感慨が、「一般的な固定観念」の転倒にさりげなく結びつけられ、読者は不意打ちにも似た驚きとともに、たちまち郡司ワールドに引き入れられてしまう。名人芸といっていい。真似してできるものではない。私的な感慨が、しかし決して私的な感慨に終わることなく、読者は気がつけば普遍的な地平に立っている。著者の書き物には、いつもそういった趣きがある。個が普遍へと突き抜けるのだ。それは記述が驚くべき該博な知識に支えられているからである。
著者はこうして「天下一」「一の人」「一夜漬」「一枚看板」「裸一貫」「一蓮托生」など、おびただしい言葉を思いつくままのように挙げながら、「一」の意味圏を探る。西洋的な数のシンボリズムとは異なる。「一」をめぐる記憶と文献のフィールドワークのごときもので、実際、そこに引かれる文献たるや、『日本書紀』『信長記』『武江年表』『小笠原礼書』『宇治拾遺物語』、果ては荷風の『断腸亭日乗』に至るまで、緻密な知的作業の前提なくしては同じ場所に集められようもないものばかりである。
だが、なんといっても記憶と文献のフィールドの中心は、かぶきであって、著者はここで皿屋敷のお菊の亡霊の皿の数え方による時代と世話のいい回しの違いに言及している。「ひとつ、ふたつ」と数えると時代(時代物)、「一枚、二枚」と数えると世話(世話物)というわけだが、この違いの根本を著者はこう推測する。
してみれば、「ひとつ」の意が「いち」を覆ったとき、「一」はたんなる数ではなくなるということになろうか。もっとも、中国十七世紀の芸術理論家、石濤(せきとう)の『画語録』に、「法は何(いずく)に於て立つや。一画に立つ。一画は、衆有の本にして、万象の根なり」とあるように、中国においても「一」は文字どおり「ものの発端」でありえた。だから厳密には、日本と中国の比較がなされなければならないだろうが、本書はあくまでも「和数」についてのエッセーであろうとする。「この世を曳きずっ」た日本の「心意伝承」が問題なのである。
「一まず一段落」という言葉で「一の章」を閉じようとした著者は、最後にこんな文章を添えている。
著者は一九九〇年に『ひとつ水』と題する句集を出している。「見捨てられた水」という意味だったのだろうか。その本を私に下さるとき、著者は表紙の裏に、句集に収められた一句、
と墨痕あざやかにしたためてくれた。この「一つ」は、たしかに数えられはするけれども、決して数の「一」ではない「ひとつ」であろう。
「星祭」とは、七月七日の七夕のことである。それで話は「七の章」に飛ぶ。
実は「七の章」だけが圧倒的に突出しているのだ。たとえば「二の章」が十二頁なのに対して、「七の章」は三十四頁に及ぶ。三倍近い量なのである。「二の章」の量の少なさは、「世に『二』ほど損な役回りはない」という書き出しで、ひたすら「二」の卑小性、矮小性、取るに足りなさを論じることに関係するかもしれない。「とかく『二』は負の数字である」とすれば、短くなるのも当然といえようか。しかし「二」が「負の数字」なら、「七」は「凶の数字」なのだ。そう著者は書き出している。
一が数ではない、山が動くというのと似た論法である。黒沢明の『七人の侍』も然り。七人の天の使いであり、同時に災いをもたらすものだという。「七福神」も「七難」に対応する。「七生報国」「七変化」「この子の七つのお祝に」……。著者は「七」をめぐる「凶」の旅に出る。ちなみに、「七」歳は不完全の完結ということの物忌みの明けであるがゆえに「お祝」になるというわけである。
すでに著者は『童子考』において、「星の影」、「土佐の星神社」、「負の七数」、「七曜剣」と、たたみかけるように「七」について語っていた。中心は「星」のテーマ、つまり七夕であり北斗七星であった。本章にも「『七』は北斗七星の影に操られる人生の宿命ということなのか」という言葉がある。だが『童子考』との重複を避けるかのように、七夕や北斗七星の記述はここでは控え目である。
正月七日の「七草粥」の習慣が、この日に飛んでくる唐土の妖鳥「鬼車鳥」(日本では「うぶめ」という)を追い払うために、俎板の上で七草をとんとんと叩くところから来ていると指摘しつつ、著者はこう書いている。
「凶」で結ばれる七月七日と一月七日。著者の「七」へのこだわりには理由がある。七月七日が著者の誕生日なのである。そして実は私の誕生日は一月七日である。まことに奇しき因縁というほかはない。
『ひとつ水』の奥付には、「一九九〇年七月七日発行」とある。
先生の御冥福をお祈りする。
【この書評が収録されている書籍】
『風流の図像誌』と『鶴屋南北』との間に『郡司正勝刪定集』(白水社、1990-92)の刊行という大きな出来事があり、先生はそれまでのお仕事を解きほぐし組み換えて、六つの領域に再配列することに専念された。「刪定(さんてい)」という言葉を私などははじめて教えられたのだが、著作集ではなく、あえて刪定集という表現にこだわったところに先生の確固たる美意識のようなものが感じられた。「かぶき門」「傾奇(かぶき)の形」「幻容の道」「変身の唱」「戯世の文」といった、それぞれの巻のタイトルの斬新さに一驚したのは、もとより私ひとりではあるまい。
第六巻「風流の象」だけは、しかし、『童子考』と、『風流の図像誌』を「山と雲――風流の図像誌――」という題名に変更して、そっくりそのまま収め、あと関係する論考を何篇か付け加えている。ここでは「刪定」は施されていないわけである。それほどにこれらの著作の内容にまとまりがあったともいえるし、先生が愛着をもたれていたともいえるだろう。
実際、退職後の先生は、芝居の創作・演出に執筆にと驚くほど奔放な活躍をされた。年齢を感じさせないパワーだったが、このお歳でなければできないようなお仕事でもあった。『童子考』『風流の図像誌』『和数考』は、比肩するもののない日本的宇宙論(コスモロジー)の三部作となった。体系とか集大成とかいった言葉を好まれなかった先生だが、これらの著作は日本的想像力の論理をめぐる、これもお嫌いだという言葉をあえて使えば、「郡司学」のまぎれもない集大成となった。
集大成にならざるをえなかったといってもいい。先生は、今度は日本の色について書きたいとおっしゃっていた。どんなに特異な色彩論、日本文化論が登場することかと期待に胸をふくらましたが、これはついに実現を見なかった。『和数考』が、先生の遺著となった。
さて、その『和数考』である。本書は、「一の章」から「十の章」までの十章に「算術の章」が付け加わり、「あと算」で締め括るという洒落た構成になっているが、「一の章」の冒頭に、こうある。
どうも一という字は数ではないのではないか。つねづね思うことがある。
うまい書き出しだ。数の話をしようとしながら数ではないという。思わず引き込まれる。
書き出しのうまさは、書物全体のおもしろさということにほかならないのだが、これは『童子考』や『風流の図像誌』についてもいえる。『童子考』は、こう始まる。
どうして消えてしまったのだろう。雛祭の頃になると、ときどき思い出すのだが、どこへどうしたのかわからぬままになってしまった紙雛があった。
『風流の図像誌』の「はじめに」は、こうである。
私の頭と胸のあいだあたりに、一つの聖なる静かな山が住むようになったのには、動機がある。
本文の「動く山」は、こういう書き出しである。
われわれには、山というと「山の如く動じない」動かないものだという一般的な固定観念があるが、古代人の考える山は、むしろ動くものではなかったかとおもう。
ごく個人的な思い出、私的な感慨が、「一般的な固定観念」の転倒にさりげなく結びつけられ、読者は不意打ちにも似た驚きとともに、たちまち郡司ワールドに引き入れられてしまう。名人芸といっていい。真似してできるものではない。私的な感慨が、しかし決して私的な感慨に終わることなく、読者は気がつけば普遍的な地平に立っている。著者の書き物には、いつもそういった趣きがある。個が普遍へと突き抜けるのだ。それは記述が驚くべき該博な知識に支えられているからである。
「一度いらして下さい」などというと、一度はいいが、二度とは来るなということにはならない。……一はそれだけで、二とは続かない。つまり数えられない「イチ」である。数字ではない「一」が日本にはあったことになる。
著者はこうして「天下一」「一の人」「一夜漬」「一枚看板」「裸一貫」「一蓮托生」など、おびただしい言葉を思いつくままのように挙げながら、「一」の意味圏を探る。西洋的な数のシンボリズムとは異なる。「一」をめぐる記憶と文献のフィールドワークのごときもので、実際、そこに引かれる文献たるや、『日本書紀』『信長記』『武江年表』『小笠原礼書』『宇治拾遺物語』、果ては荷風の『断腸亭日乗』に至るまで、緻密な知的作業の前提なくしては同じ場所に集められようもないものばかりである。
だが、なんといっても記憶と文献のフィールドの中心は、かぶきであって、著者はここで皿屋敷のお菊の亡霊の皿の数え方による時代と世話のいい回しの違いに言及している。「ひとつ、ふたつ」と数えると時代(時代物)、「一枚、二枚」と数えると世話(世話物)というわけだが、この違いの根本を著者はこう推測する。
おそらく、もと「ひとつ」は、数の一でなく、ものの発端を示す日本民族特有の語源の心意伝承があって、この世を曳きずっており、「いち」は外来語の数としての客観性をもち、この流れが、時代・世話の級のちがいを区別しているのではないかとおもわれる。
してみれば、「ひとつ」の意が「いち」を覆ったとき、「一」はたんなる数ではなくなるということになろうか。もっとも、中国十七世紀の芸術理論家、石濤(せきとう)の『画語録』に、「法は何(いずく)に於て立つや。一画に立つ。一画は、衆有の本にして、万象の根なり」とあるように、中国においても「一」は文字どおり「ものの発端」でありえた。だから厳密には、日本と中国の比較がなされなければならないだろうが、本書はあくまでも「和数」についてのエッセーであろうとする。「この世を曳きずっ」た日本の「心意伝承」が問題なのである。
「一まず一段落」という言葉で「一の章」を閉じようとした著者は、最後にこんな文章を添えている。
わたしの好きな数に入らない数に「一つ水」という語がある。
……〽いまは野澤の一つ水
見捨てられた水にちがいない。
著者は一九九〇年に『ひとつ水』と題する句集を出している。「見捨てられた水」という意味だったのだろうか。その本を私に下さるとき、著者は表紙の裏に、句集に収められた一句、
夕㒵(ゆふがほ)の一つ残りて星祭
と墨痕あざやかにしたためてくれた。この「一つ」は、たしかに数えられはするけれども、決して数の「一」ではない「ひとつ」であろう。
「星祭」とは、七月七日の七夕のことである。それで話は「七の章」に飛ぶ。
実は「七の章」だけが圧倒的に突出しているのだ。たとえば「二の章」が十二頁なのに対して、「七の章」は三十四頁に及ぶ。三倍近い量なのである。「二の章」の量の少なさは、「世に『二』ほど損な役回りはない」という書き出しで、ひたすら「二」の卑小性、矮小性、取るに足りなさを論じることに関係するかもしれない。「とかく『二』は負の数字である」とすれば、短くなるのも当然といえようか。しかし「二」が「負の数字」なら、「七」は「凶の数字」なのだ。そう著者は書き出している。
「ラッキー・セブン」などというが、西洋でも「七」は、めでたい数ではない。もと凶の数字であった。
一が数ではない、山が動くというのと似た論法である。黒沢明の『七人の侍』も然り。七人の天の使いであり、同時に災いをもたらすものだという。「七福神」も「七難」に対応する。「七生報国」「七変化」「この子の七つのお祝に」……。著者は「七」をめぐる「凶」の旅に出る。ちなみに、「七」歳は不完全の完結ということの物忌みの明けであるがゆえに「お祝」になるというわけである。
すでに著者は『童子考』において、「星の影」、「土佐の星神社」、「負の七数」、「七曜剣」と、たたみかけるように「七」について語っていた。中心は「星」のテーマ、つまり七夕であり北斗七星であった。本章にも「『七』は北斗七星の影に操られる人生の宿命ということなのか」という言葉がある。だが『童子考』との重複を避けるかのように、七夕や北斗七星の記述はここでは控え目である。
正月七日の「七草粥」の習慣が、この日に飛んでくる唐土の妖鳥「鬼車鳥」(日本では「うぶめ」という)を追い払うために、俎板の上で七草をとんとんと叩くところから来ていると指摘しつつ、著者はこう書いている。
本来はお祝い事ではなく、七月七日の七夕が、お盆を迎えるための禊ぎ祓いの日であったように、小正月を迎えるための祓いの日であったのである。
「凶」で結ばれる七月七日と一月七日。著者の「七」へのこだわりには理由がある。七月七日が著者の誕生日なのである。そして実は私の誕生日は一月七日である。まことに奇しき因縁というほかはない。
『ひとつ水』の奥付には、「一九九〇年七月七日発行」とある。
先生の御冥福をお祈りする。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
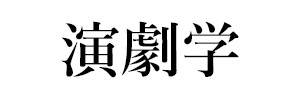
演劇学 1999年3月
ALL REVIEWSをフォローする




































