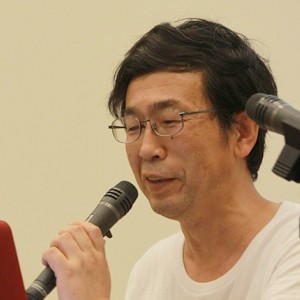後書き
『ロリータ』(新潮社)
ここで、『ロリータ』の翻訳について述べておく。アメリカでベストセラーになったすぐ翌年の一九五九年二月に、早くも大久保康雄訳が河出書房新社から上下二冊本として出版された。これがロリータ台風の日本上陸である。ところが、この翻訳に誤訳が多いという批判が起こって、同じく河出書房新社から改訳版が出された。そしてそれが新潮文庫に収録されたのが一九八〇年のことだった。
実は、あまり知られていないようだが、新潮文庫版は改訳版にさらに手直しを加えたものである。その結果、これまでに『ロリータ』の邦訳は、訳者は同一でも、わたしが確認しているかぎりでは少なくとも三種類存在していることになる。そして、初版と新潮文庫版とでは、同一訳者の手になるものとはほとんど思えないほど異なっている。今回、新訳を試みるにあたって、新潮文庫版をゆっくり読んでみたところ、細かいところまで正確な読みが行き届き、しかも日本語としてこなれた上質の翻訳であることを発見して驚いた(どうも初版本の評価を耳にしていたのが誤解のもとだったようだ)。教えられるところも沢山あったことをここに記しておきたい。
それでは、その新潮文庫版とこの新訳では、どこが違うのか。どういうところに新訳としての意義を求めたのか。翻訳者として意識した点を次に挙げておく。
新潮文庫版にあえて難点を指摘するとすれば、それはあまりにもこなれすぎている点である。これは長所でもあれば短所にもなる。こなれすぎると、つっかえるところがなくて、すらすら読めてしまう。すらすら読み終わってしまうと、記憶に残るのは物語の筋だけかもしれない。
いつのまにか、日本ではナボコフと言えば「言葉の魔術師」という形容がすっかり流通してしまったが、これは誤解を招きやすい言い方ではないだろうか。「言葉の魔術師」からすぐに連想するのは、華麗にして流麗な文章だと思うが、少なくともわたしがナボコフの文章を読んで受ける印象は、それとは微妙にずれている。ナボコフにしか書けない独特の文章とは、たとえば正統的な英国小説家の手になる端正な文章とはおよそかけ離れた、異形の文章である。普通の基準からすれば、まず間違いなく悪文の範時に入るはずで、センテンスは長く、めったに出会わない言葉と言葉が出会ったりする。その悪文が、悪文の範囲を超越して、誰にも書けない美文にまで高まる、それがナボコフ独特の魅力なのだ。
『ロリータ』にしてもその例外ではない。いやむしろ、『ロリータ』は文章のナボコフ度とでも呼ぶべきものが異常に高い作品だと言っていい。必然的に、力の入っている箇所では文章がかなり難解になり、手触りがごつごつしてくる。そこで、この新訳では、そういうごつごつした感触をなめらかに処理してしまうのではなく、そのまま伝えることを意識的に心がけた。
一例を挙げる。ナボコフの文章の特徴のーつとして、めったにお目にかかったことがないような新しい比喩表現がある。次の引用は、ハンバートの耳にロリータの声が聞こえてくるという内容の一文である。新旧の訳を並べて掲げるが、それはどちらの訳がいいかという問題ではなく、あくまでもカ点の違いを例示するためであることを念頭に置いていただきたい。
聴覚がしだいにローの声と波長が合いはじめ、彼女が昔の友だちに出会ったものだからと言っていることに気づいた。(大久保康雄訳)
私の聴覚はだんだんロー放送局に波長が合わされて、気がついてみると、ローは昔の女友達に出会ったとしゃべっているところだった。(拙訳)
ここは英文解釈教室ではないので原文を掲げることはしないが、簡単に言えば、拙訳は原文をいわば直訳して、比喩をそのまま残したものである。旧訳では、その比喩を消して意味だけを取り、わかりやすくすっきりとまとめている。拙訳を読んで読者がはてなと立ち止まるかもしれないのは、「ロー放送局」という部分だろう。つまりここでは、ラジオのつまみを廻してチャンネルを合わせているうちに、ノイズの中から次第にはっきりと放送が聞こえてくる、という比喩で書かれているわけだ(ついでに言うと、ナボコフはラジオ嫌いだった。ラジオから途切れることなくニュースや音楽が流れてくるのが気にさわったらしい)。いかにも時代を感じさせるが、こんな比喩を使った作家はナボコフの他にはいないのではないか、というのがわたしの言いたいことで、この比喩は記憶に残る。そういうわけで、比喩は消さないというのがこの新訳の基本方針のーつなのである。
批評家エドマンド・ウィルソンから、「ナボコフは稀で見慣れない言葉を使いたがる癖がある」と批判されたとき、ナボコフはこう反論した。「私は稀で見慣れないことを伝えようとしている」と。先に挙げたラジオの比喩は、その好例ではないだろうか。さらに話を広げれば、わたしの訳は、不思議な言葉が流れ出すナボコフ放送局に波長をなんとか合わせようとして、ラジオのつまみを廻しながら耳を傾けたものである。作家が発する言葉を聞き取ること。翻訳者の任務はつまるところそれではないかと思う。わたしが受信した言葉が、ノイズばかりになっていないことを祈るのみだ。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする