名古屋大学出版会The University of Nagoya Press
公式サイト: http://www.unp.or.jp/
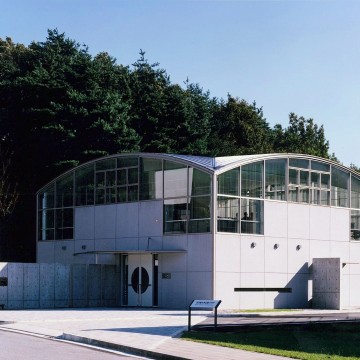
名古屋大学出版会(The University of Nagoya Press) 学術書の出版社です。2022年6月に創立40周年を迎えます。名古屋から、新たな魅力ある「知」を届けてまいります。※全国の書店でお取り寄せいただけます。もっと読む


「租税回避の多くは合法だ。しかし、まさにそれこそが問題なのだ」。これは2016年4月、アメリカのオバマ大統領(当時)が記者会見で語った言葉である…


黒澤明、溝口健二とともに、日本映画の三大巨匠の一人として数えられる小津安二郎。没後半世紀以上を経た現在でも、伝記や評論など関連書籍が国内外…


2020年10月、名古屋大学出版会は刊行点数1000点を突破した。その節目にあたるのが、700頁を超える杉原薫氏の大著『世界史のなかの東アジアの奇跡』だ…


「イスラーム・ガラス」の第一人者として国際的に活躍するも、2018年に急逝した真道洋子氏。その遺作となる『イスラーム・ガラス』がこのたび刊行さ…


現ウィルス禍にあって、医学史、科学史の書籍が読み直されています。19世紀のイギリスを舞台にした『病原菌と国家』は、科学研究が国家の政策や経済…


現代における科学史研究の古典――「テクノロジー」によって巧みに管理される事実と仮説の境界線本書は、1985年の刊行以来賛否両方向からの反響を喚起…


日本でも人気の哲学者ダニエル・C・デネット氏。1984年の著作“Elbow Room”(邦題『自由の余地』)がこのたび翻訳されました。原著出版から36年もたっ…


ホロコーストと原爆、まったく異なるこれらの出来事を結びつけて語ることにどのような意味があるだろうか。このたび邦訳が刊行された『ヒロシマ』の…


環太平洋地域の政治、経済、文化、科学技術に関する優れた著作に対して与えられる「大平正芳記念賞」。第36回となる今年は、6人の研究者が栄えある賞…


独自のスタイルで歴史記述の新たな可能性を探究するイヴァン・ジャブロンカ。邦訳第三弾となる『歴史家と少女殺人事件――レティシアの物語』がこのた…


20世紀の悲劇の連鎖のなか、二人はどのように生きたのか――繊細な文章と大胆な筋書きで紡がれる調査/物語著者の姓ジャブロンカは、ポーランド語で「…


2020年6月、チャールズ・テイラー畢生の大著『世俗の時代(A Secular Age)』の翻訳がついに出版されました。『自我の源泉』から『世俗の時代』まで…


ロボットにおける倫理的問題と、思考実験の実践例としてのSF本書は、人間の新たな隣人であるロボットをテーマにして、倫理学における議論を紹介した…


森林とは、いったいどのような存在だろうか。このたび、『里山の生態学』などの著書をもつ名古屋大学名誉教授・広木詔三による『森林の系統生態学』…


現下のウィルス禍では、さまざまな分野の専門家がまさしく命がけで奮闘している。科学技術を基盤とする今日の社会において、社会的に物事を決めよう…


強権的な政治手法に対し国際社会から批判の声も多いフィリピンのドゥテルテ大統領。そんな彼が「国家の歴史的不正義を認めたミンダナオ出身の初めて…


農業現場から得られた所領知(経験知)と諸科学との緊張関係著者の並松さんとは、学部と大学院で農学原論という同じ講座に席を置いた。評者の先輩に…


友情が同性愛とは区別できない可能性に迫る数年前、私の所属する大学の大学院入試で、「ホモソーシャル」についての用語解説を問題に出したことがあ…


左からも右からも歪んだイメージを押しつけられてきた「日教組」。インターネット上では今も、現実とかけ離れた言説が拡散されています。この組織に…


SDGsブームのいま、「持続可能性」を問う環境問題をいわゆる「環境好き」の人びとの考察対象にとどめず、統治・支配のあり方を議論するうえでの格好…