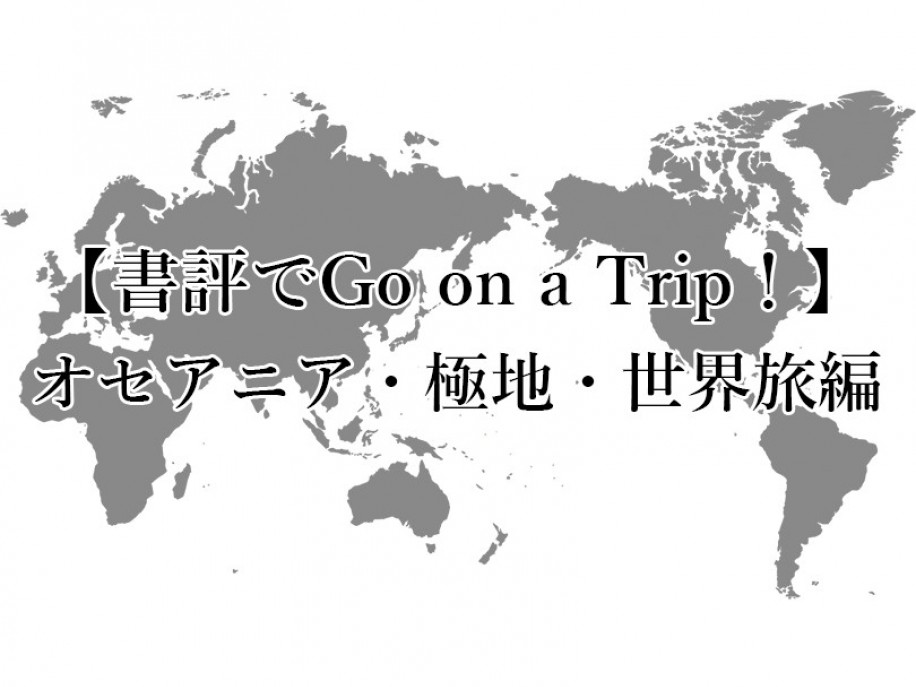読書日記
夏休み企画〈書評でGo on a Trip!〉南欧編

世界各地を〈書評〉で巡る〈書評でGo on a Trip!〉企画、続いては南欧編です!
※Special Thanks!:書評推薦者 くるくるさん、hiroさん、やすだともこさん
南欧にGo!
【スペイン】
■カルロス・ルイス・サフォン『天使のゲーム』(集英社)
評者:逢坂 剛前作『風の影』に次ぐ、〈忘れられた本の墓場〉シリーズの、2作目に当たる。舞台は、同じスペインのバルセロナだが、時代背景は1作目より15年以上前の、1920年代。若い作家ダビッド・マルティンは、コレッリという謎の編集者から、奇妙な原稿の注文を受ける。〈塔の館〉と呼ばれる、古い屋敷にこもったダビッドは、押しかけ助手のイサベッラという少女に、身のまわりの世話を受けつつ、執筆に取りかかる。(この書評を読む)
【スペイン】
■フリオ・リャマサーレス『狼たちの月』(ヴィレッジブックス)
評者:豊崎 由美「ぼく」の潜伏とサバイバルの日々を、作者のリャマサーレスは静かで端正な、もの悲しい文体で淡々と描いていきます。その”声”が、同胞同士が血を流しあい、故郷がフランコ側に提供されたドイツの新型兵器によって焦土と化す無念と、三年に及ぶ戦いで死んでいった人々への切々たる弔意を謳っているのです。(この書評を読む)
【スペイン】
■キルメン・ウリベ『ムシェ 小さな英雄の物語』(白水社)
評者:星野 智幸ウリベはまた、そのまま亡命してバスクに戻らなかった世界中のバスク人と、かれらを受け入れた世界中のロベールを、この小説で書こうとしたのだろう。その英雄たちの存在の証として。 (この書評を読む)
【スペイン】
■室井 光広『ドン・キホーテ讃歌―世界文学練習帖』(東海大学出版会)
評者:野谷 文昭「すでに書かれてしまっていることをめぐる読みの芸術に他ならない文学にあって作家はすなわち読者であるとする読者教の信者の一人に数えられてかまわない」という彼の言葉は、騎士道小説をめぐる読みからドン・キホーテが生まれたことや、『ドン・キホーテ』の読みからボルヘスの登場人物ピエール・メナールが生まれたことを踏まえている。(この書評を読む)
【スペイン】
■オルテガ・イ・ガセット『大衆の反逆』(白水社)
解説:久野収「大衆」人間は、自分たちの生存の容易さ、豊かさ、無限界さを疑わない実感をもち、自己肯定と自己満足の結果として、他人に耳を貸さず、自分の意見を疑わず、自閉的となって、他人の存在そのものを考慮しなくなってしまう。そして彼と彼の同類しかいないかのように振舞ってしまう。(この書評を読む)
【ポルトガル】
■ナイジェル・クリフ『ヴァスコ・ダ・ガマの「聖戦」: 宗教対立の潮目を変えた大航海』(白水社)
評者:水野 和夫歴史は「今」に至るまで水面下で脈々と繋がっている。それが1490年代、世界を変える三つの出来事として一気に水面上に噴出したのだった。グラナダ王国の消滅、コロンブスの「新大陸発見」、そしてヴァスコ・ダ・ガマの「インド航路発見」である。本書は三つの中でもガマの功績が大という結論を導く。(この書評を読む)
【ポルトガル】
■渡辺 京二『バテレンの世紀』(新潮社)
評者:原 武史著者によれば、それはこの国の支配者が、いち早くカトリック信仰のもつ危険性を看取したからにほかならない。現実の武力侵略ではなく、キリスト教による文化的侵略を恐れていたというのだ。(この書評を読む)
【ポルトガル】
■ルシオ・デ・ソウザ,岡 美穂子『大航海時代の日本人奴隷』(中央公論新社)
評者:旦 敬介江戸時代が始まる直前直後の時期には、ヨーロッパやアジアの各地、さらにはメキシコやペルーなど新大陸にまで、かなり多くの日本人の男女が奴隷や期限付きの契約使用人として運ばれて暮らしていた。その大部分が現代の言い方では人身売買に相当するが、そこにはポルトガル人の商人が深くかかわっていた。(この書評を読む)
【イタリア】
■ウンベルト・エーコ『薔薇の名前』(東京創元社)
評者:種村季弘北イタリア、ボッビオの町にほど近い山上台地の修道院内で、7日間のうちにつぎつぎに6人の修道僧が殺害される。(この書評を読む)
【イタリア】
■陣内 秀信『水都ヴェネツィア』(法政大学出版局)
評者:池内 紀たいていの人にヴェネツィアはイタリア観光の目玉である。…建築史家・陣内秀信にとっては、ここはごくふつうの人がふつうの生活をしている町である。ゴンドラ以外にも大運河には郵便船、ゴミ運搬船、霊柩船、救急船、引越船……ありとあらゆる用向きの船が走っている。(この書評を読む)
【イタリア】
■須賀 敦子『トリエステの坂道』(新潮社)
評者:森 まゆみこの本は著者が愛する詩人、ウンベルト・サバの住んだトリエステを訪ね、その暮らした町の坂を息を切らせて上り下りするところから始まる。サバの働いていたのは「ふたつの世界の書店」という名だ。著者自身が日本に生まれ育ち、イタリアの男性と結婚してその土地を愛し、書房の経営に参加し、再び日本に帰った。二つの世界をいつも往還している。(この書評を読む)
【イタリア】
■イタロ・カルヴィーノ『なぜ古典を読むのか』(みすず書房)
評者:高橋 源一郎いい作家はたいてい本を読むのがうまい。なぜなら、作家は本を作るのが本職で、だから、目の前の本のどこが本物の入り口か、どこが手抜き工事で、どこが天才の仕事なのか、経験上わかるからである。(この書評を読む)
【イタリア】
■マルクス・アウレーリウス『自省録』(岩波書店)
評者:四方田 犬彦マルクスは別のところで、たとえ死が身近に迫っていても、けっして慌てふためかず、いつもと同じ生活を送ることがいいと記している。それは逆にいうと、毎日を、これでお前は死んでしまっても後悔はないなといいきかせながら生きていくことでもある。 (この書評を読む)
【イタリア】
■ヤーコプ・ブルクハルト『イタリア・ルネサンスの文化』(筑摩書房)
評者:本村 凌二著者自身が語るように最もルネサンスらしい人間類型が「万能人」であるなら、視野の広さ、洞察の深さ、直観の鋭さ、さらに叙述の精彩さにとむ本書は、まさしく「万能人」史家の巨匠にしか描けない類稀なる名著である。本書は読者の人生をことさら豊かにしてくれるにちがいない。(この書評を読む)
【ギリシア】
■C・P・カヴァフィス『カヴァフィス全詩』(書肆山田)
評者:堀江 敏幸本当に長く待たされた一冊。現代ギリシア語による百五十数篇の詩を日本語に移し替えるのに、訳者は四十年の歳月を費やした。(この書評を読む)
【ギリシア】
■ホセ・カルロス・ソモザ『イデアの洞窟』(文藝春秋)
評者:豊崎 由美古代ギリシャのアテネで、野犬に食い殺されたとおぼしき若者の死体が発見される。だが、その見立てに不審を抱いた者がいた。それは「人の容貌や事物の外観を、それらがあたかもパピルスででもあるかのように読むことができる」〈謎の解読者〉の異名をとる男、ヘラクレス。若者が通っていた、哲学者プラトンが運営する学園の教師ディアゴラスの依頼を受けて調査に乗り出した彼の前に、しかし、第二、第三の死体が現れて――。(この書評を読む)
ALL REVIEWSをフォローする