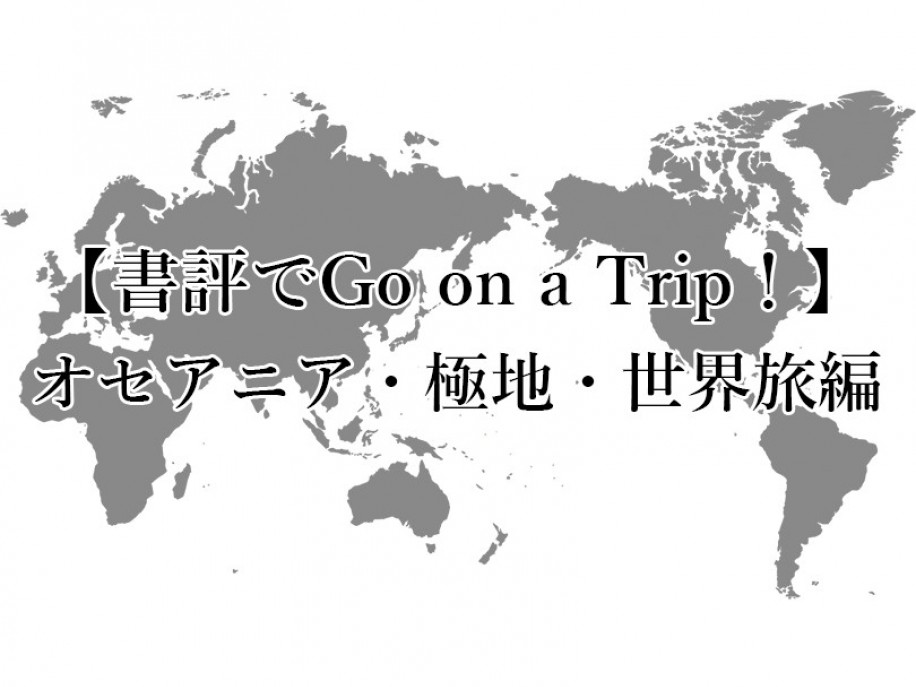読書日記
夏休み企画〈書評でGo on a Trip!〉アフリカ編
 世界各地を〈書評〉で巡る〈書評でGo on a Trip!〉企画、続いてはアフリカ編です!
世界各地を〈書評〉で巡る〈書評でGo on a Trip!〉企画、続いてはアフリカ編です!アフリカにGo!
【モロッコ】
■ポール・ボウルズ『雨は降るがままにせよ』(思潮社)
評者:牧 眞司無計画に「知らない街へ行ってみよう」などと思わないほうがいい。そんな衝動が素敵なできごとに結びつくのはお伽噺のなかだけで、たいていはろくでもない結果になる。もっとも「ろくでもない」というのは、あくまでも日常生活の規範に照らしてのことだ。未知の土地を訪れようなどと突然に考えたとき、すでにふつうの生活から逸脱しているのだ。(この書評を読む)
【モロッコ】
■ロラン・バルト『偶景』(みすず書房)
評者:橋爪 大三郎この作品の狙いを、題名が隠しているらしい。偶景(アンシダン)とは〈ミニ・テクスト、短い書きつけ、俳句、……すべて木の葉のように落ちてくるもの〉のこと。他のテクストについてのべる(記号学の)かわりに、直接のべること、ただしただの小説になることを拒む「小説的なもの」をつづることを、バルトはめざしている。(この書評を読む)
【モロッコ】
■四方田犬彦『モロッコ流謫』(筑摩書房)
評者:堀江 敏幸紀元前からさまざまな民族が奪い合い、一九二三年以後は列強八ヵ国の共同管理下に置かれ、関税が撤廃された自由貿易のコスモポリットな空間を第二次世界大戦後まで保持していたタンジェへの第一歩となるニューヨークでの出会いは、期待どおり第一章でたっぷりと語り直されている。著者にボウルズの翻訳を薦めたのがジム・ジャームッシュであり、住所も彼に教えてもらったこと、手紙を受け取ってタンジェに降り立ったはいいが、作家の家を見つけるのに多大な時間を費やしたことなど、かつてはほんの数行で片づけられていた細部が次々に明らかになる。(この書評を読む)
【アルジェリア】
■中条 省平『100分de名著 カミュ『ペスト』 2018年6月』(NHK出版)
前書き:中条 省平『ペスト』の作者アルベール・カミュの文学には、どんなに不条理で悲惨な状況を描いても、海と太陽が救いになるような、「向日性」の魅力があります。そうした感覚は、カミュが当時フランスの植民地だったアルジェリアの、地中海沿岸の町で生まれ育った事実と切り離すことはできないでしょう。(この書評を読む)
【エジプト】
■石原 慎太郎『行為と死』(新潮社)
評者:澁澤 龍彦『行為と死』の冒頭の「スエズ」の場面を読み出して、ゆくりなくも、わたしがまず頭に浮かべたのは、山中峯太郎の文体であった。短かい内的独白を挟みながら、歯切れのよい速度で、適度にハード・ボイルドな描写をつづけて行くところは、アンドレ・マルロオというよりも、むしろ、あのまことに日本的な冒険小説の大家、山中峯太郎そっくりと言うべきである。(この書評を読む)
【エジプト】
■ロバート・アーウィン『アラビアン・ナイトメア』(国書刊行会)
評者:豊崎 由美これは〈アラビアの悪夢〉をめぐるミステリーであり、冒険小説であり、都市小説であり、ボルヘスばりの迷宮小説であり、幻想小説であり、黒い哄笑を引き起こすコミック・ノベルであり、寓話であり、ありとあらゆる文学の楽しみを詰め込んだ、読み応えという点で申し分のない傑作なのだ。(この書評を読む)
【エジプト】
■古川 日出男『アラビアの夜の種族』(角川書店)
評者:豊崎 由美万能にして眉目秀麗(びもくしゅうれい)な若き執事アイユーブが、主人である知事に秘策を授ける。それは、読む者すべてを狂気に導くという伝説の本「災厄の書」を敵軍に献上すること。主人の許しを得たアイユーブは、エジプト一の語り部ズールムッドの力を借り、「災厄の書」の製作に着手する――。(この書評を読む)
【モーリタニア】
■小野 節子『女ひとり世界に翔ぶ ― 内側からみた世界銀行28年』(講談社)
評者:松原 隆一郎著者はジュネーブ大学の大学院で博士号を取った後、直接に世界銀行に就職した人。現場の実務を生々しく語る。砂塵(さじん)舞うアフリカ西部のモーリタニアで、現場の政情や貧困、文化に精通し、関係者をねばり強く説得しながら貸し出しを実施する情熱に打たれる。(この書評を読む)
【ガンビア】
■アレックス・ヘイリー『ルーツ』(社会思想社)
評者:丸谷才一,木村尚三郎,山崎正和木村 このクンタという人は、つねに自由を求めて何べんも何べんもトライするわけですね。同時に、自分の民族的な意識をいつも失わない。自分の民族に対する誇りをもっていますね。しかし、ああいった意識は、本当のアフリカ人のものだろうか、むしろアメリカ人の精神ではないかという疑問があります。
山崎 アフリカ人という概念は、彼らがアメリカにくるまでなかった概念なんですからね。(この書評を読む)
【ブルキナファソ】
■川田 順造『人類の地平から―生きること死ぬこと』(ウェッジ)
評者:鷲田 清一その、たしかな、奥行きのある語りは、東でも西でもない南の声、そう、アフリカの生活文化からの視線を入れた文化の「三角測量」と、個別への愛着を「一般化への強靱な視線」で支える「離見」(レヴィ=ストロースが世阿弥から学んだ視線)という、川田が長年にわたる西アフリカの生活経験のなかで培った構えからにじみ出てくるものだ。(この書評を読む)
【ナイジェリア】
■エイモス・チュツオーラ『やし酒飲み』(岩波書店)
評者:牧 眞司 人の死よりもやし酒が優先である。しかし、これからどうやってやし酒を確保したものか。死んだやし酒造りほどの名人はほかにいない。主人公はしかたなく、死んだやし酒造りを連れもどそうと旅に出る。(この書評を読む)
【ナイジェリア】
■チゴズィエ・オビオマ『ぼくらが漁師だったころ』(早川書房)
評者:旦 敬介そういう本当に幸福な家庭なのだが、いつも行動をともにしている十代の兄弟四人が、魔力をもつと信じられている一人の路上生活者との遭遇を機に分裂していき、いかにもその年代らしい浅はかな判断のくりかえしによって一家を不幸のどん底に陥れていく。(この書評を読む)
【ナイジェリア】
■チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ『男も女もみんなフェミニストでなきゃ』(河出書房新社)
評者:星野 智幸政治や思想の議論に幸福を感じ、ハイヒールを履き、口紅を重ね塗りし、好みの服を着る。「生活上の選択を決めるとき、『男性の視線』はきわめて二次的なもの」なのだ。
フェミニストとは、このように自分のことは自分で決める人のことだ。外からの構造的な圧力に屈さずに、自分が選択する権利を行使できる状態のことだ。(この書評を読む)
【コンゴ(旧ザイール)、スーダン】
■リチャード・プレストン『ホット・ゾーン』(飛鳥新社)
評者:速水 健朗1976年、アフリカのザイール(当時)、スーダンで多くの死者を出したのが最初のエボラの流行。当時はまだ知識もなく、医療関係者にも犠牲が出た。(この書評を読む)
【コンゴ・ルワンダ・ガボン】
■山極 寿一『ゴリラ』(東京大学出版会)
評者:鷲田 清一類人猿は「人類の過去を探る辞書のひとつ」なのだ。われわれ人類がくり返してきた衝突の悲しい歴史を<共存>の途(みち)へと切り替えるには、その類人猿がたどった<共存>の別の途から、あるいはまた「人類とは異なる自然の見方や利用法」から、うんと学ぶ必要がある。「われわれ人類はけっして最善の方法で自然と接してきたわけではない」からだ。山極はそう考える。(この書評を読む)
【ルワンダ】
■曽野 綾子『哀歌』(新潮社)
評者:鹿島 茂だが、本書をひもといた読者は、平和な日本では想像力の及ばない凄まじい憎悪と暴力が民族・部族という要因から生まれ出て、きれいごとの「友好」など一瞬のうちに吹き飛ばし、あっという間にホロコーストの悪夢へ至る現実に深く戦慄することになる。同時に、その黙示録的な描写を通して、人間存在の根源的な苦悩と悲しみを理解する。(この書評を読む)
【ケニア】
■ロバート・M・サポルスキー『サルなりに思い出す事など ―― 神経科学者がヒヒと暮らした奇天烈な日々』(みすず書房)
評者:斎藤 環著者はニューヨークで生まれ育ったユダヤ人にして無神論者。幼き日の夢はマウンテンゴリラになること。それが無理と知った彼は、妥協してヒヒの研究者となった。(この書評を読む)
【ケニア】
■三浦 英之『牙: アフリカゾウの「密猟組織」を追って』(小学館)
評者:武田 砂鉄現地で出会った、野生ゾウの保護活動に勤しむ女性が言う。「問題の解決方法は実はとっても簡単なんです。『象牙を買わない』。それだけなの」。(この書評を読む)
【ケニア・タンザニア】
■羽仁 進『とんでったら あふりか』(福音館書店)
評者:南 伸坊でてくる動物、ネコやヒョウや、フラミンゴやバッファローや、ライオンやゾウや、サイやキリンや、シマウマやウサギの、かわいくてイキイキしていること、表情のゆたかなこと。(この書評を読む)
【ソマリア】
■永井 陽右『僕らはソマリアギャングと夢を語る――「テロリストではない未来」をつくる挑戦』(英治出版)
評者:旦 敬介世界的な紛争に関しては、個人にはどうしようもないと諦めがちだが、小さなところから始めて積み重ねていけばたしかに少しずつ変えられる、改善できる、という強力なメッセージをこの本は発している。(この書評を読む)
【ジンバブエ】
■高尾 具成『特派員ルポ サンダルで歩いたアフリカ大陸』(岩波書店)
評者:小野 正嗣ジンバブエでは報道規制と年率10万%(!)のハイパーインフレに悩まされながら取材を続ける記者魂。マンデラ元大統領を語る言葉はまっすぐな敬意に満ち温かい。(この書評を読む)
【南アフリカ】
■宮内 悠介『ヨハネスブルグの天使たち』(早川書房)
評者:大森 望本書は全5話から成る近未来SF連作集。“歌姫”と呼ばれる少女型の日本製ホビーロボットDX9が軸となる。歌を歌わせることのできる電子楽器というか、初音ミクみたいなボーカロイド(音声合成ソフト)にボディを与えたような存在ですね。(この書評を読む)
【南アフリカ】
■ゾーイ・ウィカム『デイヴィッドの物語』(大月書店)
評者:大森 望白人支配層から差別され抑圧されていた黒人たちの闘争と解放の物語を描けば、それがナショナル・ヒストリーとなって一件落着とはいかない。南アには白人と黒人だけではなく、「カラード」という混血層が存在するからだ。この人々の〈歴史=物語〉を、アパルトヘイト以降の南ア文学は、どのように描けばよいのか?(この書評を読む)
【南アフリカ】
■J.M.クッツェー『モラルの話』(人文書院)
評者:沼野 充義老いの問題に焦点を当てながら、常識破りの奇矯な老母と、多少偽善的なところがあるにせよ、常識的に親孝行な子供たちの間のやりとりが描かれている。辛辣な味付けの喜劇として楽しめないこともない。しかし、クッツェーの「モラル」の真骨頂はその先にある。(この書評を読む)
ALL REVIEWSをフォローする