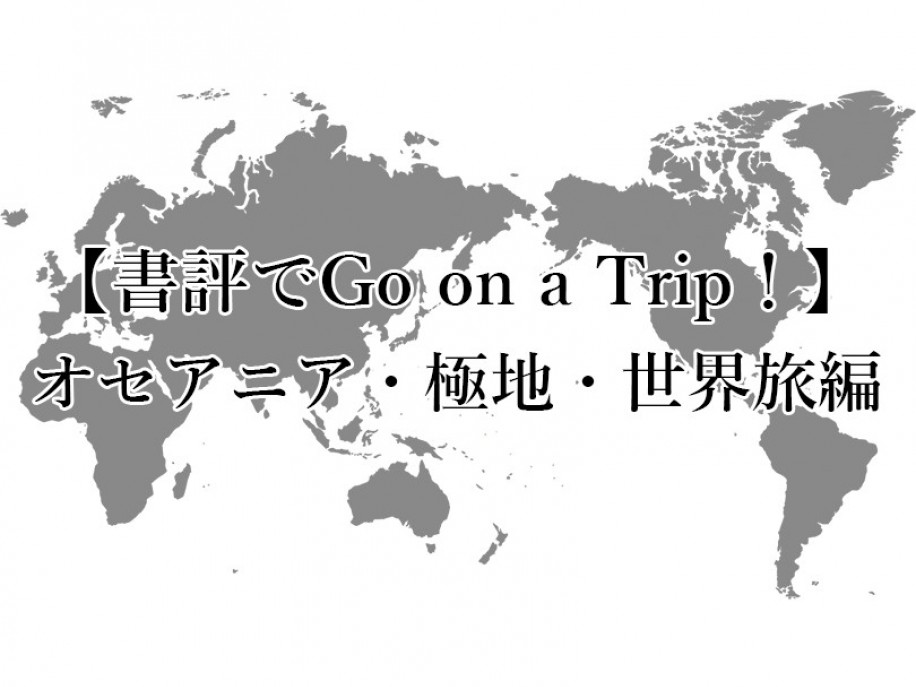読書日記
夏休み企画(書評でGo on a Trip ! )東欧・ロシア編
 世界各地を〈書評〉で巡る〈書評でGo on a Trip!〉企画、続いては東欧・ロシア編です!
世界各地を〈書評〉で巡る〈書評でGo on a Trip!〉企画、続いては東欧・ロシア編です!東欧・ロシアにGo!
【東欧諸国】
■沼野 充義・編『東欧怪談集』(河出書房新社)
評者:米原 万里常日ごろ潜在意識下に追いやって気づかないふりをしている強迫観念や幻覚という、人間の持つもう一つの果てしなく奥深く豊かな世界に引きずり込んでくれる。(この書評を読む)
【チェコ】
■ミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』(集英社)
評者:辻原 登クンデラの小説技法の新しさを云々されることが多いが、それはあまり大したことではないと思う。デュマの『三銃士』が面白いように、クンデラの小説にも、堪えられない旨さがある。(この書評を読む)
【チェコ】
■ライナー・シュタッハ『この人、カフカ?:ひとりの作家の99の素顔』(白水社)
評者:池内 紀高校卒業試験でカンニングをするカフカ、毎晩新式の体操をしているカフカ、嘘をつこうとするとヘマをするカフカ、女の子にすぐ惚れてしまうカフカ……一人の誠実で、やさしく、不器用な青年が浮かび上がる。(この書評を読む)
【チェコ】
■ミハル・アイヴァス『もうひとつの街』(河出書房新社)
評者:小野 正嗣実際、この本の語り手と同様、我々ははじめ目を疑うだろう。視界に立ち現れてくるのは、プラハ城やカレル橋など確かに〈あのプラハ〉だ。しかしそうした光景を描いているはずの文字が、異教の神々を祀る祭典で奉納されるにふさわしい官能的な舞踏を踊り出す。言葉はもはや外側から対象を記述するのに倦んで、対象の内部に、そして我々の視線の片隅に隠されていた思いも寄らぬ空間を次々と明らかにする。(この書評を読む)
【チェコ】
■デレク・セイヤー『プラハ、二〇世紀の首都:あるシュルレアリスム的な歴史』(白水社)
評者:鹿島 茂遅れてきたがゆえにいきなり二〇世紀の最先端に躍り出たチェコ・アヴァンギャルドは廃墟の予感とともに誕生し、戦後は共産党支配という究極の悪夢を生きた後に再生するという二〇世紀の首都にふさわしい運命を辿ったのである。(この書評を読む)
【ハンガリー】
■アンドラーシュ・シフ『静寂から音楽が生まれる』(春秋社)
評者:堀江 敏幸ハンガリー出身のピアニスト、アンドラーシュ・シフの長大なインタビューとエッセイを二部構成で収める本書は、話し言葉と書き言葉が補完しあい、深いところで共鳴するように、つまり後者を前者の自註と読むこともできる、読者にとってありがたい構成になっている。(この書評を読む)
【ハンガリー】
■アゴタ・クリストフ『悪童日記』(早川書房)
評者:辻原 登表面無邪気をよそおいながら、底意地悪く、復讐心の強い、あらゆる法律を軽蔑し、そのくせ同情心もかねそなえた子供の冒険を描いた小説ジャンルのひとつ、悪漢小説の系譜につながるものとしても読んだ。(この書評を読む)
【ルーマニア】
■ジュール・ヴェルヌ『カルパチアの城 ヴィルヘルム・シュトーリッツの秘密』(インスクリプト)
評者:若島 正ヴェルヌの小説を読むことで、小説そのものがスペクタクルつまりは見世物だった、ヴェルヌが執筆していた十九世紀後半から二十世紀初頭にかけての、興味尽きない時代へと旅をすることができる。(この書評を読む)
【ルーマニア】
■ミルチャ・エリアーデ『ムントゥリャサ通りで』(法政大学出版局)
評者:牧 眞司描かきだされた驚異は単純だが力強く、読み手の心に響きわたる。ずっとむかしから知っていたはず、あるいは、夢のなかでいつも見ているのとおなじだ――そんな気持ちに満たされる。(この書評を読む)
【ルーマニア】
■ヘルタ・ミュラー『狙われたキツネ』(三修社)
評者:阿刀田 高1989年の冬、市民の暴動を機に革命が起こり、チャウシェスク大統領の死刑を経て新しい体制への移行を実現させた。本書はこの時期の庶民の日常を綴った小説。(この書評を読む)
【ブルガリア】
■服部 文昭『古代スラヴ語の世界史』(白水社)
評者:出口 治明古代スラヴ語はブルガリアで定着する。そして、9世紀末に新たなアルファベットであるより書きやすいキリル文字が出現したのである。(この書評を読む)
【ボスニア・ヘルツェゴビナ】
■クリストファー・クラーク『夢遊病者たち 1――第一次世界大戦はいかにして始まったか』(みすず書房)
評者:池内 紀セルビア政府に対するオーストリアの最後通牒と覚書(書簡)のくだりだが、草案の作成が、あまり地位の高くない参事官で名文家として知られていた男爵にゆだねられた。「誠実で善意の人」が、歴史的災厄をもたらすチェスゲームのコマになった。(この書評を読む)
【ポーランド】
■オルガ・トカルチュク『昼の家、夜の家』(白水社)
評者:沼野 充義全体主義や社会主義の大きな物語の崩壊後、過去の遺産を夢のかけらのようなものに分解し、美味しい料理にまでしてくれる――それは少々毒の入った、危険な料理なのかも知れないのだけれども。(この書評を読む)
【ポーランド】
■スタニスワフ・レム『ソラリス』(早川書房)
評者:大森 望古今東西のSF作家の中で、最高の知性の持ち主は誰か? 作品から判断する限り、最有力候補は、ポーランドのスタニスワフ・レム。その天才が、人類とは異質な知性を正面から描き出した『ソラリス』は、近年のオールタイムベストSF投票で不動の1位を保つ名作中の名作。(この書評を読む)
【ポーランド】
■ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』(共和国)
評者:高遠 弘美明日への希望も断たれたなかで、囚人たちは各自が得意な分野について講義をし合うことを思いつく。それがせめても人間らしさを失わず、精神の荒廃から自分を守る方法であった。チャプスキが選んだテーマは絵画と文学、そしてプルーストの小説だった。(この書評を読む)
【ポーランド】
■ステファン・グラビンスキ『動きの悪魔』(国書刊行会)
評者:古屋 美登里著者は「ポーランドのポオ」とも呼ばれていたそうで、文章の華麗さ、錯乱した精神の発露、にじり寄る死の気配など、確かに19世紀のポオの香りを彷彿させるところがあります。なにより魅力的なのは、機関車の力強い動きと作中におけるその役割でしょう。機関車自体が一種の凶器であり狂気であり、驚喜ですらあるのです。(この書評を読む)
【ベラルーシ】
■小梅 けいと/スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』(KADOKAWA)
評者:中条 省平『戦争は女の顔をしていない』は2015年にノーベル文学賞を受けたベラルーシの女性作家スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの最初の作品で、第2次世界大戦に従軍したソ連の500人以上の女性の聞き書きをまとめたルポルタージュです。このドイツとの戦争でソ連の国民は約2700万人が死んでいます。ソ連は第2次大戦の最大の犠牲国なのです。この恐るべき総力戦のなかで、ソ連の女性は自ら志願して戦場に身を投じました。(この書評を読む)
【ロシア】
■ゴーゴリ『外套・鼻』(岩波書店)
評者:島田 雅彦ドストエフスキーはかつて「我々は皆『外套』から生まれてきた」といった。ロシアの散文は、ゴーゴリ以後、民話の時代から小説の時代に入った。近代ロシア文学の黄金期それはロシア帝国の版図拡大と重なる。(この書評を読む)
【ロシア】
■沼野 充義『チェーホフ 七分の絶望と三分の希望』(講談社)
評者:山崎 正和偉大な天才の照れ性には、天も加担するのかもしれない。死の床で彼は妻に最期の一言を呟いたが、それは「私は死ぬ」というドイツ語にも聞こえ、「こんちくしょう」というロシア語にも聞こえる言葉だったという。(この書評を読む)
【ロシア】
■ウラジーミル・ソローキン『愛』(国書刊行会)
評者:豊崎 由美死体愛好、スカトロジー、スプラッター趣味、文体破壊といった掟破りの技法をふんだんに使って、ソローキンは文学の廃墟を現前させる。それは、しかし、不毛な行為ではない。人間には廃墟を美しいと感じてしまう感性もあるのだから。しかも、これは文学の遺産を取り込んだ上での戯れだ。(この書評を読む)
【ロシア】
■サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ『スターリン―赤い皇帝と廷臣たち』(白水社)
評者:楠木 建今から振り返れば、スターリンは20世紀を代表する大悪人といってもよい。しかし、桁外れのリーダーが出てきたとき、どこまで人間社会をコントロールしてしまうのか、その恐ろしさをまざまざと教えてくれる。 (この書評を読む)
【ロシア】
■米原 万里『ロシアは今日も荒れ模様』(講談社)
評者:井上 ひさしその意味で本書は〈爆笑しながら読むロシア現代史〉として、のちのちまで第一級資料として引用されるはずである。(この書評を読む)
【ロシア・東欧】
■佐藤 優『十五の夏』(幻冬舎)
評者:本村 凌二本書には読者をして自分の人生をふりかえらせる力がある。あらためて自分がほんとうに好きなものは何であるのかを問い直してみたくなる。まぎれもなく青春紀行文学の傑作である。(この書評を読む)
【カザフスタン】
■岡 奈津子『〈賄賂〉のある暮らし:市場経済化後のカザフスタン』(白水社)
評者:沼野 充義聞き取り調査の対象となったのは、弁護士、政党幹部、教師、校長、運転手、元内務省職員、看護師、主婦、年金生活者など、エリートから市井の弱者まで、実に様々。社会の断面が広く浮かび上がってくる。(この書評を読む)
ALL REVIEWSをフォローする